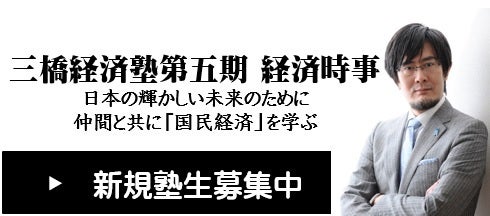
株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
三橋貴明のツイッター
はこちら
人気ブログランキング
に参加しています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
『お金の担保①』三橋貴明 AJER2016.9.20(7)
https://youtu.be/sjOa8Z-ezqA
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
9月20日、「WJFプロジェクトからの刺客 よしふる」(そもそもWJFって、何のこと? わたしは(W)、ジャマイカの(J)、フラワー(F)の略?)と名乗る者からメールが来たのですが、安倍政権の新自由主義的政策に反対しないと(していますが)、564、だそうです。
だっせ~っ(心の底からの「嘲笑」)。
何が、564ですか。堂々と「殺す」と書けばいいじゃないですか。いざというときに言い抜けするために、「殺す」ではなく、「564」と書いているわけですね。
すっげ~、惨め。しかも、わたくしだけではなく、藤井先生や施先生も「564」だそうです。
懸命に自分を守っている文章に、超爆笑しましたwww。そんなに自分が大切なら、メールなんてしてこなければいいじゃんw。
さらに、三橋経済塾にも「スパイ」を忍ばせているとのこと。年間6万円も払って、ご苦労様ですね。頑張って下さい。
さて、日本銀行が、金融政策決定会合を開き、「目で見る金融緩和の「総括的な検証」と長短金利操作付き量的・質的金融緩和」」というレポートを発表しました。
大変興味深いのですが、いつの間にか日本銀行はインフレ率の定義を、これまでのコアCPI(生鮮食品を除く総合消費者物価指数)から、「除く生鮮食品・エネルギー」に変更していました。つまりは、コアコアCPI(食料(酒類除く)及びエネルギーを除く総合消費者物価指数)に変更していました。
「インフレ率をコアCPIから、コアコアCPIに変えろ」
とは、わたくし共が以前から主張していた話なので、それはそれで結構なのですが、きちんと「説明」する必要があるはずです。
いずれにせよ、直近のデータでコアコアCPIは+0.3%に過ぎず、元々のインフレ率の定義であるコアCPIでは▲0.5%。三年半が経過し、インフレ目標2%の達成にはほど遠い状況であるのは間違いありません。
9月21日の日銀金融政策決定会合では、日銀当座預金残高の金利を▲0.1%、長期国債買入れも約80兆円で据え置き、総じて現状維持となりました。この判断は、正しいと思います。
『甘い「日銀バズーカ」の総括、高まりにくい株高・円安の期待
http://jp.reuters.com/article/cross-mkt-eye-idJPKCN11R1LV
日銀の「総括的検証」に対し、市場では冷ややかな声が少なくない。バズーカと呼ばれる「量」の政策効果に対する評価が甘かったためだ。大胆な緩和策は目標に達せず失敗したとの見方が市場では多いが、今回の検証では一定の効果があったと評価した。日銀と市場の認識ギャップは埋まらないままで、今後の追加緩和においても株高・円安の期待は高まりにくいとみられている。(後略)』
予想通り「玉虫色」の、分かりにくい総括になりましたが、日本銀行はインフレ目標を達成できなかった理由として、
(1) 2014年夏以降の原油価格の下落と消費税率の引き上げ後の需要の弱さ
(2) 2015年夏以降の新興経済の減速とそれを受けた世界的な金融市場の不安定化の逆風
と、これまた微妙な言い回しで説明しています。「消費税率引き上げ」という言葉が入っていることは評価できますが、日銀のレポートを見ると、日本の予想物価上昇率(期待インフレ率)が上昇しない理由として、
『予想物価上昇率(人々が予想する物価の上がり方)は、①「中央銀行の目標である2%に向かっていくだろう」という予想の要素(フォワードルッキングな期待形成)と②「過去の物価状況が続くだろう」という予想の要素(適合的な期待形成)の2つで決まります。
日本の場合、ほかの国に比べて、②の要素が強い、つまり過去の物価上昇率に引きずられやすいといわれています。
その理由はいくつかありますが、春闘など日本の賃金交渉の際、「前年度の物価上昇率」が勘案されることもそのひとつです。米欧では、先行き数年間の賃金を交渉することが多いため、中央銀行のインフレ目標(だいたいどの先進国も2%です)が賃金決定の重要な要素になっています。』
と、相変わらず「期待インフレ率」を前提にした「はずだ」理論に沿っており、レポートでは「財政」という言葉が出てきませんでした。
もっとも、黒田総裁は会見で、
「政府の財政運営、成長力強化の枠、取り組みとの相乗的な効果によって、日本経済をデフレからの脱却と、持続的な成長に導くものと考えております。」
と、語っており、「問題」が何なのかは認識しているように見えます。
要するに、デフレは「貨幣現象」とやらではない。「総需要の不足」であり、日銀の金融政策だけでは限界があり、政府の財政(需要創出)が必要であるということを認めたわけです。
日本銀行は、今回の「総括」で、金融政策の目標を「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」に変更しました。
何を言っているか分からないと思いますが、日銀のレポートから引用すると、
『具体的には、物価上昇率の実績値が安定的に2%を超えるまで、通貨供給量(マネタリーベース)を増やし続けると約束することにしました。これによって、「2%が実現する」ということに対する人々の信認を強めることを狙っています。
日本の通貨供給量は、経済規模対比で80%と欧米の4倍です。これがあと1年少し経つと100%を超えていきます。その位大規模な金融緩和を、実際に「2%超」の物価上昇を目にするまで続けるということです。』
とのことでございます。
勘違いしている人が多いですが、わたくしは日本銀行の金融緩和に反対したことは一度もありませんし、これからも反対しません。(マイナス金利の拡大は反対します。単に、銀行を痛めつけるだけで終わるので)
とはいえ、
【日本国債所有者別内訳(総額は955兆円)】

http://members3.jcom.home.ne.jp/takaaki.mitsuhashi/data_53.html#hoyu
からも分かる通り、銀行(預金取扱機関)が保有する国債が、尽きつつあります。現在の年間純増80兆円の量的緩和(日銀の国債買取)は、二年間は継続できないでしょう。
デッドライン、つまりは「日銀のXデイ
」が近づいている状況で、何を悠長なことを言っているのか、という感じです。
ポイントは、お分かりでしょう。日本がデフレから脱却できない主因は日本銀行の金融政策ではなく、政府の財政出動が「不十分」という点に尽きるのです。そもそも、安倍政権は今年の6月1日まで、財政を縮小する緊縮財政を強行してきました。
問題は日銀ではなく、政府にあるのです。
無論、安倍政権はようやく(三年間、間違えた挙句)財政拡大の方向に転じています。この流れを日銀のレポートで後押しして欲しいと願ったのですが、予想通りそこまでは踏み切れませんでいた。
いい加減に、認めましょ。
デフレは貨幣現象(お金の量が足りない)ではなく、総需要の不足なのです。モノやサービスの購入が足りないのです。
この「事実」を政府が認めない限り、我が国のデフレーションは終わりません。
しつこいですが、デフレは貨幣現象とやらではなく、「総需要の不足」なのです。
「デフレは貨幣現象ではなく、総需要の不足である」にご賛同下さる方は、↓このリンクをクリックを!
人気ブログランキングへ
◆本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。

◆関連ブログ
◆三橋貴明関連情報
Klugにて「三橋貴明の『経済記事にはもうだまされない』」
連載中
新世紀のビッグブラザーへ ホームページ
はこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」
は↓こちらです。

