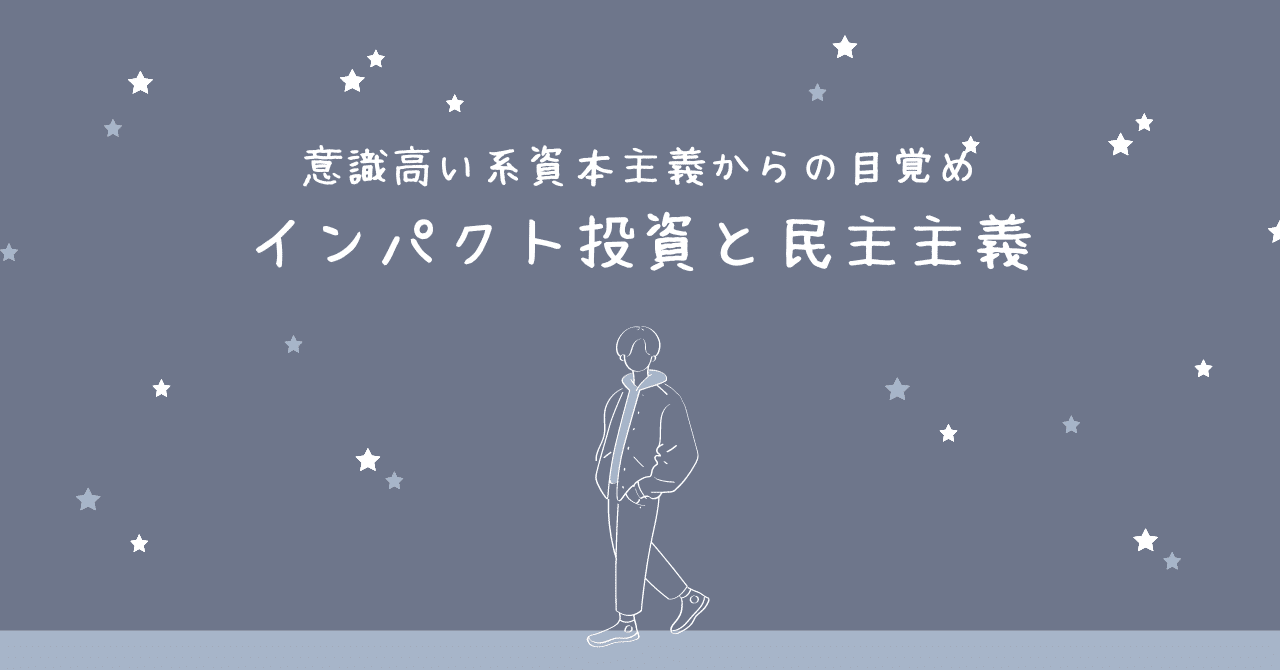面白い記事を見つけたのでシェアしたい。
記事のタイトルは、題名の通りである。
内容をかいつまんで言うと、以下の通りである。
アメリカで、金融機関や企業幹部によるESGの悪用が横行しているという。
環境(E)と社会(S)、ガバナンス(G )。財務だけではない側面を評価して投資先を選んだり、議決権行使などを通じて投資先に取り組みを促したりするのがESG投資だ。
そうした課題に取り組んだ企業の方が事業の持続性が高まり、不祥事などのリスクも下がり、長期的に見れば株主にとっても利益になるという考え方に基づく。…
(中略)
米経済界では19年以降、株主重視の行きすぎが格差拡大や気候危機につながったとして、従業員や顧客、環境など幅広いステークホルダー(利害関係者)に配慮する資本主義が掲げられ、…
(中略)
…
「ESG投資はエリートが作り出したもので、金融機関は金もうけのためにESG投資をやっている。…」
(中略)
環境対策が見せかけだけで実態が伴わない「グリーンウォッシュ」も反ESG感情に拍車をかける。
(中略)
ESGを隠れみのに、企業幹部が巨額報酬を得ている実態も浮かび上がった。
(中略)
純粋な財務とは別の観点で企業の価値を評価するESGは、そもそもあいまいさを含む。金融業界や企業エリートが、そのあいまいさを悪用して私服を肥やしているのではないかーー。
(中略)
ESG投資の賛同者は「ウォーク(目覚めた人)」として共和党保守派などから揶揄されている。日本語なら「意識高い系」というほどの意味だ。
(中略)
あまりの逆風に、ESG投資の拡大に旗を振ってきた世界最大の運用会社、ブラックロックのラリー・フィンク会長兼CEOも音を上げた。「(ESG投資という言葉は)政治的になりすぎた。もう使わない」
----------------------
アメリカでは上記のような流れが今強くなっているという。投資額も減っている。恐らく、社会的インパクトは今後も課題でなくなることはないと思われるが、環境など、耳に心地よい言葉を生み出してきた人々、それらを投資や企業倫理に絡めて用いようと企図する人々が、一部の社会的なエリートであり、経済的には投資家、資本家に当たる、恵まれたグループに属する人々であることに間違いない。
ESGを謳う以上、相応のリターンや結果があればよいが、言葉巧みに投資家を引き寄せるだけでは信頼を失ってもやむを得ない。
------------
なお、上のブログに紹介されていた Woke Capitalism の邦訳本も関連本として面白そうだったので紹介しておく。
上記ブログより
「多額(100億ドル)の寄付を行う一方で租税回避を行うアマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏などが例として挙げられ、意識高い系資本主義の矛盾、いや、”経済合理的な”倫理的行動が多く指摘されている。」
-----------
資本主義経済も、国による租税制度も、それを巧みに利用できる社会的・経済的強者の立場にある人々と、そもそも消費文化に翻弄されやすい場所にいて、蓄財の余力も能力ついぞ獲得しえないであろう社会的弱者の立場にある人々とを、入れ替えるほどの力は、持ちえない。
にもかかわらず、人は倫理的でありたいと思う。そういう生き物なのである。
「経済合理的な倫理的行動」というフレーズが面白い。倫理と経済の関係性。ゆとりのある人ほど倫理を求めるようになる。
蓄財はしたいが、「善」行為も好き、というのは、人間の特質だ。
きっと神様がいたら、まず倫理を優先せよ、そうすれば経済的合理性は自ずとついてくる、と言うはずだ。
ところが富の額が大きければ大きいほど、手放しずらくなるのが人の性でもあるという、ジレンマがここにある。
人であるが故の、永遠の悩みの一端が表れた内容であった。