猛暑復活の8月2日。
いつもの神田明神と湯島天神の参拝を済ませてから、「浅草六区」に行ってきた。
我が家からだと、歩いて50分程度だ。
ここでいう「浅草六区」は、旧い名前で、浅草寺の東側の繁華街のことだ。
浅草ROXで買い物があり、そのついでだ。
浅草に来るたびに思う。
ここは東京かと。
ここの空気、というかこの肌にベタつく感じ、は何だろう?
日本のいろいろな時とか場所が混在する異空間、あえていえば東京の大阪、
のように思えてしまう。
今昔 浅草六区 異空間
フランス座 エロと漫才 昭和録
「浅草六区」。ウィキペディアで調べた。要旨はこうだ。
「浅草寺周辺の盛り場は元禄時代の頃からで、やがて江戸最大の規模に発展した。
明治時代になり、1873年3月、都市公園をつくる目的で浅草寺周辺を「浅草公園」と命名、歓楽街を形成した。
1884年、公園地は東京府によって一区から六区までに区画され、その歓楽街は「浅草公園地第六区」となった。
1890年に建設された凌雲閣は通称「浅草十二階」と呼ばれた高層ビルで観光名所となったが
1923年9月1日の関東大震災で崩壊した。
1945年東京大空襲で一帯は炎上したが、終戦後すぐに再建され、芸能の殿堂・一大拠点となった。
1950年代後半に最盛期を迎えたが、テレビ時代を迎え、1964年(昭和39年)の東京オリンピック以降は
新宿、渋谷、池袋等の方面に若者の文化が芽生えると、人通りは激減、
若者世代の嗜好と合わなくなった多くの施設が閉館、
1954年には10軒もあったショー劇場も次々と閉館、ロック座、カジノ座、浅草座が辛うじて残る状況となった。
六区の斜陽に歯止めを掛けるべく、地元の「浅草おかみさん会」等の下支えも始まったが、
2012年浅草六区の最後の映画館5館が相次いで閉館した。
近年は外国人観光客も多く、観光客向けのホテルやお土産屋も多くみられるようになった。
2019年9月には特区に指定され、週末に全国各地のお祭りを誘致する取り組みも始まった」
浅草六区は、かつては、東京最大の繁華街であり、演芸の中心地だったのだ。
たとえば、太平洋戦争前、1937年の浅草六区はこうだ。
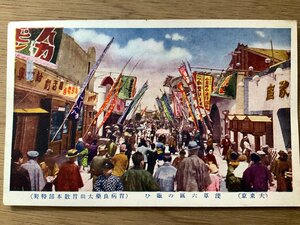
どの施設ものぼりをたて、カラフルな大看板を掲げて、
そして、いまならではのSNS発信をガンガンやれば、
戦前の賑わいに近づけないものか...
いま、この通りで、劇場として確認できるのは...
まず、浅草演芸ホール。
きょうは、「笑点」メンバーの三遊亭小遊三、春風亭昇太も出演するようだ。
お代は3000円。名人たちの噺としたら安いものかもしれない。
同じ建物に、フランス座東洋館。
落語は演芸ホール、いろもの、漫才はフランス座東洋館だ。
そもそも、いろものとは、落語の添え物の芸のような位置づけったようだ。
ここでは、むかしはストリップがメインで、その合間に漫才をやっていたとか。
個人的には、45年前、東京に出てきて行った新宿OS劇場の興奮が蘇る。
ネットで調べると、
渥美清、由利徹、東八郎、それからビートたけしも、ここから出世しているそうだ。
それから、ロック座。ストリップ劇場だ。
ストリップ小屋は、いまや文化遺産といってもいいだろう。
きょうは、浅草でも、この浅草六区のいまのレポートだけにとどめよう。
暑いし...。
浅草は、さまざまな顔をもっている。
これからは、その残りの顔に、たちどまってゆくつもりだ。



