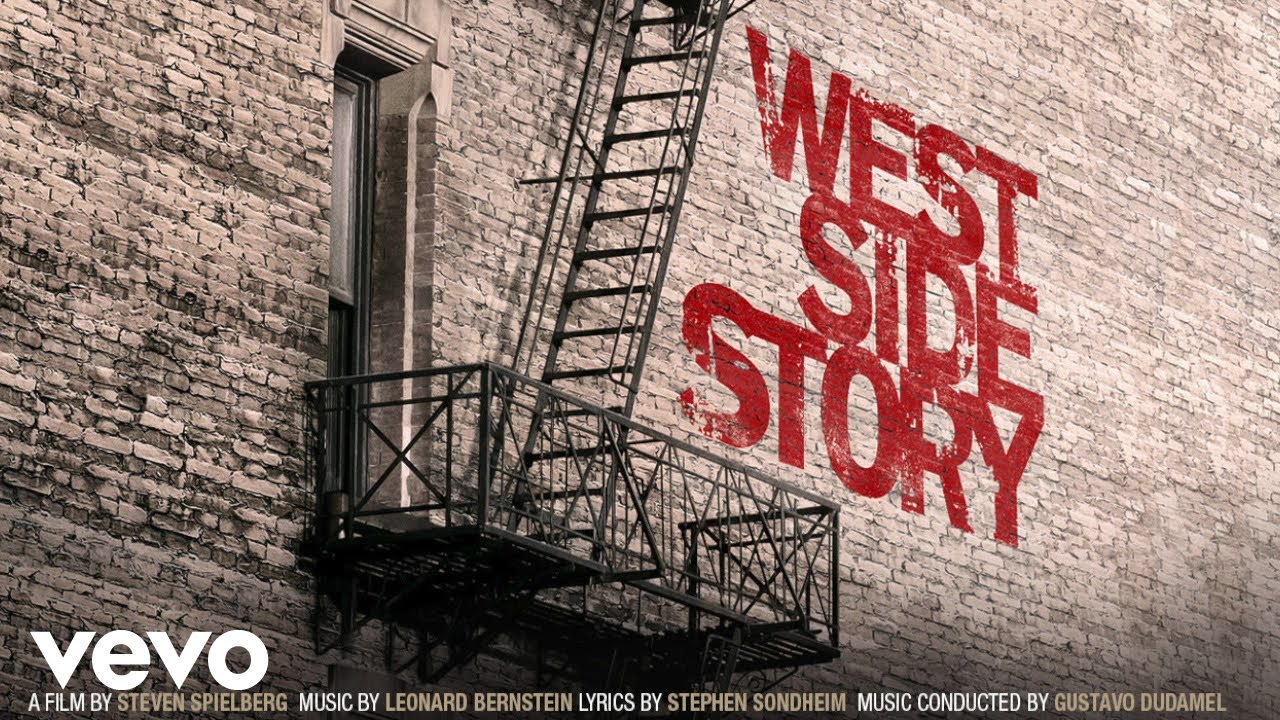今回の再映画化された『ウエスト・サイド・ストーリー』
今だから表現できる脚本(演出)を加えたことで、何故再びウエストサイドなのか、なぜ今のタイミングでウエストサイドなのかに答える内容に仕上がっています。
👏👏👏👏👏
観たら、きっと観ている最中にこの『ウエスト・サイド・ストーリー』の再映画化が大成功で、より訴えてくるものがダイレクトに響いてくる素晴らしい作品であることがわかります。
公開期間も短いし、上映館も少ないけれど、見逃さないでほしい、観るべき映画です。
今、私たちが一番に望む平和を訴える物語でもあります。もう一度、新たにアカデミー賞を受賞して欲しい映画です。
絶対に映画館で観てほしいので、極力ネタバレは避けますね。
本当に大きなスクリーンで観ていただくと舞台でミュージカル作品を観ているように1曲毎に👏したくなります。誰も映画館ではしていないので私は神式の葬儀の時のように音を立てない拍手をしていました。
レナード・バーンスタインの素晴らしい名曲はオーケストラ演奏でインストゥルメンタルを含めほぼ全曲、曲順通りですがところどころ1961年版の設定と違う人物が歌います。それが今回の脚本(演出)の見事なところだと思います。
1961年版は悲劇のなかにも当時のシークエンス、ミュージカルのきれいな、ふんわりしたところもあります。観ている側はそれがミュージカルの手法のようにも思っていましたが、2021年版映画のスティーブンスピルバーグは具体的に現実味を加えることで、ロミオとジュリエットの甘い悲しいおとぎ話ではなくアメリカの過去の差別でもなく、今も同じことが世界各地で起きていることを伝えているんだと感じました。
最初にブロードウェイの舞台で上演が始まったのが1957年だそうで、映画の最後にも1955年、1956年、1957年のバーンスタインのクレジットがあったようにみえました。
スピルバーグはちょうどその時代のニューヨークをリサーチしてウエストサイドの貧困層の移民たちの具体的な環境を舞台にしたことで今回、観ているこちら側が、これが単なるロミオとジュリエットの現代版ではないこと、町の素行の悪いガキのギャング団の抗争物語でないこと、今もニュース等で海外から届く事柄と時間も場所が違っても共通した問題であることが身近な出来事のように感じられます。
再映画化になぜなんだろう、と思っていました。
コロナ渦に中止要請を受けほとんどの公演が中止になった豊洲の回る舞台のウエスト・サイド・ストーリー(IHIステージアラウンド東京版)も観る前はそう思っていました。(こんな事態に陥る以前のシーズン1のみの観劇でしたが)以前にも書きました
が、名作であるジェロームロビンンズ演出振付版から変遷して新たな、その時、現実的に響いてきたんです。舞台化するべく今のタイミングなのだと読み取れるものでした。
いくつか新しいフレーズを加えたんだ(新曲)と思いますが、シャークス団(プエルトリコ移民)たちの誇りを歌うシーンもあります。誰が悪い、ではなくどちらも頑張って生きているが《望まれて生まれたわけではないから虐待や貧困等で環境が悪い》とか、移民してきたのに《肌が黒いから差別される》等どちらも頑張っていることとは関係なく居心地が悪いんです。その上この貧困者たちが住む場所はあのリンカーンセンター建設予定地区で現在馴染みのあるメトロポリタンオペラ劇場等の完成予想図が立ち退き地域のフェンスに掲げられているんです。
設定の違いは他にもいろいろあります。
アメリカは1961年版では故郷がいいと言う仲間にアメリカの素晴らしさを歌い上げるのが印象的ですが、2021年版では出稼ぎで稼いで故郷に戻りたいベルナルドたちに対してアメリカならこんなものもあんなものもあるわと適応しているアニータたちが強調されているように感じました。
そして、衣裳が抜群に可愛いし、その時代のいいとこどりでもあります。
ヒールでダンサブルに踊る女の子たちのかっこ良さもわくわくしてしまいます。
カッコいい体育館でのダンスシーンもその迫力もきっと後から観られるビデオ配信等ではなく映画館のスクリーンで観てほしいです。ビデオだと迫力のあるダンスや華やかな場面でもこじんまりと感じてしまって、変に視点がそれてしまうような気がして。
マリアたちの職場も1961年映画版と違い、その時代に確かにありそうですし、職場をそこに移したことによりそこで歌われるアイフィールプリティも華やか。
クールも全く違う場面でトニーが主に歌います。
トゥナイトやワンハンドワンハート、マリアなどバーンスタインの有名曲満載ですが、いちばん泣きそうになったのはサムホエア
ここが1961年版や舞台とは最も違う新しい演出です。これを観に映画館にいくべきです。
😭👏👏👏
ここでリタモレノ。
実はアニータをかつて演じていたのはチタリベラだと思っていました。ずっと勘違いしてました。ブロードウェイの舞台版では間違いなくチタリベラが演じてトニー賞など受賞していたそうですが、1961年映画版アニータがリタモレノだったんです。そのリタモレノは今回製作に名を連ねています。
今回、もちろんリタモレノがアニータを演じるわけではありませんがとても重要な人物として登場します。
アリアナ・デボーズ(アニータ)
アンセル・エルゴート(トニー)
レイチェル・ゼグラー(マリア)
そして、マリアとのこのシーンのアニータの辛さも
この後のアニータに起こる悲劇も痛みがヒリヒリしてこの歌声を聴きながら、辛いです。
その場面の演出も1961年版ではジェット団の女たちはスルーしているんですが、この2021年版では声にならないダメ―っという抵抗の叫びをあげています。昔はたぶん演出も制作側も気にしていない部分なのでしょうが今スクリーンに向かって観ている私たちの感情とリンクする場面です。
エンドクレジットの楽曲も素晴らしいので(なぜかここで席を立つお客さんが居てびっくりしたんです、この素晴らしいバーンスタインメドレーを聴かないで帰るなんて)映画を見てから是非お聴きくださいませ。
マリアが最後に言う台詞は最初の映画版とも劇団四季版とも同じです。(特に浅利慶太氏も舞台版で強調した)憎しみから相手にやり返すのではないマリアの毅然とした態度こそ争いをなくしたい願いなんです。
この演出をした後に浅利先生がその直後のカーテンコールで決して(素に戻って)ニコニコ出てきちゃダメだとおっしゃっていた言葉が耳に残っています。カーテンコールまですべてこのウェストサイドストーリーという作品なんだと。ニヤニヤするような結末ではないし伝えたいことを全うするという意味だと思いますが、同じように町田樹先生のフィギュアスケートで演技していた姿勢(態度)とか、この人だから好きなんだという部分は一貫しています。
いま、
ロシアの気の狂った攻撃によって破壊されつつあるキエフ🇺🇦(ウクライナ)の状況も終わらせなければいけない。ロシアの敵国は破壊され、ロシア市民の反対の声をあげる人々は拘束され罰を受ける。
この飛び火があちこちから飛んできそうで、(あちこちにわたしたちの常識とは全く相容れない思考の核ボタンを押せる立場の人がいて)それも恐怖です。
悲しいし、苦しいし、どう声をあげたらいいのか、このまま黙って滅亡を対岸からみていていいのか、
私たちの思う平和を願うことしかありません。