
フリー~〈無料〉からお金を生みだす新戦略/クリス・アンダーソン
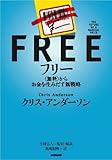
¥1,890
Amazon.co.jp
ぼくの評価







(ロングテールに匹敵するほど説得力のある完成度の高い一冊。経営層やWebの収益化に関わる人などにぜひおすすめです)
合わせてこちらもどうぞ

週刊 ダイヤモンド 2010年 3/13号 [雑誌]/著者不明

¥690
Amazon.co.jp
週刊ダイヤモンド『FREE』特集連動企画
http://diamond.jp/feature/dolweekly/10001/
無料、無償、自由、タダ、フリー。
この世界にはいわゆる無料で手に入るものが数え切れないほど存在します。
しかし、これら無料のモノやサービスは経済学の観点から考えると一概にもすべてがタダというわけではなく実際はどこかの企業や個人、政府・自治体などが補填もしくは投資という形で提供している場合が少なくなく、それらの概念が主にWebを代表とした世界で急激に台頭してきており、それら概念のメリットとデメリットを正確に理解し、投資もしくは経営などの成長戦略に取り入れられるか否かで将来の成長さえも変わってくる。
簡単に言うと、そういうことを本書では「FREE」という新概念として紹介しています。
さらにこれらのFREEには4種類の概念が存在すると本書では紹介しています。
1.直接的内部相互補助
2.三者間市場
3.フリーミアム
4.非貨幣市場
例
1.無料体験教室、無料体験版など...
2.テレビ、ラジオ、広告モデルのWebサイト、フリーペーパー(広告収入でまかなうものすべて)など...
3.有料課金で収益を上げるWebサイトなど...
4.贈与など...
クリス・アンダーソンを一躍有名にしたロングテールという概念は主にアマゾンを代表するECサイトなどを中心に語られてきましたが、本書もWebにフォーカスしている面がどちらかというと強い印象があります。
そこであえてここではWebに焦点を絞って話を展開してみたいと思います。
1.Webサイト運営の観点からFREEと向き合う
まずWebの観点から言うと、最近注目されているのは3のフリーミアムという概念だと思います。
有料のプレミアム版の利用者が無料利用者をカバーするというモデルを指すのですが、
これは一般的に5%ルールと呼ばれ、典型的なWebサイトはこの方式を採用している場合が多く5%の有料ユーザーが残り95%の無料ユーザーを支えているモデルです。
これは身近なところで挙げると、Yahoo!Japanやmixiもこの方式を採用しています。
しかし、この2つのサイトほどの規模になると大量のトラフィックがあるため、ネット広告の中でもグロス単価が高い純広の期間保証モデルが成り立ち、2と3のモデルを組み合わせた形のビジネスモデルとなっているのが現状です。
上場してからなにかと話題に上がるGREEも2と3を組み合わせたモデルですが、
この企業の場合は2より3のパーセンテージを5%よりも高め、
先駆けて有料課金モデルを成功させた事例だといえます。
今回の不景気もあり2の収益モデルの不安定さが露呈したため、どちらかというと安定的な3の比率を高めるべく収益化のシフトが起こっています。
そしてさらに、最近話題のソーシャルアプリ市場の成長も牽引して3の有料課金モデルでのWebサイト運営の舵取りが今後さらに増加していくことと思います。
アプリの黎明期においては、iモードが牽引した形で月額有料課金が主流となっていましたが、現在ではiphoneのApp Storeやソーシャルアプリなどの登場でアプリへの課金の金額が高額化しています。
以前も紹介した夏野剛さんもおっしゃっているとおり
iモード立ち上げ時の300円固定制度は相当悩んだ上での設定だった(途中から多様化)ようですが、
現在ではアプリの高機能化により一回のアプリ購入の金額も高額化してきていることでWin-Winの関係がより鮮明になってきているように感じます。
2.FREEの代表格Google。収益構造は2が97%、3が3%
通常のWebサイトが2より3からの収益化を強化している中、Googleは収益の大半が2の広告収入モデルに依存しています。
ちなみに3の3%はGoogle Appsなどに代表される法人の有料課金などです。
では、なぜGoogleは3ではなく2に依存しているのでしょうか?
Googleは2から3への収益構造転換を考えているのでしょうか?
これはぼく個人の予想ですが、
おそらくGoogleは2からの脱却は当面考えていないように思われます。
そもそもGoogleは基本的に技術で解決できないことはやりません。
人的要素が絡むサービスもしくはコンテンツはWeb2.0とロングテールの概念に従って、Google利用者にコンテンツ提供をしてもらう形をとっています。
サービスを超えたWebのインフラを提供しているのがGoogleといえます。
Web2.0のスピードで生み出されるWebの世界を制するには、すべてをテクノロジーで解決する以外方法はないという判断からきているのでしょう。
ご存知の通り、Googleが最優先しているのはユーザーであり、利用者です。
たとえ100円や1ドルでも課金をしてしまえば、ペニー・ギャップ(用語の意味は本書または週間ダイヤモンド3/13号P37参照)が生まれ、ユーザーがGoogleに抱く印象が変わってしまいます。
Googleのサービス=無料
というイメージをユーザーに植えつけることができれば、
新しいサービスをリリースしたときでも、Googleユーザーから真っ先にアクセスしてもらえるというわけです。
もし仮に、100円や1ドルでもサービスを課金制にしてしまった場合。
おそらくリリースをしても
「このサービスは有料かもしれない・・・」
と、一瞬でもユーザーに感じさせてしまうとアクセスすらしないユーザーも発生することでしょう。
あらゆる情報を無料で公開できるWebの世界でもっともアクセスを集める方法。
それは高機能かつ高性能で、情報量が多くクオリティが高いこと、そしてそれらがすべて無料で提供されていること。
これがWebの世界で高シェアを握る最強戦術だと見てまず間違いないとぼくは考えます。
その理由と裏付けはなによりGoogleがそうであり続けてきたからです。
3.FREEが注目される理由
ロングテールという概念を生み出したクリス・アンダーソン氏がなぜ今回、このFREEという題材にしたのか?
そこがぼくはとても気になりました。
彼の立場を推察するとロングテールがあまりにも有名になり、彼の功績を一つの言葉が代弁するかのように押し上げていったのだと思います。
「彼は次にどんな発言または書物を出すのだろう」
と、期待ばかりが高まり本人もヘタなことは言えない状況になっていったはずです。
しかし本を通じて世界に自分の言葉を伝えたいという思いはある。
だから今回の題材は相当悩んで悩んで振り絞った上での執筆→出版だと思ったのです。
と、彼の頭脳と勝手にシンクロするような気持ちで本書を読んでいたわけでありますが

Webを中心とした捉え方はロングテールと変わりませんが、
彼の視点のすばらしいところはWebを中心としつつもWebに限らず経済全体の変化までもを的確に捉えていて、それを一つの言葉に集約してしまうわかりやすさという点にあると思います。
つまりFREEがなぜここまで注目されているかの答えは、
「ロングテールという言葉を生み出した人が満を持して出版する第2段だから」
が正解にあたるのでは?と思っています。
まあ当然といえば当然のことですが

最後に、FREEが台頭してきた裏側にはこんなことが言えると思います。
経済がより複雑化してきたということです。
例えFREEとはいえ、それは表面上の話なので流通過程やあらゆる場面でそれを回収する必要があることは変わりません。
積極的にPRして売り出している商品も形はどうあれ、その広告費も我々消費者が負担しているという事実が存在していることを忘れてはいけないと思います。
納得して購入しているのであれば何の問題もありませんが、FREEという概念を深く理解していくと納得のいかない価格設定の商品などこの世にたくさん溢れているのです。
特に今回の不景気などで出費に敏感な人はFREEをより深く理解することで、広告費を上積みされた商品と原価と人件費のみの商品(同じクオリティと仮定する)どちらを購入した方が得か?
一目瞭然だとは思いますが

※ちょっと雑談※
そういえば前にこう語っていたのですが(本文一番下参照)→こうなるようです。
やっぱりそういう流れになりますよね

ぼくの読みは間違ってなかった

嬉シスなあ


