この小説は純粋な創作です。
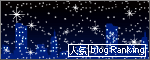
人気ブログランキング
実在の人物・団体に関係はありません。
かむどさま………。
朱唇が
己が名をかたどるのを、
神渡は食い入るように見つめた。
「鷲羽が長、
神渡殿、
ここに興津より信義の証あり!
いざ お受け取りあれ!」
たづの声は低く、
その
神渡は進み出る。
踏み行く布は
いかなる設えか僅かに沈んでは
柔らかく神渡の身を朔夜へと導く。
廊を囲む臣下らは
ひそとも声を立てぬ。
夢幻にも似た朔夜の姿が
五色の波の上に耀う。
たづが鮮やかに微笑んだ。
藍の衣ながら
艶やかな笑みに姫の顔がよみがえる。
「神渡殿、
これは我が妹でございます。
興津の兵も
興津の財も
この者に何事かあるとき、
すべてを投げ出して守らんと動きます。
一同の者 よいか」
藍の袖が翻り、
居並ぶ興津の臣下は一斉に平伏した。
「神渡殿、
この十年、
待ちわびたぞ。
貴殿を婿にお迎えする。
目出度い限りじゃ。」
朔夜ばかりを見つめている神渡の背に、
興津の長が声をかけた。
ゆったりとと神渡の前に長は進む。
「ここにおるは、
我が娘。
鷲羽に差し上げる。
鷲羽と興津の信義は
ここに守られる。
ただ我が娘の手を取られよ。」
武骨というより
十年の内にぼってりと肉厚になった手が
たづの清しき手から
朔夜の手を取り上げた。
キャッと上がりかけた悲鳴を
興津の臣下らは感心にも表情一つ変えずに
やり過ごした。
目で朔夜を抑えた神渡は、
そのままふるふると震える朔夜に歩み寄る。
つい先程までの月の化身を思わせる朔夜も愛しいが、
ただ己を頼る幼子のいとけなさは胸を締め付ける。
のべた手に
その手は与えられた。
「信義により
お預けした我が命、
確かにお返しいただいた。」
神渡の返答が響く。
朔夜の眸が潤んだ。
神渡は
その手を引いて
布の道に下ろした。
鮮やかな緋色の布に、
小さき足先が下ろされた。
そのかかとまでが透き通る白き玉を思わせる。
神渡は
渡り来た道を振り返り
ふっと笑う。
花嫁の装いの朔夜の手を引いて戻るには
些か長すぎた。
ふわりと
白き蝶の群れが舞い上がった。
幾重にも朔夜の華奢な腕に掛けられていた薄布は
神渡の狼藉に棚引く。
「神渡さま………。」
ようやく
待ち焦がれた甘い声を聞き、
神渡は微笑んだ。
「その声、
やはり そなただ。
この目で見ても信じられぬ。
朔夜、
美しい。」
「神渡殿、
強引な運び、
お許しください。」
たづの声が
重なる。
神渡の頬が引き締まる。
静かに長に向き直る姿に、
力が漲る。
「我が契るは
ただ一人と決め申した。
今我が腕にある者です。
それで構いませぬか、
興津殿。」
興津の長は
にやりと破顔した。
われながらよくぞ思い付いたと言わんばかりに鼻をうごめかす。
「それこそ興津の望み。
信義において、
今我らが姫を鷲羽に贈る。
名は〝月〟。
神渡殿、
興津はその姫と共にある。
慈しんでくだされ。」
興津の長は
大仰にその両袖を広げ
腰を深く折った。
神渡は
朔夜をそっと下ろした。
「我が月よ
そなたの親となられたお方だ。
御礼申し上げよう。」
庭に流れる一条の赤。
交わされる鮮やかな黄は光の矢。
木々の緑に地の花々は秋の盛りに咲き零れる。
天晴れ日の長と仰がれる男は、
花嫁を迎える装いに
その男振りはいや増す。
月の光が凝りて生まれたかと心騒がせる麗人は
楚々として立つ。
その腰を折って礼を返す神渡と
膝を曲げて頭を垂れる朔夜に
興津の庭は天宮の趣だ。
この地を治める男は、
その権勢を誇る設えの中で
満足げに日と月の礼を受けた。
その顔は立った。
ともあれ興津は鷲羽の盟友でなければならぬ。
たとえ
鷲羽と血で結ばれずともだ。
祭が待っている。
日と月は里に帰る。
婚儀は行われることとなった。
それを婚儀と呼ぶかはまた深水が頭を捻ればよいこと。
日と月は契りを交わす。
その披露目が行われる。
斜陽が里山を染め上げる。
華やぐ館は二人を送り出して
その片付けに入っていた。
里山の枝に黒き影が立っていた。
その足元に丸くなる小さな影は子どもだろうか。
〝行くかい?〟
〝行くさ〟
岩戸の民を滑る老人の
労るような優しい声に
押し被せる速さでタケルが応じる。
老人は
もう声を発することはしなかった。
優しい影が猛々しい影にちょこんと寄り添う。
日は落ちた。
いつしか影は消えていた。
画像はお借りしました。
ありがとうございます。
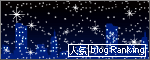
人気ブログランキング

