この小説は純粋な創作です。
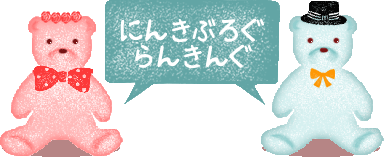
人気ブログランキング
実在の人物・団体に関係はありません。
伊東は、
後部座席に海斗と瑞月を乗せ
ホテルへと向かっていた。
水澤に高遠、
そして渡邉は、
西原と共に再びトラックの荷台だ。
トラックは託児所から移動式司令室となっている。
作田と政五郎は
何だかんだと理由を付けて
秦と女をホテルに送っていった。
病院に連れ込みたかったが、
女が固辞したのだ。
ホテルで合流できるだろう。
大した混み具合だな……。
GW後半初日、
昼時を迎えようという今、
前を行くナンバープレートは関東圏のそれが
犇めいている。
この三日間、
自ら美しい景観と史跡で知られると共に
東北観光の拠点となる交通の要衝でもあるこの街には、
誰と特定できず
跡を辿りにくい人間たちが
刻々と流れ込んでくる。
伊東は
西原を思った。
入り口は無数だが
ゴールは一つ
瑞月さんだ
惑わされるなよ
鷲羽海斗、
日を戴く長が
戦いに臨む。
気恥ずかしくさえなる
この状況が真実かどうかなど、
また
この戦いが世の様々に関わるか否かなど
伊東にはどうでもよいことだ。
受けて立つ。
それだけだ。
鷲羽は鷲羽らしく生きる。
それだけだ。
「海斗がね、
呼んだんだよ。
ぼく、
海斗が見えた。
光っててね、
ぼく……繋がってた。
ああ繋がってるって感じた。」
後部座席から
瑞月の声が聞こえる。
……瑞月さん
だから
私は信じている
欲情は
結晶して透き通り
天上へと光の軌跡が繋がる
瑞月は
特別だ。
それは
どうしようもないまでに
真実だ。
他の誰に
営みを
このように語れるだろう。
愛されること
愛することが
こんなにも清らかなものとなる。
すべては瑞月から発する光に裏付けられて
現実主義者に降ってくる。
聖なる天使を
神のお告げで守ってる
もとい
月の巫を
勾玉のお告げにより
守っている
西原は、
高遠らが視たという闇の時間を
共有できたろうか。
傀儡の流入、
その小賢しい襲撃、
今までも繰り返されてきた小競り合いの指揮は
西原が取るのだ。
ふと、
その指揮官たる西原が羨ましくなる。
負の感情は闇につけこまれる元だ。
振り払うことが肝心だが、
なかなか消えていかない。
伊東は
運転席に一人
思い悩む。
戦いは既にあったという。
それが
伊東には重くのしかかる。
対峙するのは鷲羽海斗ただ一人。
選ぶのは瑞月。
結果、
秦は形を喪って宙宇をさ迷っているという。
巫の魂を支えるのだと自らを励ましても
無力感は残る。
西原に指揮権を譲った今、
自分は何をしたらよいのか。
いや
できることがあるのか。
水澤と渡邉は
勾玉の結ぶ過去の記憶をもっている。
それだけで鍵足り得る。
作田は視るのだ。
政五郎は支えるのだ。
自分は
何を
どうしたらよいのか。
見えぬ自分が
警護以外を知らぬ自分が
こうして付き添っていることの虚しさを
伊東は噛み締めていた。
「伊東、
すまなかった。」
突然
鷲羽海斗が話しかけてきた。
後部座席は
仕切りの向こうだ。
開かれたままの回線は声だけを繋いでいる。
「はっ
とんでもありません。
力不足で
御心配をおかけしました。」
伊東は、
明瞭な声で
返した。
「伊東、
俺を信じてくれるか。
いや
信じてほしい。」
鷲羽海斗の声は続く。
その声は
伊東に向かいながら
どこか独り言のようにも聞こえた。
信じてほしい
と
願っている。
願う自分を確かめているように
語尾は僅かに下がる。
伊東は
ハッとした。
そして、
しっかりとハンドルを握り直した。
「もちろんです。
信じています。
今までもこれからも
信じています。」
伊東は思い出していた。
作田に感じた共感を。
「何が起きるか
俺にも分からない。
そこで
俺が何を選ぶかも
今は分からない。
選んだことさえ
気づかぬかもしれない。
……そのとき、
また心配をかける。」
言葉を選んでいる。
瑞月がいるからだ。
伊東は
問い返すことはしなかった。
〝海斗!〟
の
一瞬のことだ。
そう感じた。
そして、
それはどうでもいいとも思った。
「信じています。
作田さんと同じです。
鷲羽海斗という方に
私は出会いました。
そして、
信じると決めました。
もう十二年にもなるのですね。
総帥はいつも信じるに足る方でした。」
鷲羽海斗が佐賀海斗の頃から
その指揮のもと
伊東は戦ってきた。
その不器用を案じながら
その決断に切り開かれるものに驚きながら
その傷心に何もできぬ自分を責めながら
ただ付いてきたのだ。
「ありがとう」
その声は
低く
噛み締めるようにゆっくりと返された。
車は
もう駅へと通ずる大通りにあった。
伊東は、
目の前にある次のステージに向けて動き出す自分を感じていた。
思い悩む必要はない。
自分にできることを組み立てる。
投げ掛けられたこと、
直面することに、
自分が思うままに動けばいい。
自分は自分を知る人の下で戦っている。
その持ち場はその人が定めた。
迷うことはないのだ。
伊東は
静かに午後のタイム・スケジュールを反芻した。
車は静かに
ホテル駐車場に滑り込む。
イメージ画はwithニャンコさんに
描いていただきました。
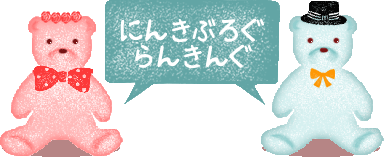
人気ブログランキング
