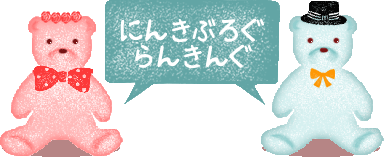この小説は純粋な創作です。
実在の人物・団体に関係はありません。
コン!
と
小気味良く槌が振り下ろされる。
壁には
ペルシャ渡来のタペストリー、
小卓には
中国渡来の蝋燭立て。
今日は
東洋の小品ばかりとあって
小卓を囲む二十人ほどの客は
東洋の情趣に購買意欲を掻き立てられているらしい。
空いた卓が
まだあるとはね
これは
外れだったかな
と
デリクは苦笑いしながら
ちゃちな偽物の蝋燭立てに灯る灯を眺めた。
給仕に回る老練なウェイター、
小さな夕食会でも催されているかの風情は、
それ自体がエキゾチックで
悪くはない。
このいかがわしさは
癖になる
ちら
と
目をやると
今落札されたのは
小さな浮世絵のようだ。
落札された品は
スタスタと運び出され、
次の品は
中央のテーブルに置かれる。
「皆様、
次は、
根付でございます。
螺鈿の細工が美しゅうございますよ。
本日は螺鈿細工に
良いものが集まりました。
螺鈿細工を集めておられたお方様の縁の品が
出品されております。」
微かな囁きが
そこかしこで交わされる。
そして、
指先が僅かに上げられ
ハンカチが小さく揺れる。
まるで言葉を無くしたような不思議な市が立つ。
何度見ても
どこかいかがわしい。
いつしか
そのいかがわしい市にも
馴染みとなり、
品の由緒やら値打ちやらを語ることを趣味の生業とし、
ここにいる。
さして来たかった訳ではないが
結婚話を携え
使命感に燃えて現れた叔母たちを撃退するのには
何か理由が必要だった。
小文を書くのは趣味で
その収入も趣味に浪費する。
骨董の目利きなど
仕事とするつもりもないが、
デリクの見立ては正確で
いつしか
引く手あまたの素人鑑定人となっていた。
だからこそ、
その小文は売れる。
皮肉なものだ。
あ…………。
黒い漆塗りの地に
螺鈿細工の花の紋様が美しい。
日本の女の髪を彩る櫛が
登場した。
江戸だ……。
いい仕事をしてる。
螺鈿細工もさることながら
漆の見事さには
唸るものがあった。
〝20ポンド!〟
デリクは
右手を上げ
静かに頷いた。
拍手は
微妙にばらけた。
高額に過ぎる……。
そういうことだろう。
だが、
価値はその細工にある。
値を付けることで
正当な評価を定着させることができる。
そう考えてもいた。
這う這うの体で逃げ出したアパートに戻り、
今度は夜会の支度だ。
ぶらぶら生きているようで、
人生は忙しい。
叔母たちの襲来を防ぐには
それなりに努力する姿勢を見せねばならない。
正装に身を包み
髪を撫で付け
ハンカチをポケットに差し込み
鏡を見る。
時計の針は
6時を回ったばかりだ。
間に合う。
そう思ってようやく落ち着いた。
値打ちがある。
やややけくそ気味で飛び込んだオークションだったが、
落札した櫛への評価は正直な気持ちだった。
すまなかった
許してくれたまえ
共に購入した袱紗に包み
懐に持ち帰った櫛を
スーツの内ポケットから取り出す。
生真面目に
袱紗を目の前に捧げ
心で詫びを言う。
耳学問だが、
日本では
すべてのものに魂が宿ると
聞いていた。
特に
身の回りの品、
身に付ける物たちは、
その持ち主の思いをもちやすい。
とてもロマンチックに感じた。
以来、
こうして時折思い出すのだ。
この場合は、
櫛にも
その作り手にも
この粗略な扱いを申し訳なく思っていた。
そっと袱紗を開くと、
部屋の灯りに
櫛は輝いた。
美しいな……。
ため息が出る。
櫛は髪に差すものだ。
浮世絵の女たちは黒髪を結い上げている。
その結い上げた髪の根に
こうした櫛がアクセントとなっていた。
手の中にある櫛が
行灯から広がるぼんやりとした光の中で
そっと抜き取られる様が
思い浮かぶ。
それは
ひどく艶かしいものに思えた。
ウィルが来るな……。
今日の夜会に駆り出された年若い友人が
思い浮かんだ。
大叔母の
いやグロリアの孫にあたる。
大叔母の館にあった骨董品の情報は
彼がくれたものだ。
散ってしまうには惜しい。
そう感じる心が好もしかった。
まだソバカスが残る彼も駆り出されるとは
気の毒だった。
見せてやりたいな
ふと思い付き、
デリクは
袱紗を
ふたたび懐に入れた。
もう出なければならない時刻だった。
画像はお借りしました。