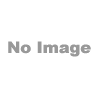今日は、「仙台のお土産」について、私の思い出話をしてみたい。
最近、踊り子さんに「今日のおやつ」と称して、毎日、日替わりの仙台の銘菓を渡すようにしている。踊り子さんは、今日はどんなお菓子かなと楽しみにしてくれる。「あっ、これ美味しいのよね」とか「昨日のお菓子はすごく美味しかったわよ」とか感激してくれる。
喜んでくれるその顔を見ながら、ある日、ふと亡くなった私のおばあちゃんのことを思い出した。
おばあちゃんが亡くなり、もうかれこれ30年近く経った。
私とおばあちゃんは血のつながりはない。正式に書けば養祖母という関係になる。
おばあちゃんの若かりし頃のことは私にはよく分からない。秋田の田舎で貧乏だったために、四人妹弟の長女であったおばあちゃんが若いときに北海道の函館に奉公に行かせられた。昔は美人だったようだ。私の母親から後々聞いた話では、身売りで女郎をやっていたようだ。だから子供の出来ない身体になったとのこと。
その函館で富山から流れてきていた養祖父と出会い、二人は所帯をもち、養祖母の故郷である秋田に戻って小さな店を始めた。酒、たばこ、塩を含む日用品店で、商売は順調だった。ここが私の実家、だから私の姓のルーツを辿ると養祖父の出身である富山ということになる。
子供のいない養祖父母は、お向かいの家から次男坊を養子に迎え、隣の村から嫁をもらう。それが私の両親である。
私が生まれたとき、我が家として初孫であったため、養祖父母はそれはそれは喜び可愛がった。私は完全なおじいちゃん、おばあちゃんっ子。私は二人の背におぶられて大きくなっていった。夜はずっと二人と寝ていたので、不思議と両親と一緒の布団に寝た記憶がない。私の両親は養祖父母に気をつかい、私と弟を養祖父母に預けざるをえなかったようだ。私と弟が家族円満の核となっていたのだろう。
おばあちゃんは、70歳頃から目を患いだした。白内障、緑内障とかと言っていた。働き者だったおばあちゃんは、目が悪くなってからは次第に外に出かけられなくなる。高齢になってからの目の病だから、無理もない。かすかに見える視力で、ぼんやりと池の中の鯉を眺める日々が多くなっていった。テレビも最初のうちはかすかに見えていたようだった。
おばあちゃんが目を患い出したのは私の小学校高学年の頃。私は中学、高校と成績は常にトップだった。自宅での勉強は中学・高校を通じてずっと朝型。早朝3時から4時頃に、いつもおばあちゃんに起こしてもらっていた。おばあちゃんは私の目覚まし時計。おばあちゃんは成績のいい私が自慢だったし、自分に残された唯一の仕事が私を毎朝起こすこと。「もう四時だけど、起きなくていいの」「お勉強、頑張ってね」、あのときのおばあちゃんの声が今でも耳に残っている。高校後半の頃には、おばあちゃんは80歳を越え、もう殆ど視力をなくしていた。でも、私の目覚ましだけは最後まで続けてくれた。お陰で私は志望校にストレートで合格。おばあちゃんが私の合格を喜んでくれたのは言うまでもない。
私が大学に入り、仙台に下宿を始めてから、おばあちゃんは呆けが始まり、完全に昼夜逆転の生活になったようだ。私は丁度そんなおばあちゃんの状態をほとんど知らないで済んだ。ずいぶん大変だったと母から聞かされた。
たまに私が仙台から帰省すると、おばあちゃんは本当に喜んでくれた。私は仙台で買ってきたお土産を開き、全盲のおばあちゃんの口に運ぶ。
「おばあちゃん、これね、日本一おいしいお菓子だよ」
甘いもの好きなおばあちゃんは、いつも「おいしい、おいしい」と言って、泣きながら食べてくれた。私が仙台に帰った後もずっと「しょっこ(私のこと)の買ってきてくれたお菓子は本当に日本一おいしい」と家族や近所の人に話していたようだ。いま思えば、一番のおばあちゃん孝行だった。
私が家を離れて1年2ヵ月後のゴールデン・ウィークに、おばあちゃんは亡くなった。死に目には会えなかった。長い間、目の見えなくなったおばあちゃんを看病していたおじいちゃんも、まさにおばあちゃんの後を追うように、その一年後に亡くなった。養祖父母はとても素敵な夫婦だったと今更ながら思う。
私は、仙台のお菓子は本当に日本一おいしいと自慢できる。しかも、たくさんの味がある。踊り子さんが喜んでくれる顔を思い浮かべながら、「今日のおやつ」を選ぶのがいまの私の楽しみになっている。
平成20年10月 仙台ロックにて