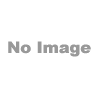今日は「おもてなしの心」という話をしてみます。えっ、そんなこと「思って無し」(親父ギャグ)なんて言わないで聞いてくださいな。
高校生の娘が茶道クラブに入っているというので、ちゃんとした茶道具でお茶を点ててもらった。茶を点てる娘のひとつひとつの仕草に感心しつつ、妻と一緒に厳かにお茶を味わう。
いいものだ。すごく心が洗われた気がした。
興味をもったので、茶の湯をインターネットで検索してみた。千利休の考え方にすごく共鳴するものがあったので後ほど少し紹介したいと思うが、なによりも茶道がストリップに通じることに驚いた。
今回は茶道の基本理念である「おもてなしの心」について考えてみます。
表千家のホームページには「もてなしの心」について次のように記載されてありました。
『茶の湯は、おいしいお茶を主が客にもてなし、客は感謝してこのお茶をいただき、主と客の間に心のかよいを深めていく道といえます。おいしいお茶とは、味覚にとどまらず、道具組の趣向、季節や歳時との呼応、主のふるまいの美しさや語りの奥ゆかしさ、客同士の心遣いといった、一座を成り立たせるまたとない一時がもたらす味といえましょう。』
主という字を踊り子という言葉に置き換えると、ストリップが本来求めるものにそのまま通じると思いませんか。ストリップというのは本来「ストリップ道」なのかも。まあそこまで深く考えなくても、茶道が女の子のたしなみを学ばせるものとして普及しているのなら、その心は踊り子さんにも通じますよね。
この文書をもとに読み換えると、「ストリップというのは、ステージを通して、踊り子と客がともに楽しみ、心を通い合わせること」に大きな意義があるように思えます。素晴らしいステージというのは、単に踊り子さんのヌードだけに限らず、舞台、照明、音響、衣装などの趣向を凝らし、構成に季節感や流行をうまく織り込むことも大切です。また何よりも踊り子さんの内面からにじみ出る品格、美しさ、奥ゆかしさみたいなものがステージを大きく左右するとまで言えそうです。
また、私は以前からストリップの楽しみのひとつは踊り子さんと仲良くなることと言っていますが、「主客が心を通い合わせる」というのはまさにそのことだと思います。少なくとも私のような常連は、単にヌードを見に来ているわけではありません。踊り子さんの中には、裸も見せてあげた、いいステージもしてあげた、だからそれで十分満足でしょう、という態度を感じる方もいますが、そこには「おもてなしの心」が欠けています。劇場に足を運んでもらうためには「おもてなしの心」で客に接する心がけが絶対不可欠です。
踊り子さんだけでなく、お客の方にも「おもてなしの心」が大切だなと思います。
リボンさんが踊り子さんに対する基本姿勢はこの「おもてなしの心」であるべきです。せっかくステージに上がっていただいたわけですから、気持ちよく踊ってほしいと願う思いやりです。
私のホーム・グランドの仙台ロックでは、数人の常連が毎回コスプレをやります。それもかなり凝っています。そのため、踊り子さんが大喜びしてくれます。彼らもそれを励みに、最近ますますコスプレに磨きがかかっている感じです。
私としても、大好きな踊り子さんがせっかく仙台に来ていただいたからにはホストのつもりで接しています。仕事・出張のないときには毎日顔を出していますが、まず通うことが一番。次に一生懸命に応援して場を盛り上げること。客の少ない仙台ロックでは私の存在は小さくないと自覚してます。だから踊り子さんには「十人分の応援をするからね」と言ってます。たとえば私の手拍子は変わっているとよく言われますが、実はそれなりに進化しています。気持ち的にはタンバリンとリボンを手拍子でやっているつもりです。お手紙を毎回渡すのもまったりした仙台ロックで退屈させないというおもてなしのひとつです。また最近は仙台名物ポラを踊り子さんと一緒に考えて楽しんでいます。仙台に来た縁ですから、ひとつでも仙台名物を知ってもらえればと思っています。
‘相手を喜ばせ、それを見て自分も喜ぶ’・・そんな関係が最高だと思います。
私は踊り子さんに花や物を贈ったりはしませんが、「おもてなしの心」という精一杯の気持ちを贈りたいと常々考えています。
平成19年 仙台ロックにて
【付録1】利休七則
「利休七則」とは茶の湯を学ぶ者の基本となる心得。自然体のままで季節感を大切にし、「もてなし」と「しつらえ」を基本とする。
● 茶は服のよきように点て
「服」とは、飲むことを意味する。「服のよきよう」とは、飲んだ人にとって「丁度良い加減」ということで、つまり、自分の点て易いように点てることを戒めている。お茶は心を込めて美味しく点てる。舌の先で美味しいと感じるだけでなく、一生懸命に点てたお茶を客がその気持ちも味わっていただくという、主と客との心の一体感を意味する。
● 炭は湯の沸くように置き
湯が良く沸くように火をおこすために上手に炭をつぐ。形式だけで炭をついでも火はつかないので、本質をよく見極めることが大切ということ。
● 花は野の花のように生け
花は自然に生けよということであるが、自然そのままに再現するのではなく、一輪の花に、野に咲く花の美しさと自然から与えられたいのちの尊さを盛りこもうとすること。
● 冬は暖かに夏は涼しく
季節感を大切にするということ。茶道では、たとえば夏の涼しさを表現するために「打ち水」をしたり、冷たいお菓子を出すなど、「茶室」「露地」「道具の取り合わせ」に季節を表現し、自然の中に自分を溶け込ませるような工夫をする。
● 刻限は早めに
時間厳守を説いているのではなく、心にゆとりを持つ、ということ。「ゆとり」とは時間を尊重すること。自分の気持ちに余裕ができるだけでなく、相手の時間を大切にすることに繋がる。
● 降らずとも雨の用意を
どんなときにも落ち着いて行動できる心の準備と実際の用意をいつもすることが茶道をする人の心がけであるということ。適切に場に応じられる自由で素直な心を持つことが大切である。
● 相客に心せよ
「相客」とは、一緒に客になった人たちのこと。正客も末客も、お互いに尊重し合い、楽しいひとときを過ごすようにせよ、ということ。
【付録2】利休百歌
「こころざし深き人にはいくたびも あわれみ深く奥ぞ教ふる」
「その道に入らんと思ふ心こそ 我身ながらの師匠なりけれ」