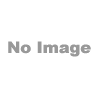今回は、ロックの踊り子・徳永しおりさんについて、H30年4月中の大阪東洋ショー公演模様を、新作「In the dark」と演目「静-2018-」を題材に語ります。
H30年4月中の大阪東洋ショー劇場に顔を出す。
今週の香盤は次の通り。①松本なな(東洋)、②青山ゆい(東洋)、③中条彩乃(ロック)、④あすかみみ(ロック)、⑤徳永しおり(ロック) 〔敬称略〕。
今週は、1,3回目に演目「静-2018-」、2,4回目に新作「In the dark」。三日目から出している新作「In the dark」は東洋限定のようだ。もうすぐ5月頭に2周年を迎えるところ、その前に東洋限定で新作を披露してくれるなんて、東洋常連として嬉しい事この上ない。
この新作は、東洋の舞台にある簾状の垂れ幕を利用したシルエット演出がポイントになっている。たしかに、これは他の劇場には常備されていない。
さっそく、新作「In the dark」の内容を紹介しよう。
最初に、洋楽に合わせて、しおりさんが簾の内側でポーズを切る。照明がうまく工夫され、簾に映るシルエットが美しい。しおりさんのスタイルが抜群にいいため、ポージングされたシルエットがかっこいいのだ。
一旦ここで暗転。二曲目は女性ボーカルの洋楽でノリノリになる。
しおりさんが簾から現れる。黒いブラに黒いズボン。赤いブレザーぽい上着を羽織り、かっこいい出で立ち。また、髪が印象的。背中まで流れる長くてストレートな黒髪に白や金の毛が混じっている。三つ編みまで混じっているぞ。ウイッグだろう。
三曲目は男性ボーカルの邦楽に変わり、衣装を黒いドレスに変える。
椅子を花道に持ってきて演ずる。
四曲目が男性ボーカルの洋楽ハードロック。ここからベッドショーへ。
近くで拝見するも、アクセサリーは特にない。手足に銀のマニキュア。
立上りは、女性ボーカルの洋楽で締める。
殆ど洋楽で固めて、かっこよく決めている。
なんというか、ロックの看板娘である徳永しおりが、まさにロックのホワイトスワンが果敢にブラックスワンを演じている印象を受けた。悪役や汚れ役を演じてこその真の表現者。また一歩成長した徳永しおりを観た気分になる。
もうひとつの演目「静-2018-」は、いつもの徳永しおりというか、まさしくロックの王道を演ずる。
斬新な着物のドレス姿で、盆の上からスタート。上半身は長い振袖が付いた着物状で帯を締める。下半身は、裾広がりのドレス状で銀のきらきらしたハイヒールを履く。全身が白の中に銀が散りばめられた模様。頭にも白の中に銀が入る髪飾りをして、長い髪を後ろにひとつ結びして背中まで垂らす。真珠のイヤリングが輝く。マニキュアも銀という徹底ぶり。まさしく白銀の王女といった様相。その中で、赤い口紅が妖しく浮かび上がる。
金のコンパクトを手に持って、音楽に合わせ舞い踊る。
一曲目は、竹内まりやの懐かしい曲「元気を出して」。(この曲は竹内まりやが作詞・作曲して薬師丸ひろ子が歌った。1984年2月14日にリリース。)
二曲目は、男性ボーカルの洋楽で、ノリノリ。
一旦、暗転。
三曲目が、氷室京介の渋い曲「魂を抱いてくれ」になる。
白い衣装の上に青いガウンを羽織って登場。両手首が白い縄で縛られている。拘束されている身か。
そのまま、裸足でベッドショーへ。
立上り曲は、池田綾子の曲「空の欠片」。じわっとくる歌詞とメロディ。
♪この道を進んだなら いつかまた君に 逢えるだろう
遠く続いていく時の中で 今日を懐かしむ きっとこの場所で
この曲もこの歌手も初めて知った。嬉しくなる。
「空の欠片」は、2007/08/29リリース。NHK教育アニメ『電脳コイル』のオープニング曲「プリズム」、エンディング曲「空の欠片」、さらにイメージ・ソング「旅人」を収録した池田綾子のシングルに収録。
池田 綾子(いけだ あやこ、1978年6月1日 - 現在39歳)は、日本の女性歌手、シンガーソングライター。埼玉県立越ヶ谷高等学校、武蔵野音楽大学声楽科卒。血液型はB型。2002 年2月21日シングル「ヤサシイウタ」でデビュー。 日本語の「韻」を大切にした歌詞と旋律、クラシックの発声を基調とした独自の歌声を持つシンガーソングライター。心の音を紡ぐような音楽世界と、透き通る声の音色は、 ジャンルを超えて数々のコラボレーションを生み続けている。今までに数多くのTV、CM、 映画などの主題歌や、出会いの中でアーティストへの楽曲提供も行っている。
「静-2018-」は、しっとりしたステキな作品である。
静という名前から、歴史上の「静御前」を彷彿させられた。私の大好きな歴史秘話である。源義経の妾であるがゆえ、兄頼朝により捕えられた。最期は義経の後を追う旅の途中で非恋の死を遂げる。そんな彼女の心境を想って「空の欠片」を聴くと涙が出てくる。義経への愛を貫き通した静御前の生き様は多くの人に感動を与える。
平成30年4月 大阪東洋ショーにて
【お願い】
ライブシアター栗橋をご存知ですか?
栗橋は静御前ゆかりの地。旧村名が静村で、秋には静御前祭りが催される。インターネットで知り、すぐに駅前の「静女の墳」に行った。小さな祠(ほこら)。「静桜の里くりはし」とある如く、桜が有名。今度はその時期に来たい。
静御前は義経の後を追って京から平泉に向かう途中、ここ栗橋で病に倒れ悲恋の死を遂げたと言われる。他にもまだ静御前の墓とされる所がいくつかあるようで、今となってはどれが正しいかは確かめようがない。
狭い祠の中に佇むと、はるか彼方の昔に想いを寄せられる。
是非、しおりさんもライブシアター栗橋に出演し、この演目「静-2018-」を演じてほしい。それが静御前の供養になる。そのときには私も必ず観劇に伺います。
【参考】賤の小田巻(しづのおだまき)
「しづやしづ しづのおだまき 繰り返し 昔を今に なすよしもかな」
初めて読む人には何を言っているのか分からないと思うが、これからの話を読むと、この和歌に感動すると思う。
平安時代末期の話。
ある年に、百日も日照りが続き、心配した後鳥羽上皇は100人の僧に読経させるも効験がなかったので、100人の容顔美麗な白拍子を集めて雨乞いの舞をさせた。しかし、だれが舞っても一向に雨が降らない。最後に、当時15歳の静が舞い始めると雨が三日三晩降り続き洪水になるほどだった。大変感心した院が静に「日本一」の院宣を与えた。
ちょうどその「雨乞いの神事」に、兄・頼朝の代官として入京していた義経も見物しており、二人は初めて出会う。義経は静を見初め、召して妾とする。
その後、義経は兄の鎌倉殿(頼朝)の怒りに触れて暗殺者を送り込まれる。院や都の権力者は手の平を返すように冷たくあしらう。義経はついに都にいれなくなる。
義経が都落ちした時、静も一緒についていく。その時、静のお腹には義経の子を身籠っていた。
吉野の山中を身重の体で彷徨い続けて、最後には義経と生き別れになる。静は見つかり山僧に捕えられ、京の北条時政に引き渡される。
さて、ここから「賤の小田巻」の本題に入る。
静は1186年3月に、母の磯禅師(いそのぜんじ)とともに、鎌倉に呼ばれる。表向きは「鎌倉殿(頼朝)の妻、政子が日本一の静の舞を見てみたい」というものだが、その魂胆は、①.血眼になって探している義経捜査のため、②.静の腹の中にいる義経の子供を殺すため。
初めて、静が頼朝と対面したとき、その場で頼朝は「今ここで静の腹を裂いて、赤子を取り出し、目の前で殺してしまえ!」と叫んだそうです。さすがにそれはあまりにも残酷と、その場を仲介した者があり、「今ここで」というのは無理があるという事になるが、のちに出産した時に女子なら助けるが男子であれば即殺すという事に決めた。(結局、静の子は男の子で、生まれると同時に川に投げ込まれる。)
ちなみに、頼朝は若い頃、まだ流人として伊豆にいた時に、一つの恋をして子供が生まれた。ところが世は平家の全盛時代。流罪人頼朝の子は可哀そうに皆で寄ってたかって川に投げ込まれてしまう。しかも頼朝の目の前で。頼朝の異常症はこの時に決定的になったのではないかと推測される。話を戻す。
名目の静の舞は、鶴岡八幡宮で奉納舞することに決まる。八幡宮は源氏の氏神。当然、静は鎌倉万歳を祈る舞をしなければならない。
1186年4月8日当日、今、世を騒がせている義経の愛人が鎌倉万歳を祈って舞うということで、鶴岡八幡宮は異常な盛り上がりをみせた。鎌倉中の人々が集まってくる。高座には頼朝・政子夫婦が並んで座る。そして舞い始める。
「吉野山 峰の白雪 踏み分けて 入りにし人の 跡ぞ恋しき」
これは、まさに義経を想う恋の歌。
この時、頼朝の顔色がサッと変わる。鎌倉万歳どころか、吉野で別れた義経が恋しい・・という歌ですから。続けて、冒頭の歌が登場する。
「しづやしづ しづのおだまき 繰り返し 昔を今に なすよしもかな」
「おだまき」は小田巻と書いて、昔の糸を操る道具。真ん中が空洞になっていて、糸を巻きつけて使う。くるくる回るので、この「おだまき」は「繰り返し」という言葉の枕詞にもなっている。
「しづの・・・」というのは「賤(シズ)」という布の事。これは身分の低い人が着た衣服の布でした。そこで静は、この「しづの・・・」という言葉に自分の名前「静」をかけました。
白拍子として蔑まれたから鎌倉まで呼びつけられた私だけれども義経を想う心に嘘偽りはありません。「静よ、なぁ、静」と繰り返し私の名を呼んだあの人が輝かしかった頃に、今一度戻りたいものだ、という意味。「昔を今に なすよしもかな」は、どうか昔を今にする方法はないものでしょうか、と言っている。
ちなみに、この歌には本来オリジナルの歌があった。
「いにしえの しずのおだまき 繰り返し 昔を今に なすよしもかな」(伊勢物語)
男が昔付き合っていた女の人に、この歌を捧げて「もう一度昔みたいに会いたいなぁ」と言ったけど、女の人は何の返事もしてくれなかった・・・という意。この歌をパロデイにして想いのたけを読み歌っている。
静に頼朝公が期待していた関東の繁栄を寿ぐ祝儀舞に反して、義経との別れの曲を舞った。当然、頼朝は怒ります。普段冷静な頼朝が、この時ばかりは傍目にも分かるくらいに顔色を変えて怒ったそうです。その頼朝を諌めたのが妻の政子でした。「夫を慕う本心を形にして幽玄である(女の気持ちというのはそういうものです)」と言ったといわれる。(出典「吾妻鏡」は政子が編纂させたもので、当然政子をよく見せる話が多い。)
白拍子を呼びつけて晒し者にしようという企ては見事失敗に終わりました。恥をかいたのは人間性の貧しさを衆人の前でさらし、あげくの果てに妻の一言で尻尾を巻いてしまった頼朝の方でした。
この切羽詰まった状態の中で、静が見せた毅然とした態度は多くの人々に感動をもたらし、この場で謳い上げた義経への愛はそれを受け止めた政子と共に美談として後世に語り継がれていくのでした。
その後、7月29日、静は男の子を産んだ。頼朝の家臣が赤子を受け取ろうとするが、静は泣き叫んで離れなかった。母の磯禅師が赤子を取り上げて家臣に渡し、赤子は由比の浜に沈められた。9月16日、静と磯禅師は京に帰された。憐れんだ政子と大姫が多くの重宝を持たせたという。その後の消息は不明。