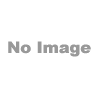ストリップ童話『ちんぽ三兄弟』
□第62章 顔なし妖怪の巻
~JUNさん(西川口所属)と山口桃華さん(TS所属)に捧げる~
ちんぽ三兄弟が、顔の話をしていた。
きっかけはJUNさん(西川口所属)のステージ、まさしく演目「顔」であった。
「あの最初の曲(CIVILIANの『顔』)の歌詞にひきつけられたなあ~。人間のもつ顔のコンプレックスにもろに触れていたもんな~」
「オレも自分の顔が嫌いだから、ツーショット・ポラは絶対に撮らない!」
「でも、ストリップのポラ撮影ではツーショット・ポラを撮りたがる人は多いよね。恰好つけてポーズをとる人が多い。こういう人は自分の顔が好きなナルシストなんだな。」
「そういえば、この演目では、最初に能面を付けていたのもインパクトあったよな!」
よく「能面のような表情」というと無表情な顔の例えに使われるが、果たして実際の能舞台では、動かないはずの能面が表情を変化させる。
「小面(こおもて)」と 呼ばれる少女の能面で見てみる。下に傾けると、物思いにふける寂しげな表情になる。逆にすると、喜びの表情が浮かび上がる。正反対の感情を、角度の違いで表すことができる。このように、ひとつの能面で無限の表情を味うことができる。
「顔といえば、山口桃華さん(TS所属)の演目『変面』も印象的だったよな。一瞬で顔を変える技は凄かったなー!!」
これは中国雑技団のパフォーマンスにあり、一瞬で顔が変わる変面(へんめん)という中国四川省の伝統芸能である。役者が手を顔に手を当てた途端に装着している仮面を瞬時に喜怒哀楽を表現しているそれぞれの仮面に変化させる。門外不出の秘儀とされ、一子相伝のみ伝承を許された技法である。700年近い歴史を持つ技術である。
「ふつうに考えたら、喜怒哀楽は別々の表情だから、中国方式にいくつもの仮面を用意するのが当たり前だよな。日本の能楽も600年もの長い歴史を持っているわけだが、ひとつの仮面で喜怒哀楽を表そうとする発想は面白いというか凄いことだよな。
日本の能楽のルーツは、奈良時代に中国から伝わった『散楽(さんがく)』と呼ばれる芸能にあると言われるが、同じ中国発でも時を経ると、このあたりにお国柄の違いが出ているよな。ちなみに散楽は、平安時代に入ると、『猿楽(さるがく)』と名前を変え、各地に広がってゆく。天下泰平、五穀豊穣を祈る祭りの中で、『神』に扮して踊る仮面が能面の始まりとされる。そして、室町時代になって世阿弥という天才によって、大衆の娯楽だった猿楽を、芸術性の高い能へと発展させたわけだ。」
「というか、そもそも人間というのは顔ひとつで喜怒哀楽の感情を表現する。他の動物ではここまで繊細には表現できないもの。まさしく‘人間は顔の動物だ’と言えそうだよね。」
ここで、物知りのおじいさんが口を挟んでくる。
「顔にはその人の育ちや性格などが出てくる。よく‘男の顔は履歴書だ’と言われる。逆に‘女は顔だ’なんて酷いことを言う輩もいるわけだが、…要はいかに顔が重要かを物語っている。
昔は、顔を見るだけで、こいつはヤクザだ!チンピラだ!というのが分かった。どうしても育ちなどが顔に出てくるんだな。だから悪いことをする奴は顔で判別できたんだ。ところが、最近の犯罪者の顔をTV報道などで見ると、ふつうの顔をした奴がこんな酷い犯罪をするのか!?と思えることが多くなった。世も末だ!」
ちんぽ三兄弟の顔の話が、いつもの癖で妖怪談になっていく。
「JUNさんの演目『顔』は、最初は女の能面だったが、最後には鬼の面になっていたなー。オレはその点がすごく気にかかったよ。」
「顔なし妖怪の代表は‘のっぺらぼう’だ!」
辞書(『ウィキペディア(Wikipedia)』)を見ると、こう記載してある。・・・
のっぺらぼう(野箆坊)は、顔に目・鼻・口の無い日本の妖怪。また、転じて凹凸が(ほとんど)ない平らな状態を形容する言葉。
外見は人に近いが、その顔には目・鼻・口がないという日本の妖怪である。古くから落語や講談などの怪談や妖怪絵巻に登場してきた比較的有名な妖怪であり、小泉八雲の『怪談』の「貉(ムジナ、MUJINA)」に登場する妖怪としても知られる。また、しばしば本所七不思議の一つ『置行堀』と組み合わされ、魚を置いて逃げた後にのっぺらぼうと出くわすという展開がある。妖怪としての害は人を驚かすことだけで、それ以上の危害を与えるような話は稀だが、話の筋立てとして「再度の怪」がよく用いられる。
八雲の「狢」が表題からしてそうであるように、タヌキやキツネ、ムジナといった人を化かすという伝承がある動物がのっぺらぼうの正体として明かされることも多い。
八雲の「狢」の話を紹介しよう。・・・
江戸は赤坂の紀伊国坂は、日が暮れると誰も通る者のない寂しい道であった。ある夜、一人の商人が通りかかると若い女がしゃがみこんで泣いていた。心配して声をかけると、振り向いた女の顔には目も鼻も口も付いていない。驚いた商人は無我夢中で逃げ出し、屋台の蕎麦屋に駆け込む。蕎麦屋は後ろ姿のまま愛想が無い口調で「どうしましたか」と商人に問い、商人は今見た化け物のことを話そうとするも息が切れ切れで言葉にならない。すると蕎麦屋は「こんな顔ですかい」と商人の方へ振り向いた。蕎麦屋の顔もやはり何もなく、驚いた商人は気を失い、その途端に蕎麦屋の明かりが消えうせた。全ては狢が変身した姿だった。
⇒この「狢」の話は、二度にわたって人を驚かせるという筋立ての怪談「再度の怪」の典型である。
「なんで、のっぺらぼうには顔がないのかな?」
「結局は、キツネやタヌキの化け話。単に人間を驚かしたいだけ。それ以上の悪気はないようだよ。まぁ、かわいい妖怪じゃないか。」
「日本独特の気配で人を怖がらせる妖怪だね。気配だけで驚かすなんて粋の世界とも言えそうだけど・・・」
「顔を失くすということは表情を隠すということだよね。先ほど‘人間は顔の動物だ’という話をしたけど、これは逆行しているよね。」
「人はいろんなことを考える。それがついつい顔に出る。それを悟られまいと顔を隠すわけだ。犯罪人はメガネやマスクや帽子などで顔を隠したり、変装したりする。のっぺらぼうはその典型かもしれないな。」
「つまるところ、顔がないということは没個性ということだ! 自分の考えや主義主張を持たない人はのっぺらぼうになっちゃうんだね。」
「最近はネットで他人のことを誹謗中傷する輩が増えた。あれは顔のない犯罪だと思う。実際に誹謗中傷で自殺した有名人もいたわけだから、殺人罪と言っていい。
顔が見えないことをいいことに平気で他人を誹謗中傷する。それは人間に悖(もと)る恥ずべき行為だ。そんな輩には絶対に貧乏神がつく。のっぺらぼうも笑っていると思うよ。」
「本当にそうだな!」
JUNさんがポラのコメントでこう書いてくれた。
「人それぞれの顔。これこそが、人間の大切な部分であり、個性なんです。(中略)この顔により、人生を生きていく。そして、この顔により、人を慈しむ。」と。
おしまい