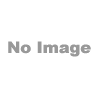今回は一周年作について私なりの感想を述べてみたい。最初に拝見した頃とだいぶ本作品に対するイメージが違ってきている。
一周年週の初日H27年12月21日に、初めて新作を拝見。
内容を簡単に紹介しよう。
三波春夫のよく透き通る甲高い歌声が流れる。「世界の国からこんにちは」は1970年の大阪万博のテーマソング。
最初に、さゆが和物の衣装で正座して登場。赤と銀で左右に煌びやかに分かれている。扇子をもって歌に合わせて「こんにちは」と客席にお辞儀をして回る。この衣装は、次のお正月公演にもピッタリだ。
次に、半袖で膝丈のコンパニオン・ルックに着替える。青と白のラインがさわやか。銀色のステックを手に持ち、水色の短靴を履いて、軽快に踊る。
懐かしい音楽が次々と流れる。「白い色は恋人の色」や「愛と風のように」。後者は日産のCMソングで、ケンとメリーのスカイラインとして人気を博した曲。
今回の作品では、TVの実況中継が曲の合間に流れるのが特徴。その中で、最初にケンとメリーのスカイラインのCM放送が入った。懐かしくて、思わずニヤッとする。
セパレートな軽装で登場。上がたくさんの糸が垂れている白い衣装で、下は水色のパンタロン。当時の懐かしいファッション。途中からパンタロンを脱いで、下も上と同じ白い衣装へ。
茶色の帽子をかぶりながら踊り、そのままベッドへ。帽子を客席へ投げる。
ベッドではインストルメント(歌のない演奏)が流れる。このメロディがとても心地よく耳に触れる。そして、立ち上がり曲が吉田拓郎の「今日までそして明日から」。アップテンポな曲に変わり、客がみな手拍子を始めた。曲の最後に、客席に預けた帽子を受け取り去っていく。
なかば予想通り、大阪万博の演目だった。
10月のDX歌舞伎で周年作品について話しているときに、さゆが大阪万博に関するものを考えていることを知った。しかし、私にはさゆの想いやイメージが全く分からなかった。大阪万博って1970年だから、さゆが生まれるずっと前のこと、なのに、なぜ大阪万博なのだろうかと不思議に思ったのを覚えている。その時点では、このテーマで確定していたわけでなく、いまだ模索中の様子だったのでこれ以上突っこまなかった。
実際、この周年作は今までのさゆの作品イメージとかなり違う。デビュー作を除き、さゆが自分で創り上げてきた作品群には、アイドル系の王道というべきものばかり。二作目の水着ものに始まり、セーラー服もの、ウエディング、そしてクリスマスものと、エロかわ路線をまっしぐらに突き進んできた。これが可愛いさゆのイメージにぴったりヒットして人気がブレイク。六作目にあたる周年作をどうするかが大きな課題でもあった。このままアイドル路線で行くのか、少し新しい分野に挑戦してみるか。後者としてはどんなものがあるか。面白いものでいくか、かっこいいものでいくか、シリアスに感動させるものでいくか、着物でしっとり舞う和物、ダンスで魅了する等々、選択肢はたくさんある。いずれにせよ、頭を悩ますね。
今回の演目は、面白さを追求したものかなと最初思った。おじさんウケ狙いというか、懐メロのオンパレードだからね。
もともと、さゆの選曲はおじさんウケするとの定評がある。よく若い踊り子さんが最近のアニソン(アニメソング)を多用してくるが、我々の世代だと全く知らない曲ばかり。その点、さゆの選曲は我々が青春時代に聴いていた曲にぴったしヒットしてきて懐古心をくすぐられる。セーラー服の演目での森昌子のデビュー曲「先生」は最高だと思う。だから、今回の作品はおじさんウケ狙いの延長線かなと感じた。ただその時に思ったのが、ストリップは四十代、五十代のファン層が多い中で、この選曲はいささか古すぎるな!という点。私でさえも、聴いたことがある程度であり、青春真っ只中ドンピシャリではなかった。私より少し上の世代にはドンピシャリだったようだ(笑)。中には、「この選曲は太郎あたりがアドバイスしたものだろう。さもなければ、若いさゆみさんが知っているはずがない。」などと言う人もいた。実際のところ私も記憶がほとんど無い(笑)。
ラスト曲の吉田拓郎は、井上陽水と並び、フォーソング界の巨匠。この二人は我々の青春にドンピシャリ。ただ「今日までそして明日から」という曲は今では拓郎の代表作として知られるが、拓郎三枚目のシングルとして1971年にリリースされた当時はそれほど売れていなかった(オリコン59位)。ようやくステージで人気が出始め、翌年1972年リリースの名曲「結婚しようよ」で完全ブレイクした。だから、ノスタルジーを掻き立てるのに何故この曲を選んだのかもよく理解できなかった。
もっといえば、ラス前のインストルメントは懐メロではない。
これらの懐メロの関連性が今ひとつ理解できなかった。
また、今回の作品ではTVの実況中継が曲の合間に流れているという話をしたが、ジャンボ鶴田と天龍が谷津嘉章に勝ったというプロレス中継まではプロレスファンとして微笑ましい懐かしさがあったものの、東京オンピック決定の場面はつい最近のもので、ノスタルジーとは全く次元が違う。なぜ東京オリンピックまで入れたのか理解できなかった。ストリップファンの中には、東京オリンピックはストリップ衰退の元凶だ!と捉えている人もいるくらいだからね。
こうした幾つかの疑問が、この作品の理解を妨げ、すっきりと客に受け入れられない要因になっている。
実際、周年作を一番観ている私や石原軍団メンバーが、この周年作を懐メロのオンパレードとしてしか受け取っていないのが現実である。
ただ、私の場合、周年作を拝見した翌日に手紙で、演目名にするには「昭和ノスタルジー」がいいんじゃないかという感想を書き、それに対して、さゆからボラコメを頂いたので、今回の作品がクレヨンしんちゃんの映画をモチーフにしているのが分かった。「クレヨンしんちゃんの映画『オトナ帝国の逆襲』をテーマにしました。見たことあるかな? ちょー面白いから是非見てみてね。」
その時には、周年イベントの準備で忙しく、落ち着いて周年作の感想レポートに取り組む余裕がなかった。今回、大和に来て、改めて周年作を眺めながら色々感ずるものがあった。さゆからの「太郎さんには童話書いてもらいたいなー☆」という一言で、すぐに周年作の童話化に着手。四日にメモし、翌五日に話の構想を練り、六日目に一旦童話「ノスタルジーの囁き」は出来上がった。この童話を仕上げる過程で、この周年作が昭和ノスタルジーではなく、人への応援歌であることが理解できるようになった。翌日、少し推敲し、応援歌であることを強調するため副題を「生きる勇気」とした。そして、八日目に渡す。
さゆからの感想が嬉しかった。「童話、うれし~。すごく良かったよ。そ~人生がんばろうって応援の演目なの! うれしい~。さすがだね。」「人によってはすごく泣けるねとか言ってもらえてうれしい☆ 泣けるくらい心動かす演目つくれてうれしい。もっと頑張るぞ~。」「周年作は昭和って感じより人生賛歌みたいな。またしっかり練り直して出します。楽しみにしてて。」「オトナ帝国観た? ちょ~感動するシーンがあって絶対泣けると思うよ! 人が死なないのに泣ける映画!」次々と周年作の解説をいただく。これも童話がきっかけになってくれた。
おそらく、モチーフとなっている映画を観て感動の涙を流した人はすぐに周年作の本題を感じ取り一緒に涙することができるのだろう。いずれにせよ、この映画を観ないことには始まらないと悟った。
この映画はアニメを超えている。クレヨンしんちゃんという大人を小馬鹿にした主人公のキャラをうまく活かしながらも、まさにキャッチコピーの「未来はオラが守るゾ」というように型破りに未来を手に入れていく。物凄く哲学的な奥深さを持っている。
私はすぐにドイツの児童作家ミヒャエル・エンデの名作『モモ』の時間泥棒を思い出した。とある街に「時間貯蓄銀行」と称する灰色の男たちが現れ人々から時間が盗まれていく。皆の心から余裕が消えていく。しかし、貧しくても友人の話に耳を傾け、その人自身を取り戻させてくれる不思議な力を持つ少女モモが、冒険の中で奪われた時間を取り戻すというストーリー。
童話『モモ』が人々から時間を奪うことで人間らしさを失っていくのに対して、『オトナ帝国の逆襲』は、あ~あの頃に帰りたいなぁという大人たちの懐古心をくすぐり、昔のニオイでもって大人たちを子供に戻してしまう。大人たちが仕事や家事等のやる気を無くしたため子供たちが大いに困る。
映画『クレヨンしんちゃん オトナ帝国の逆襲』は2001年に公開された『クレヨンしんちゃん』の劇場映画シリーズの9作目。ちなみに、この題名は、当時公開されていた映画『スターウォーズ』シリーズの「帝国の逆襲」をもじったものらしい。
あらすじを簡単に紹介する。
かつて大人たちが体験した昔懐かしい暮らしが再現された「20世紀博」というテーマパークが日本各地で開催されていた。ひろしやみさえら大人は、懐かしさに浸って20世紀博を満喫する。帰宅しても、昔懐かしいテレビ番組などに夢中になる。
この20世紀博は、ケンをリーダーとした秘密結社「イエスタディ・ワンスモア」の恐るべき陰謀であった。
ある晩、テレビで20世紀博から「明日、お迎えにあがります」という放送があり、これを観た大人たちは突然人が変わったように眠りにつく。
翌朝、町中の大人たちに異変が起きていた。大人たちは家事や仕事を忘れて遊びほうけ、まるで子供のようになってしまった。そして、お迎えの車が来て、大人たちはそれに乗り込み、子供たちを置き去りにして走り去ってしまう。
野原しんのすけ、風間トオル、桜田ネネ、佐藤マサル、ボーちゃんら子供たちが、各々の両親を取り戻すために20世紀博に乗り込む。
最初は、20世紀の懐かしさに洗脳されていた野原家のひろしとみさえが途中から目が覚める。ひろしの足のニオイで洗脳が解ける。この時の「ひろしの回想」は名場面である。心地よいインストルメントが郷愁を誘い、自然と泣けてくる。
そして、野原家が一丸となって秘密結社「イエスタディ・ワンスモア」に対抗する。
しかし、リーダーであるケンとチャコの夫婦が20世紀博の屋上にあるスイッチを押せば、また子供に戻ってしまうらしい。しかも、どんなことをしても元に戻れないらしい。夫婦がエレベーターを使い屋上に上がる。それをしんのすけが食い止めようと、必死で階段を駆け上がる。途中、何度も転び、顔が傷だらけになりながらも必死で追いかけ続け、スイッチを押すのをなんとか食い止めた。このしんのすけの姿に感動。
原恵一監督は「まず大阪万博ありきだった」との趣旨の発言をしている。当時の新しい未来像の象徴でもある大阪万博を異様なまでにモチーフとし、「未来に希望が無いなら一度やり直そう」というケン&チャコと、「これから自分たちが新しい未来を切り開く」という野原家の決意がメインテーマになった見事な作品である。
この映画を観ることで、初めて周年作におけるさゆの想いが理解でき、周年作がこのモチーフを見事に表現していることが分かる。人間賛歌というべき素晴らしいテーマをもっていながら、これが昭和ノスタルジーくらいにしか捉えてもらえないのがすごく残念。
この周年作には解説が要る。少なくとも演目名を「クレヨンしんちゃん オトナ帝国の逆襲」と明記すべきだろう。そして作品に関心のある人にはボラコメにて是非映画を観るように勧めたらいいと思うよ。
平成28年1月10日 大和ミュージックにて
~石原さゆみさんの一周年作を記念して~
私はダメな男だ。事業に失敗し、会社も家庭もいっぺんに失った。信用していた部下の裏切りに遭い、会社はにっちもさっちもいかなくなった。人間不信に陥ってしまい、もう生きていてもしょうがないと思えるほどの精神状態になる。
駅裏の路地をうつむき加減でとぼとぼ歩いていたら、ふと、ストリップ劇場の看板が見え、ふらりと中に入った。
一人の若い踊り子のステージが始まったばかり。笑顔がとてもかわいかった。しかし、私は今更若い娘のヌードにどきどきするような気分になれなかった。
ふと、耳に懐かしい歌声が入ってきた。なんと、三波春夫の「世界の国からこんにちは」。これは1970年の大阪万博のテーマソングじゃないか。なんで、こんな若い女の子がこれだけ古い曲を使っているのか不思議だった。
それだけではく、「白い色は恋人の色」や「愛と風のように」と懐メロがどんどん続いた。後者は日産のCMソングで、ケンとメリーのスカイラインとして人気を博した曲だ。男の子として車に興味を持ち始めた頃だったので懐かしくてたまらない。
彼女の選曲が私の心の中にノスタルジーの嵐を激しく巻き起こす。
彼女のステージは後半のベッドショーに入いる。きれいなパイパンが見えた。若さに輝いていて眩しいほど。思わず私は見とれていた。すると、ヴァギナがかすかに開いて私は中に吸い込まれた。
どれくらいの時間が経ったのかわからない。ものすごく短いかもしれないし、すごく長かったのかもしれない。そんなことはどうでもよかった。
ふと気付いたら、そこに1970年の自分がいた。私は空中に浮かんでいるように、時空の隙間から昔の自分のことを眺めた。
瞳をきらきら輝かせた少年。まだ眼鏡をかけてない。そう、当時の私は小学五年生。
当時、世の中は科学技術が大きく進歩した時代で、アポロ計画で人間が月の上に一歩を刻んだ。持ち帰った月の石が大阪万博のアメリカのパビリオンに展示されていた。私は宇宙や科学に心をときめかしていた。大阪万博はその象徴。私は当時、小学校の図書館で大阪万博の写真図鑑を何度も何度も借り換えして、他の人に回さないほどにずっと一人で借り続けた記憶がある。
図書館と言えば、当時は江戸川乱歩の少年探偵団シリーズに夢中だったなぁ。名探偵/明智小五郎と小林少年率いる少年探偵団が怪人二十面相と争うシーンに胸を高鳴らせた。その後、当然ながら次はシャーロック・ホームズや怪盗ルパンにもはまっていく。将来何になりたいかと聞かれたときは、探偵があこがれの職業でもあったなぁ~。
66歳で亡くなった父親を思い出す。プロレスが大好きで、ふだんは仕事で遅いのに、プロレスがTV放映される日に限って早く帰ってきてたなぁ~。晩酌している父親と一緒にプロレス観戦しているのは楽しかった。
近くにTVが置いてある。大阪万博のにぎわう模様が映し出された。水色の制服を着たコンパニオンがいる。あっ!ステージの上にいた踊り子と同一人物だ。
なにもかにもが懐かしく思い出される。あの頃のきらきら輝いている瞳にすべての原点があるよな~。死にたいなんて考えるのは止そう。生きよう。そうして、もう一度、一からやり直してみよう!そんな気分になれた。
ふと気付くと、私は盆周りのかぶり席に座っていた。
その踊り子のベッドショーが続いていた。
スローバラードから、吉田拓郎の「今日までそして明日から」というアップテンポな曲に変わり、客がみな手拍子を始めた。
私は今日まで生きてみました
時には誰かに裏切られて
時には誰かと手を取り合って
私は今日まで生きてみました
そして今 私は思っています
明日からもこうして生きていくだろうと♪
やけに歌詞が心に響く。この歌は私への応援歌のように思えてならなかった。
彼女は私に向かって、やさしい笑顔で手を振りながら、舞台から消えていった。
彼女は私の心の傷を癒してくれたストリップの白衣の天使だった。
おしまい