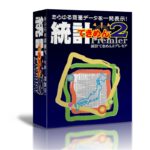立地コラム(45-1)「慣れ」が来る前に店の外装は変えよう1
売上予測に使うデータなら商圏分析ソフト”統計てきめん2プレミア”
●立地コラム(1)手ぶらで現場を見に行く 1
●立地コラム(2)手ぶらで現場を見に行く 2
●立地コラム(3)手ぶらで現場を見に行く 3
●立地コラム(4)店は立地よりも、商圏だ
●立地コラム(5)セットバックした店は、長続きしない。だから工夫を。
●立地コラム(6)結局、物件というものは、どこかの撤退物件。
●立地コラム(7)物件探しで、重要なのは、利用者つまり住む者の利便性
●立地コラム(8)赤字の店1店舗出すことは、もう1店舗も犠牲になること
●立地コラム(9)人は、住んでいる場所によって他の人と似たような行動をする。
●立地コラム(10)看板を増やせば売上げも増えるか?
●立地コラム(11)マーケットの大きさを知る
●立地コラム(12)マーケット規模とは、『人口』のことではない
●立地コラム(13)商業統計は「繁盛度合い」のバロメーター
●立地コラム(14)商業統計を「人口」に変換する 立地コラム(15)看板増やして売上げが増えるかは、業種業態による
●立地コラム(16)マーケットの大きさを知る
●立地コラム(17)マーケット規模とは、「人口」のことではない
●立地コラム(18)商業統計は「繁盛度合い」のバロメーター
●立地コラム(19)商業統計を「人口」に変換する
●立地コラム(20)購買人口こそ、都市の本当の人口
●立地コラム(21)ちょっと“商業統計”について オレンジジュリアス,ホワイトキャッスル,森永ラブ、ドムドム、100円バーガー
●立地コラム(22)立地分析で“昼間人口”はさほど重要な要素とはいえない理由
●立地コラム(23)昼間人口にこだわる必要はないが、それは、別の大きな意味がある
●立地コラム(24-1)新しい統計指標 年収別世帯数
●立地コラム(24-2)新しい統計指標 年収別世帯数
●立地コラム(25)TG(ティージー)とPC(ピーシー)という二つの重要な立地用語
●立地コラム(26-1)PC、そして・・動線
●立地コラム(26-2)PC、そして・・動線
●立地コラム(27)施設の中にあるTG
●立地コラム(28)動線の質
●立地コラム(29)「動線」と「導線」の違い
●立地コラム(30)ショッピングセンター内での立地
●立地コラム(31)見えない立地は危うい
●立地コラム(32)見えない立地でも、見てくれる道路
●立地コラム(33)見えている「はず」が一番よくない
●立地コラム(34)見え「過ぎ」ているも良くない。
●立地コラム(35)「派手だから見える」は間違い
●立地コラム(36)えっ?商圏が○○キロ?
●立地コラム(37-1)商圏の「決め方」その1
●立地コラム(37-2)商圏の「決め方」その2
●立地コラム(38-1)商圏の「決め方」その3
●立地コラム(38-2)商圏の「決め方」その4
●立地コラム(39-1)商圏の「決め方」その5
●立地コラム(39-2)商圏の「決め方」その6
●立地コラム(40-1)商圏の3つの要素
●立地コラム(40-2)商圏の3つの要素 その2
●立地コラム(41-1)「行動ベクトル」とは。1
●立地コラム(41-2)「行動ベクトル」とは。2
●立地コラム(42-1)TG(ティージー;交通発生源)のこと1
●立地コラム(42-2)TG(ティージー;交通発生源)のこと2
●立地コラム(43-1)来店頻度を高める立地とは 1
●立地コラム(43-2)来店頻度を高める立地とは 2
●立地コラム(43-2)来店頻度を高める立地とは 3
●立地コラム(44-1)来店頻度を高める立地とは 4
●立地コラム(44-2)来店頻度を高める立地とは 5
●立地コラム(45-1)「慣れ」が来る前に店の外装は変えよう1
前回、「知覚の量がある一定の水準を超えると来店行動が起きる」という仮説を申し上げました。
「仮説」は、あくまで「仮説」であって、まだ、事実と認定されているわけではありません。しかし、そうした仮説でも、何の脈絡、根拠がなく設定されたわけではありません。
実は、これ、「刺激量がある一定以上になってはじめて知覚する」という科学的事実に基づいています。
例えば、7リットルの水にスプーン1杯の砂糖を溶かしたとき初めてその甘みを感じます。また、頬の上に1cmの距離から落とされたミツバチの羽をやっと感じることができるといわれています。
この一定以上の刺激量は「絶対閾(ゼッタイイキ)」と呼ばれています。つまり、人間は、どんな感覚(視覚・嗅覚・味覚・聴覚・触覚)でも、その刺激量が絶対閾を越えない限り、知覚しないということなのです。
絶対閾は、実験室のような他の騒音や光などがないような場所での測定です。これに対して、「弁別閾(ベンベツイキ)」というものがあります。
それは、すでにある一定以上の刺激があるなかで、その「変化」が生じたかどうか、例えば、「光が強くなった(明るくなった)」とか、「少し重くなった」と感じるための「僅かな差」のことを指します。
明るさの場合、この弁別閾は、元の明るさに比べて7.9パーセント変化することです。音の大きさなら4.8パーセント、重さなら、2パーセントです。
これらのことから、私たちの行動に対しても同じようなことが言えるのではないかと立てたのが、冒頭で挙げた仮説です。
普段の日常生活の中で見る景色の形や大きさ、色の配分、パターン、動きはそのほとんどが、「毎日同じ」ようなものです。少なくとも、人間の「脳」は毎日、毎日、目で見た全ての光景を記録しているわけではありません。そんな非効率なことをしていたら、さすがの大容量の「脳」でもあっという間に記憶で満タンになってしまいます。
ですから、それを防止するため「脳」は、景色を見ながら、どんどんパターン化、抽象化していきます。そして、視覚情報を最小限の情報に変換してしまう。逆に言えば、見たもののほとんど全てを消去してしまう。本当に印象に残ったものや、普段と異なる情報、あるいは、危険に晒されたときの情報などに「限って」記憶しておく。
そういう「効率的な脳」であるようです。
この「効率的な脳」に記憶してもらい、来店行動にまでつなげてもらうにはどうしたら良いか?
まず、第一は、脳に知覚してもらわないとなりません。それには、脳が知覚するに足る「刺激」、すなわち弁別閾以上の刺激が必要です。
そして、「学習」させる。それは、繰り返し、繰り返し、知覚、記憶を行うことです。
統計てきめん2プレミアのダウロードサイト
統計てきめん2プレミアの紹介動画5分
YouTube 統計てきめんの活用講座
1.統計てきめんの基本操作
2.統計てきめんの統計項目の変更方法
3.統計てきめんの多角形商圏での集計
4.統計てきめんの色分け分布表示の設定
5.統計てきめんのグリッド表示の変更方法
統計てきめんの時間圏作成シミュレーション◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
林原安徳:有)ソルブは、立地と高精度/売上予測で「不振店」を根絶します。電話 048-711-7195 メール問合せは、こちら
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
引用元:立地コラム(45-1)「慣れ」が来る前に店の外装は変えよう1・・・