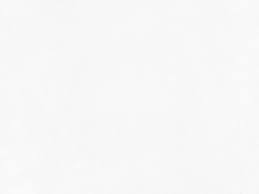陶磁器の妖しい魅力…それは人が生み出した宝石というべきか…本来地中にて数千万年・数億年かかるプロセスが、土に炎を加えることによりわずかの時間で窯から宝石のような焼物が現れてくる。そしてその土もまた地中にて気が遠くなるような長期間かかって形成されたものである。土から石へ、そして石からまた土へ、輪廻転生に似たサイクルが焼物の小世界にはこめられている。
陶磁器の教科書などを開くと、陶土の3要素として石英・長石・粘土があげられており、それを大体のところ1-1-2の割合で混ぜて混ぜて焼いたものが通常の陶磁器である。
もちろんほぼ100%石英である海砂などを除いては、それぞれの成分が単独で採掘されるわけではなく、各成分がミックスされた原土(有田の泉山陶土はそれ自体で磁器の原料として各成分が理想的にmixされていることで有名)採掘されて不要な部分を除く精製工程をへて陶土の原料となる。
その中でも最も入手が困難なものは粘土であり、その良質なものの入手は極めて難しい。
何をもって良質な粘土というかは、成形時に粘りがあることや焼成時に耐火度が高く変形しないことなどの様々なファクターがあるが、やはり歴史的にハードルが高く得難い特性とされていたのはその“白さ”である。石英や長石は白いものが容易に入手できるが、粘土は不純物が混じることが多く白いものは少ないのである。
その白色粘土は、陶磁器のメッカというべき中国・景徳鎮の近くの高嶺(高稜)から採掘されるものが世界的に名高かったためカオリンと呼ばれるようになった。別名チャイナ・クレーともいう。

中近世のヨーロッパでは白色磁器は中国から(後には日本からも)輸入される最高級の贅沢品であり、金に等しいような値段で取引され、国王の宮殿には磁器の間(画像上はシャルロッテンブルク宮殿の磁器の間)が設けられてその贅を競っていた。
もちろんヨーロッパ各国ではこの貴重な磁器を自製しようと長年研究を重ねたが誰も成功しなかった。新旧大陸の植民地も含めて肝心のカオリンをどこにも見つけられなかったからである。
英国ではついにカオリンを探すのをあきらめてボーンチャイナに走った。これはカオリンの代わりに牛の骨灰を用いたもので、通常の土の白さではなくミルク色の白さが出るがこれは好き好きというものであろう。
ところが皮肉なことに、世界最大のカオリン鉱床は英国の地下に眠っていた。
英国の西南端に突き出た半島部のコーンウォール地方(画像下)であり、この辺りは地の果てという意味でランズ・エンド(Land‘s End)とも呼ばれている。

コーンウォールのカオリンが英国陶磁器の父とも呼ばれるウィリアム・クックワージーによって“発見”というか工業的に採掘されるようになったのは18世紀半ばである。
露天掘りで採掘できてそれほど技術難度が高いとも思われないのにこれまで発見されなかったのは、表土を剥ぎ取った後に水簸により不純物を除く技術と資本力が不足していたためであろう。
コーンウォールのカオリン鉱床からはこれまでに約1億2000万トンのカオリンが採掘されたといわれており、あと数百年分の埋蔵量は確認されている。
なお現在粘土資源の枯渇が問題になっているのは、主として日本が産地である可塑性が特に良好なやや黒色がかった粘土であり、白色粘土(カオリン)ならコーンウォール等を考慮すれば実質的には無尽蔵といえる。

その現役のピットには今でも年間百万トン以上の採掘量を誇るものもいくつかあり、そこはまさに火星のような荒涼とした光景(画像上)である。
年間百万トンというと水簸による“歩留り”を5%(通常よりはるかに低いがこれがコーンウォール鉱床の特徴)とすると年間2000万トンの原土を掘り出さなければならない。
直径数KMの露天掘りピットから年間2000万トン掘り出すというと、これはもうユンボやトラックを使っていたのでは話にならないことは計算してみればわかる。
また粘土の卸売価格の相場がトン5万円(最高級粘土といっても山元卸値はキロ50円くらい)とするとそのピットの年間売上高は500億円となるので採掘コストはそれよりはるかに低く抑えなければならない。
そこで開発されたのが巨大な水鉄砲を使って鉱床を砕いて瞬間的にスラリーにしてしまい、そのスラリーを“川”にして下流の水簸工場に流していくという豪快な?システムである。スラリーの濃度を10%とすると年間2億トンのスラリーが流れていくことになる。
40年ほど前、筆者は話のタネにその“水鉄砲”を打たせてもらったが、数十メートル先の鉱床が目の前で文字通り木端微塵になるのは大変な迫力であった。なおそこに人間が立っていると、完全にバラバラになって痕跡をとどめないとのことである。
もちろんクックワージーによるカオリン鉱床の発見当時はこんな近代的な仕掛けはなく、手作業で水簸をしていたのであろうが、それにしても水簸により取れる粘土は原土の5%というのはあまりにも少ない。なお通常の粘土鉱山の水簸歩留は20-50%であり、可塑性重視で色をあまり気にしない銘柄では100%に近いものもある。
したがってこれを“産業”に育て上がるには大資本を投入して大規模な鉱山コングロマリットで量産効果を狙わなければならないし、またそれが可能なだけの世界最大の大鉱床でもあった。
そこで登場するのが鉱床地帯のコーンウォール地方の大地主であり、クックワージーの事業の後援者となったトーマス・ピットである。ピット家は後に親子で英国首相となり世界史に大きな影響を与えた大ピット・小ピットを輩出して有名になるが、ピット家が大資産家に成り上がるきっかけとなったのが、インドのマドラス総督であったトーマス・ピットによる世界最大級のリージェント・ダイヤモンド(別名ピットダイヤモンド・画像下)の入手であった。

このダイヤモンドは“呪いのダイヤ”として後世有名になるが、もともとはインドの鉱山奴隷が原石を発見したものである。彼は自分の足を切り抉って足の肉の中に原石を隠して逃亡し、貿易船の船長にダイヤの売り上げを山分けにする約束で船にかくまってもらう。しかし船長はこの奴隷を殺してダイヤを奪い、その船長も一時はこのダイヤを売って大金持になるものの後に破産・発狂して自殺する。ダイヤはまわりまわってピットの手に渡り、彼はこのダイヤを持って英国に帰国する。そしてフランスの摂政(Regent)オルレアン公フィリップ2世に国家予算的価格で売却することに成功し、大資産家となってコーンウォールの広大な土地を買い占める。
なおダイヤはその後、マリー・アントワネットの手に渡り、ナポレオンの皇帝戴冠式では彼の儀丈剣の柄頭に用いられ、ルイ十八世とシャルル十世の王冠やナポレオン三世の帝冠にも飾られるが、その持ち主の多くは悲劇的な最後を迎えることになる。なお現在はこのリージェント・ダイヤはルーヴル美術館に展示されている。
ピットはこのダイヤから得た資金をコーンウォールのカオリン鉱山の開発に投入し、またクックワージー主導で窯を最初は地元プリマスに開いたが、後に英国陶磁器のメッカというべきストークオントレント(ウェッジウッドやミントンなどの陶磁器メーカーの多くはここに本拠を構える)まで運河でカオリンを運ぶルートを開拓して英国陶磁器産業の基礎を築き上げた。
コーンウォールの荒涼たる大地はダフネ・デュ・モーリアが描く世界やアーサー王伝説などで著名であるが、陶土の世界でもロマンに満ちた地域である。
(コーンウォール訪問記)
私の専門は社会人になって以来陶磁器・セラミックス(粉を固めてから焼いて作るものは何でもセラミックス)であり、40年ほど前にコーンウォールの粘土採掘現場(画像下)への初訪問した時のこと。

まず驚いたのがエアーラインである。
ガトウィック空港(ロンドン)の一番はしっこに止まっていたのは20人乗りくらいのプロペラ機。まあとんでもない田舎に行くんだからこんなものだろうと乗り込んだが、チケットの座席番号には0と書いてある。ゼロとは何か? 驚いたことにそれは副操縦席だった。
おまけにパイロットは飛行中にスチュワーデスとお茶を飲みながら雑談するために席を立ってしまった。完全に操縦席にひとりぼっち。とんでもない航空会社もあったものだが、英国南部田園地帯のどこまでもうねうねと続く緑の世界を堪能できた至福のフライトであった。
フライトといってもバス路線の感覚であり、次々と停留所じゃなくてローカル空港に着陸し、中には無人空港もあるので、その場合はパイロット自身が乗客を誘導するのだから忙しい。
まあ陶土の鉱山というのはそんなに便利なところにはないので、飛行機で近くに行けるというのは幸運ではあるのだが。
コーンウォールで泊まったホテルは田舎にしてはなかなかの高級感である。
部屋には足首まで毛足でかくれるような贅沢な絨毯が敷き詰められている。
しかし…その絨毯の上に大型猫足バスタブがデンと鎮座している。
このバスにどうやって入れというのか?
コーンウォールを車で走っていると、遠くに“Cornish Food”の大看板が見えた。これはケルト伝統料理を供する店かなと期待して近づいてみると“Cornish Ford”であった。
なおこの辺りはアングロサクソン侵攻以前のケルト文化が残る、平均的英国人にとっても異国的な地域であるが、ケルト語をしゃべる最後のコーンウォール人は200年ほど前に死に絶えたそうである。
鉱山の担当者から聞いた愚痴。
“この地区にはこの鉱山しか産業がないので、雇用も税金も道路も病院もすべてこの鉱山に依存している。それにもかかわらず鉱山はこの地区の住民からは非常に嫌われている。粘土鉱山というのは数百年にわたり環境を破壊し光景を荒涼としたものに変えてしまうからであり、因果な商売だ”
…と酒を飲みながら相手はこぼした。ランチタイムに社員食堂(笑)で。ヨーロッパでは昼食時に酒を飲むのは珍しいことではないが、これほど大量に(まず立ち飲みカウンターでエールビールを私は1パイント・相手は3パイント、そのあとテーブルに移動してワインを二人で1本)飲んだのは初めて。さすがに英国人は強いと感心したが、その担当者は午後の会議ではずっと居眠りしていた。
この話にはまだ続きがあって、その数年後、突然その担当者から電話がかかってきた。
粘土ではなく、その粘土鉱山自体を経営する会社を買いませんか(笑)というお誘いだった。
ここだけでなく、欧州中に各種原料鉱山を経営するコングロマリットであり、上に諮るまでもなく手に余る話なので丁重にお断りした。
日本がまだ経済大国であった時代の話である。