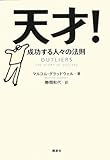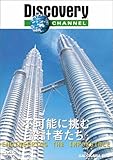海馬―脳は疲れない (新潮文庫)/池谷 裕二
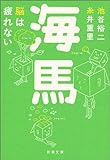
¥620
Amazon.co.jp
脳科学の知識に基づいた方法論を考えるなら
この本が参考になる。
たとえば、記憶をつくる海馬は、刺激によって増える。
刺激を増やすために、旅をしようとか
無理をしてみるとか。
鼻歌うたえなんて、くだらなすぎて思いつかない(笑)
それから、おもしろい話をもう一つ。
ニンジンを見たときに反応する神経細胞があることがわかっているらしい。
要は、脳が物を認識するとき
基本図形約500個の組み合わせで
見ている物体が何かということを判断するらしい。
500個の中から1個選ぶ組み合わせは500通り。
500個の中から2個選ぶ組み合わせは約12万通り。
500個の中から3個選ぶ組み合わせは約2070万通り。
これを4個選ぶとき、5個選ぶとき、・・・と足していけば
想像もつかない数になる。
こういう仕組みで、限りある神経細胞で、それよりたくさん存在する物を認識できる。
認識するための基本図形が異なるから
個性が生まれるし、プロフェッショナルとアマチュアの違いが生まれる。
基本図形を1個増やすだけで、認識できるものは莫大に増えるから
新しい視点を加えることがとても重要なのだ。
という話。
結局これも刺激を増やすといいってことになるのか。
何でもかんでもやってみるなんてことをしてたら
時間がいくらあっても足りないので
ちょっと面白そうと思ったら
フットワークを軽くしてやってみようかな。
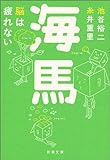
¥620
Amazon.co.jp
脳科学の知識に基づいた方法論を考えるなら
この本が参考になる。
たとえば、記憶をつくる海馬は、刺激によって増える。
刺激を増やすために、旅をしようとか
無理をしてみるとか。
鼻歌うたえなんて、くだらなすぎて思いつかない(笑)
それから、おもしろい話をもう一つ。
ニンジンを見たときに反応する神経細胞があることがわかっているらしい。
要は、脳が物を認識するとき
基本図形約500個の組み合わせで
見ている物体が何かということを判断するらしい。
500個の中から1個選ぶ組み合わせは500通り。
500個の中から2個選ぶ組み合わせは約12万通り。
500個の中から3個選ぶ組み合わせは約2070万通り。
これを4個選ぶとき、5個選ぶとき、・・・と足していけば
想像もつかない数になる。
こういう仕組みで、限りある神経細胞で、それよりたくさん存在する物を認識できる。
認識するための基本図形が異なるから
個性が生まれるし、プロフェッショナルとアマチュアの違いが生まれる。
基本図形を1個増やすだけで、認識できるものは莫大に増えるから
新しい視点を加えることがとても重要なのだ。
という話。
結局これも刺激を増やすといいってことになるのか。
何でもかんでもやってみるなんてことをしてたら
時間がいくらあっても足りないので
ちょっと面白そうと思ったら
フットワークを軽くしてやってみようかな。