いいお天気です。
このところ、ずっと経営者保証ガイドラインについて書いてきています。経営者が法人借入について差し入れている連帯保証についてはその履行について免責を受ける可能性が増しました。
しかし、依然として個人破産を選択せざるを得ない場合があります。次のような場合です。
1.法人が法的整理、準則型私的整理手続(中小企業再生支援協議会、特定調停など)をしないで単純に営業停止した場合…経営者保証ガイドラインの適用対象外、となりますので通常の手続きを経て連帯保証履行を求められます。履行できなければ個人破産を選択した方が良いケースも出てくると思います。
2.法人が、法的整理、準則型私的整理手続を行い、法人借入れの連帯保証について保証債務の免除を受けたとしても、その他の債務、住宅ローン、個人で借りたカードローンなどが返せなければ個人破産に進まざるを得ません。
3.法人に対して経営者以外の第三者が連帯保証している場合で第三者がその会社の役員など経営にタッチしていない場合は経営者保証ガイドラインの適用はありません。社外の友人や、親せきなどを連帯保証人にしている場合、夫婦で連帯保証したがその後離婚している場合など、経営者保証ガイドラインで救済するのは難しいと思われます。
昨日は1.のパターンの社長さんのご相談をお受けしました。
法人はすでに破たんし、営業停止状態になっています。
法人借入については期限の利益喪失に進んでいます。
個人破産についてご説明した中で意外な反応をいただいたのが「公租公課」でした。
地元市町村に迷惑を掛けたくない、できるだけ納税したい、というお気持ちがおありでしたので、「個人破産に進んだとき、配当は優先債権である税金(市税を含む)から、ということになります」とご説明したところ、
「それなら納得できる」というお答えをいただきました。
丁寧な説明が必要、と感じた局面でした。
【本日開催・セミナー】
平成26年4月16日(水)
中小企業健全化研究会様主催、弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所様後援/「特定調停の活用と経営者保証の新ガイドライン」
第一部 「税理士、弁護士など専門家向」 13:30-16:00
第二部 「経営者向」 18:00-20:30
開催要項兼申込書PDFはこちらから
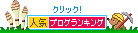
人気ブログランキングへ
このところ、ずっと経営者保証ガイドラインについて書いてきています。経営者が法人借入について差し入れている連帯保証についてはその履行について免責を受ける可能性が増しました。
しかし、依然として個人破産を選択せざるを得ない場合があります。次のような場合です。
1.法人が法的整理、準則型私的整理手続(中小企業再生支援協議会、特定調停など)をしないで単純に営業停止した場合…経営者保証ガイドラインの適用対象外、となりますので通常の手続きを経て連帯保証履行を求められます。履行できなければ個人破産を選択した方が良いケースも出てくると思います。
2.法人が、法的整理、準則型私的整理手続を行い、法人借入れの連帯保証について保証債務の免除を受けたとしても、その他の債務、住宅ローン、個人で借りたカードローンなどが返せなければ個人破産に進まざるを得ません。
3.法人に対して経営者以外の第三者が連帯保証している場合で第三者がその会社の役員など経営にタッチしていない場合は経営者保証ガイドラインの適用はありません。社外の友人や、親せきなどを連帯保証人にしている場合、夫婦で連帯保証したがその後離婚している場合など、経営者保証ガイドラインで救済するのは難しいと思われます。
昨日は1.のパターンの社長さんのご相談をお受けしました。
法人はすでに破たんし、営業停止状態になっています。
法人借入については期限の利益喪失に進んでいます。
個人破産についてご説明した中で意外な反応をいただいたのが「公租公課」でした。
地元市町村に迷惑を掛けたくない、できるだけ納税したい、というお気持ちがおありでしたので、「個人破産に進んだとき、配当は優先債権である税金(市税を含む)から、ということになります」とご説明したところ、
「それなら納得できる」というお答えをいただきました。
丁寧な説明が必要、と感じた局面でした。
【本日開催・セミナー】
平成26年4月16日(水)
中小企業健全化研究会様主催、弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所様後援/「特定調停の活用と経営者保証の新ガイドライン」
第一部 「税理士、弁護士など専門家向」 13:30-16:00
第二部 「経営者向」 18:00-20:30
開催要項兼申込書PDFはこちらから
人気ブログランキングへ
