今朝ほど出勤してしばらくしたところで、「ぷつん」と言って画面が真っ暗に。電源スイッチを押しても復旧せず。「とんじゃったか…」と思っていましたら…よく見たら電源コードが抜けていただけでした。ちょっと焦りました。
さて、経営者保証ガイドライン、このような場合に、というご説明です。
【グループに複数ある会社のうち1社が不調である】
不調な1社を切り取って特別清算なりできればよいですが、普通にやってしまうと他社と経営者が共通な時に不都合が出てきます。
その1社を処理することで経営者の個人信用情報に傷がついてしまえば、ほかの会社の借入に影響がでます。
このような場合、その1社を特定調停+経営者保証ガイドラインで処理し、他の会社に影響が及ばないようにすることができるかもしれません。
その1社が赤字体質で恒常的にグループ他社からの資金補填で生きながらえているような場合にはどこかで手を入れなければなりません。
手を入れたいが連帯保証責任が…という場合に、非常に有効な手段であると思います。
【利息の支払が経営を圧迫している】
旅館業、製造業、医業などで借入が多くなりがちな業態ですと借入が多くなるにつれ、支払利息も増えていきます。経営不振から借入が増えるパターンになりますと、金融機関側も高めの金利を提示しますしそうなるとおカネを借りられても利払い負担が重くのしかかることになります。
旅館業では、営業利益がきちんとでているのに同額かそれ以上の利払にその利益が消えてしまい、返済原資がほとんど残らない、ということが起こり得ます。
そこで債務について特定調停でカットを行い、それにつれて支払利息を減らす、という再生計画が書ければ、非常に実効性の高い、わかりやすい再生計画となると思います。
実際には、それを提示された金融機関としては、「すべてわれわれに負担を押し付けて会社は悠々と経営を続けるのか」という印象になりますので、「経営者の交替」「余剰資産の売却」「会社本体のリストラ計画」などとセットでご提案することになると思います。
借入金と連帯保証で身動きがとれなくなっている事業体としては、非常に受け入れやすい再生計画になるのではないでしょうか。
【リース会社が主要債権者である場合】
今まで金融円滑化法では、金融庁管轄の金融機関+農協、漁協が対象となっていました。今回の経営者保証ガイドラインは対象債権者をこれらの域に限定していません。
「理論上」リース会社やノンバンクも対象債権者に含め、特定調停をお願いすることは可能と思います。
ただし、金融円滑化法がでたときも、一応はリース会社などに対し、「円滑化対応の要請」がなされましたが行き届いた対応がなされたとは言えず、今回の経営者保証ガイドラインに対して、リース会社、ノンバンクがどのような対応をするかは未知数です。
しかしながら、経営に必須な資産がリース資産であるような場合、再生を目指そうとすればリース会社を避けて通るわけにはいきません。
どのようなスキームが書けるかトライする価値はあると思います。
【主債務の処理が終わっている場合】
例えば金融機関借入について、期限の利益喪失となり、保証協会の代位弁済やサービサーへの債権譲渡が完了してしまっている場合でも経営者保証ガイドラインは使うことができます。
つまり、条件を満たせば、その状況から自宅を保全したり、次の事業に着手する道筋を作るなどが可能になります。
対象債権者の範囲は非常に柔軟に設定されているのです。
以上、思いつくままに書いてみましたが、実際にどう適用していくかはご相談の中でお話を聞きながら、ということになると思います。
経営者保証ガイドラインは、早期着手ができればできるほど、守れるものが多くなります。
連帯保証責任は免除になるかもしれません。家も守れるかもしれません。まずはご相談下さい。
平成26年4月8日(火)18:30-20:30
ウイズグロウ合同会社様主催・税理士対象「経営者保証ガイドライン」セミナー
開催要項兼申込書PDFはこちらから
平成26年4月16日(水)
中小企業健全化研究会様主催、弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所様後援/「特定調停の活用と経営者保証の新ガイドライン」
第一部 「税理士、弁護士など専門家向」 13:30-16:00
第二部 「経営者向」 18:00-20:30
開催要項兼申込書PDFはこちらから
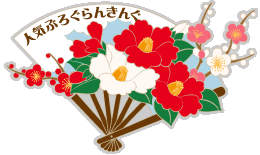
人気ブログランキングへ
さて、経営者保証ガイドライン、このような場合に、というご説明です。
【グループに複数ある会社のうち1社が不調である】
不調な1社を切り取って特別清算なりできればよいですが、普通にやってしまうと他社と経営者が共通な時に不都合が出てきます。
その1社を処理することで経営者の個人信用情報に傷がついてしまえば、ほかの会社の借入に影響がでます。
このような場合、その1社を特定調停+経営者保証ガイドラインで処理し、他の会社に影響が及ばないようにすることができるかもしれません。
その1社が赤字体質で恒常的にグループ他社からの資金補填で生きながらえているような場合にはどこかで手を入れなければなりません。
手を入れたいが連帯保証責任が…という場合に、非常に有効な手段であると思います。
【利息の支払が経営を圧迫している】
旅館業、製造業、医業などで借入が多くなりがちな業態ですと借入が多くなるにつれ、支払利息も増えていきます。経営不振から借入が増えるパターンになりますと、金融機関側も高めの金利を提示しますしそうなるとおカネを借りられても利払い負担が重くのしかかることになります。
旅館業では、営業利益がきちんとでているのに同額かそれ以上の利払にその利益が消えてしまい、返済原資がほとんど残らない、ということが起こり得ます。
そこで債務について特定調停でカットを行い、それにつれて支払利息を減らす、という再生計画が書ければ、非常に実効性の高い、わかりやすい再生計画となると思います。
実際には、それを提示された金融機関としては、「すべてわれわれに負担を押し付けて会社は悠々と経営を続けるのか」という印象になりますので、「経営者の交替」「余剰資産の売却」「会社本体のリストラ計画」などとセットでご提案することになると思います。
借入金と連帯保証で身動きがとれなくなっている事業体としては、非常に受け入れやすい再生計画になるのではないでしょうか。
【リース会社が主要債権者である場合】
今まで金融円滑化法では、金融庁管轄の金融機関+農協、漁協が対象となっていました。今回の経営者保証ガイドラインは対象債権者をこれらの域に限定していません。
「理論上」リース会社やノンバンクも対象債権者に含め、特定調停をお願いすることは可能と思います。
ただし、金融円滑化法がでたときも、一応はリース会社などに対し、「円滑化対応の要請」がなされましたが行き届いた対応がなされたとは言えず、今回の経営者保証ガイドラインに対して、リース会社、ノンバンクがどのような対応をするかは未知数です。
しかしながら、経営に必須な資産がリース資産であるような場合、再生を目指そうとすればリース会社を避けて通るわけにはいきません。
どのようなスキームが書けるかトライする価値はあると思います。
【主債務の処理が終わっている場合】
例えば金融機関借入について、期限の利益喪失となり、保証協会の代位弁済やサービサーへの債権譲渡が完了してしまっている場合でも経営者保証ガイドラインは使うことができます。
つまり、条件を満たせば、その状況から自宅を保全したり、次の事業に着手する道筋を作るなどが可能になります。
対象債権者の範囲は非常に柔軟に設定されているのです。
以上、思いつくままに書いてみましたが、実際にどう適用していくかはご相談の中でお話を聞きながら、ということになると思います。
経営者保証ガイドラインは、早期着手ができればできるほど、守れるものが多くなります。
連帯保証責任は免除になるかもしれません。家も守れるかもしれません。まずはご相談下さい。
平成26年4月8日(火)18:30-20:30
ウイズグロウ合同会社様主催・税理士対象「経営者保証ガイドライン」セミナー
開催要項兼申込書PDFはこちらから
平成26年4月16日(水)
中小企業健全化研究会様主催、弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所様後援/「特定調停の活用と経営者保証の新ガイドライン」
第一部 「税理士、弁護士など専門家向」 13:30-16:00
第二部 「経営者向」 18:00-20:30
開催要項兼申込書PDFはこちらから
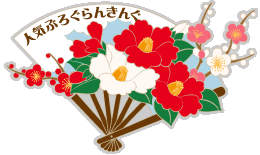
人気ブログランキングへ
