朝は鉢植えに水やり、ポットや加湿器の水を換え、洗い物があれば洗い…さて新たな1週間の始まり。
今日は粉飾決算について。
粉飾決算のあり方、というと変ですが、粉飾決算も経営者保証ガイドラインの登場で本質や対処方法が大きく変わります。
おさらいですが、条件が合致すれば、「経営者の連帯保証責任を免除する」「それに当っては個人信用情報に傷をつけない」「華美でない自宅や99万円を超える現金も残せるようにする」
という道を開き、中小企業の再生や事業承継の後押しをしよう!というのが経営者保証ガイドラインです。
経営者保証ガイドライン
経営者保証ガイドラインの中にこんなくだりがあります。
「ガイドラインに基づく保証債務の整理の対象となり得る保証人」という部分で、今回のガイドラインにより保証債務減免の対象となる保証人の条件を列挙しています。
条件はいくつかありますが、今日のテーマである、粉飾決算に関連してくるのは以下の条件です。
「主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること」
当たり前といえば当たり前です。
しかし中小企業の申告書の大半に粉飾がある、とも言われる現実を思い起こして再度、上の文章をよく見てください。
粉飾決算はどう考えても「適時適切な」情報開示とは言えません。つまり、粉飾があった、というだけで経営者保証ガイドラインの適用は難しくなるように思います。
つまり、「経営者の連帯保証責任は免除されず」「個人信用情報には事故の記録が残り」「自宅や現金は残せない」
ということになります。
銀行側からすれば、「この社長なら連帯保証責任を追及せず、早期に立ち直ってほしい」という気持ちがあればこそこの仕組みを使って後押し、という流れになるはずです。
それが、
粉飾決算を重ねていたことがわかれば虚偽の財務諸表をもとにおカネを引き出した上に、「返せない」さらには「私(経営者)の連帯保証責任も免除して欲しい」と言われるわけですから、
「ちょっと待って」「それはないでしょう」という気持ちになるのは当然のことと思います。
ただし、救いの道は、早期に民事再生へ進むなどの判断をした結果、単純に破産を迎えるより返済額が増加した、という事実を作れれば経営者保証ガイドライン適用の可能性は残ります。
以上のことを考え合せる、粉飾決算をするタイミング、が変わるように思います。
今までは会社を潰したくない⇒お金は必要⇒(やむを得ず)粉飾決算へ、という流れ(思考)でしがた、これからは、
業績がマズイ⇒粉飾をしないでそのまま金融機関にディスクローズ⇒条件変更などで対処できる範囲ならそれで対処⇒重症なら経営者保証ガイドラインを使って早期に次のスタートを切る、というのが正解になるように思います。
それでは今、決算に粉飾がある企業はどうなるでしょうか。
自力再生が可能かどうかなどチェックするポイントはいくつかありますが、そのまま粉飾決算を重ねてもいいことは何もありません。最終的にはどこかで行き詰まりますので、先に書いたような、
「円滑化対応による条件変更」
「会社を整理または債務カットを行い経営者保証ガイドラインの適用を受けて再生へ」
のどちらかを選択せざるを得ないと思います。
経営者保証ガイドラインが出ている以上、それを利用して軟着陸をすることをまずは検討するべきかと思います。
以前にもこのブログに書きましたが、私個人的には粉飾決算をしたあと、再生にこぎつけた企業は1社を除き見たことがありません。
粉飾をした後正常化するのはいばらの道です。
「これから粉飾をするかどうかというところに立っている企業さんなら『しない』というのも選択肢」(経営者保証ガイドラインの適用を受ける)
「粉飾をしてしまっている企業は、どのような対処が必要か要検討(粉飾の程度、企業の体力、などで進むべき道のりが変わります)」
ということになるのではないでしょうか。
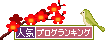
人気ブログランキングへ
今日は粉飾決算について。
粉飾決算のあり方、というと変ですが、粉飾決算も経営者保証ガイドラインの登場で本質や対処方法が大きく変わります。
おさらいですが、条件が合致すれば、「経営者の連帯保証責任を免除する」「それに当っては個人信用情報に傷をつけない」「華美でない自宅や99万円を超える現金も残せるようにする」
という道を開き、中小企業の再生や事業承継の後押しをしよう!というのが経営者保証ガイドラインです。
経営者保証ガイドライン
経営者保証ガイドラインの中にこんなくだりがあります。
「ガイドラインに基づく保証債務の整理の対象となり得る保証人」という部分で、今回のガイドラインにより保証債務減免の対象となる保証人の条件を列挙しています。
条件はいくつかありますが、今日のテーマである、粉飾決算に関連してくるのは以下の条件です。
「主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む。)について適時適切に開示していること」
当たり前といえば当たり前です。
しかし中小企業の申告書の大半に粉飾がある、とも言われる現実を思い起こして再度、上の文章をよく見てください。
粉飾決算はどう考えても「適時適切な」情報開示とは言えません。つまり、粉飾があった、というだけで経営者保証ガイドラインの適用は難しくなるように思います。
つまり、「経営者の連帯保証責任は免除されず」「個人信用情報には事故の記録が残り」「自宅や現金は残せない」
ということになります。
銀行側からすれば、「この社長なら連帯保証責任を追及せず、早期に立ち直ってほしい」という気持ちがあればこそこの仕組みを使って後押し、という流れになるはずです。
それが、
粉飾決算を重ねていたことがわかれば虚偽の財務諸表をもとにおカネを引き出した上に、「返せない」さらには「私(経営者)の連帯保証責任も免除して欲しい」と言われるわけですから、
「ちょっと待って」「それはないでしょう」という気持ちになるのは当然のことと思います。
ただし、救いの道は、早期に民事再生へ進むなどの判断をした結果、単純に破産を迎えるより返済額が増加した、という事実を作れれば経営者保証ガイドライン適用の可能性は残ります。
以上のことを考え合せる、粉飾決算をするタイミング、が変わるように思います。
今までは会社を潰したくない⇒お金は必要⇒(やむを得ず)粉飾決算へ、という流れ(思考)でしがた、これからは、
業績がマズイ⇒粉飾をしないでそのまま金融機関にディスクローズ⇒条件変更などで対処できる範囲ならそれで対処⇒重症なら経営者保証ガイドラインを使って早期に次のスタートを切る、というのが正解になるように思います。
それでは今、決算に粉飾がある企業はどうなるでしょうか。
自力再生が可能かどうかなどチェックするポイントはいくつかありますが、そのまま粉飾決算を重ねてもいいことは何もありません。最終的にはどこかで行き詰まりますので、先に書いたような、
「円滑化対応による条件変更」
「会社を整理または債務カットを行い経営者保証ガイドラインの適用を受けて再生へ」
のどちらかを選択せざるを得ないと思います。
経営者保証ガイドラインが出ている以上、それを利用して軟着陸をすることをまずは検討するべきかと思います。
以前にもこのブログに書きましたが、私個人的には粉飾決算をしたあと、再生にこぎつけた企業は1社を除き見たことがありません。
粉飾をした後正常化するのはいばらの道です。
「これから粉飾をするかどうかというところに立っている企業さんなら『しない』というのも選択肢」(経営者保証ガイドラインの適用を受ける)
「粉飾をしてしまっている企業は、どのような対処が必要か要検討(粉飾の程度、企業の体力、などで進むべき道のりが変わります)」
ということになるのではないでしょうか。
人気ブログランキングへ
