週末までとっちらかっていた机上、ようやく一段落です。机の上がTODOリスト、という考えですので仕事がたまる=机が散らかる、ということになります。
実質一人の会社ですので電話応対、現金出納、ファックス送信やらいろいろな業務が押し寄せてきます。月、火でたまっていたものがだいぶ片付いたのでここから攻めに。
さて、先日来何度も取り上げていますが、経営者保証ガイドライン(以下GL)についてです。
特定調停制度の改革とセット、ということでGLの運用開始、2月1日がまじかに迫っています。
政府はこれで何を進めたいのか?を考えますと…
1.特定調停制度の柔軟運用により債務のカットを実現することで事業再生を進めたい。
2.また何が何でも事業再生、ということではなく、実質的に破たんしている会社であれば清算型の特定調停を行う。
3.上記1,2ともGLと組み合わせることで早期着手の判断を経営者に促す。以前の記事(「経営者保証GL・免除の根拠」)で書きましたが、現金をより多く持ったり、持ち家を保全した状態で連帯保証を免除する根拠は、「経営者が早期にメスを入れる判断をしたことで金融機関の回収額が増加した」、です。
背景には円滑化法とそれに先立つ特別保証制度により、本来つぶれているはずの中小企業が多数残っているものを整理したい、という意向があるように思います。破たんしている企業の整理については金融機関側も進めたいと思っているはずです。円滑化法(円滑化対応)があるがために正常先に不良債権が混じっている形になっているのは事実です。
と、ここまでは政府と金融機関の目線から。
経営者からはこの新制度はどう映るでしょう?
「再生をしたい、そのためには一定額の債権をカットしたい」と考えている経営者がいたとして、既存の仕組みと比べてみます。
1.対民事再生法 …民事再生法の方がコストが高い(予納金、弁護士費用合わせて1,000万円から上になります)。また再生計画認可にこぎつけるまでにいろいろなリスクがある。(スポンサーがつくか、手続き中に資金ショートを起こさないか、別除権協定を結べるか、など…再生計画認可まで行きつけなければ結局破産へ移行してしまう。また債権カットは金融機関だけでなく仕入れ先にも及ぶので事業継続できるかどうかリスクが付きまとう。
2.対中小企業再生支援協議会 …カットを含むスキームだと1年近く時間がかかること、第三者のデューデリジェンスが求められるためその費用がかかります。
もちろん、特定調停でも弁護士費用や裁判所の費用は掛かってきますし必要に応じてデューデリジェンスも行うことになるでしょう。しかし、道内の事情を見ますと、民事再生法や中小企業再生支援協議会を利用する企業規模は小型化してきており、もう一息、使いやすく短期間で終了する仕組みがあれば経営者にとって選択の幅が広がることは間違いありません。しかも連帯保証責任までカットできるとすれば…
経営者側にニーズが発生するのは、特定調停の再生型の方ではないでしょうか。
会社が継続し自らの連帯保証責任も免除(あるいは特定調停を機に債務をカットして事業承継しやすくする)ということで再生は一気に加速することになるでしょう。
問題は、金融機関の納得する再生スキームを提示できるかどうか、ということになります。
そこで…再生コンサルタントの出番、ということになると思いますがいかがでしょう。
弁護士会では、「弁護士に再生型の特定調停は荷が重い。清算型で会社をなくす方向なら」という議論もあるようですが顧客(経営者)のニーズは間違いなく再生型にあると思います。
すくなくとも、今弊社で仕掛になっている事案についてはすべて特定調停+経営者保証GLでスキームを練り直してみることにします。このスキームが中小企業の事業再生の大きなブレイクスルーになるでしょう。
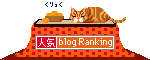
人気ブログランキングへ
4.
実質一人の会社ですので電話応対、現金出納、ファックス送信やらいろいろな業務が押し寄せてきます。月、火でたまっていたものがだいぶ片付いたのでここから攻めに。
さて、先日来何度も取り上げていますが、経営者保証ガイドライン(以下GL)についてです。
特定調停制度の改革とセット、ということでGLの運用開始、2月1日がまじかに迫っています。
政府はこれで何を進めたいのか?を考えますと…
1.特定調停制度の柔軟運用により債務のカットを実現することで事業再生を進めたい。
2.また何が何でも事業再生、ということではなく、実質的に破たんしている会社であれば清算型の特定調停を行う。
3.上記1,2ともGLと組み合わせることで早期着手の判断を経営者に促す。以前の記事(「経営者保証GL・免除の根拠」)で書きましたが、現金をより多く持ったり、持ち家を保全した状態で連帯保証を免除する根拠は、「経営者が早期にメスを入れる判断をしたことで金融機関の回収額が増加した」、です。
背景には円滑化法とそれに先立つ特別保証制度により、本来つぶれているはずの中小企業が多数残っているものを整理したい、という意向があるように思います。破たんしている企業の整理については金融機関側も進めたいと思っているはずです。円滑化法(円滑化対応)があるがために正常先に不良債権が混じっている形になっているのは事実です。
と、ここまでは政府と金融機関の目線から。
経営者からはこの新制度はどう映るでしょう?
「再生をしたい、そのためには一定額の債権をカットしたい」と考えている経営者がいたとして、既存の仕組みと比べてみます。
1.対民事再生法 …民事再生法の方がコストが高い(予納金、弁護士費用合わせて1,000万円から上になります)。また再生計画認可にこぎつけるまでにいろいろなリスクがある。(スポンサーがつくか、手続き中に資金ショートを起こさないか、別除権協定を結べるか、など…再生計画認可まで行きつけなければ結局破産へ移行してしまう。また債権カットは金融機関だけでなく仕入れ先にも及ぶので事業継続できるかどうかリスクが付きまとう。
2.対中小企業再生支援協議会 …カットを含むスキームだと1年近く時間がかかること、第三者のデューデリジェンスが求められるためその費用がかかります。
もちろん、特定調停でも弁護士費用や裁判所の費用は掛かってきますし必要に応じてデューデリジェンスも行うことになるでしょう。しかし、道内の事情を見ますと、民事再生法や中小企業再生支援協議会を利用する企業規模は小型化してきており、もう一息、使いやすく短期間で終了する仕組みがあれば経営者にとって選択の幅が広がることは間違いありません。しかも連帯保証責任までカットできるとすれば…
経営者側にニーズが発生するのは、特定調停の再生型の方ではないでしょうか。
会社が継続し自らの連帯保証責任も免除(あるいは特定調停を機に債務をカットして事業承継しやすくする)ということで再生は一気に加速することになるでしょう。
問題は、金融機関の納得する再生スキームを提示できるかどうか、ということになります。
そこで…再生コンサルタントの出番、ということになると思いますがいかがでしょう。
弁護士会では、「弁護士に再生型の特定調停は荷が重い。清算型で会社をなくす方向なら」という議論もあるようですが顧客(経営者)のニーズは間違いなく再生型にあると思います。
すくなくとも、今弊社で仕掛になっている事案についてはすべて特定調停+経営者保証GLでスキームを練り直してみることにします。このスキームが中小企業の事業再生の大きなブレイクスルーになるでしょう。
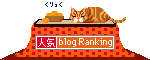
人気ブログランキングへ
4.
