クリスマスまで入り口を飾ってくれたポインセチア。さすがに葉が落ちてきました。
さて、「破産」のお話です。
法人の商売を温存するなら「民事再生」、と誰もが思います。法人格が消滅してしまう破産よりも法人格がそのまま残る民事再生の方が名前からいっても再生向きのような気がします。
しかし、民事再生ならでは、とうデメリットもあります。
札幌地裁においてはスポンサー付の民事再生が一般化してきており、まずスポンサーがついてくれるのか?という論点が出てきます。最悪、「民事再生法の手続きの中でスポンサーを募る」というスキームも成り立つかもしれませんが確実に開始決定されるということでもありませんん。
一方スポンサー側からいうと、開始決定前に資金ショートが起きたり予納金や弁護士費用を払えない、ということになるとスポンサーが立て替えなければなりません。それらは再生債権として民事再生法の中でカット対象になる可能性が高いため、まず、
「いくら出す?」という質問をつきつけられることになります。
そして説得力のある再生計画を出せるかどうか…
上記の通り、申立をするまで相当な準備が必要になります。
一方、言葉はきついですが破産はどうでしょうか。
事業を引き継ぐ、ということであれば、破産申し立て⇒換価のなかで事業を継続、という目もなくはありません。管財人にすれば事業ごと換価できればそれぞればら売りしなくてもよくなりますし明らかに配当額は増えると思います。また、事業を引き取る側とすれば裁判所をくぐったものを買うわけで将来、思わぬ見逃し事項が明らかになり追加費用発生、ということもなくなります。
また、
複数店舗を展開している会社なら、「3店舗は●●社へ」「5店舗は△△社へ」という分け方もできると思います。パターンによっては民事再生法よりも柔軟に、かつ似たような効果(事業の温存)ができるかもしれません。
再生に置いては何事も決めつけをせず、柔軟に対応することがキモ、となります。
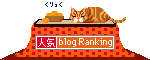
人気ブログランキングへ
さて、「破産」のお話です。
法人の商売を温存するなら「民事再生」、と誰もが思います。法人格が消滅してしまう破産よりも法人格がそのまま残る民事再生の方が名前からいっても再生向きのような気がします。
しかし、民事再生ならでは、とうデメリットもあります。
札幌地裁においてはスポンサー付の民事再生が一般化してきており、まずスポンサーがついてくれるのか?という論点が出てきます。最悪、「民事再生法の手続きの中でスポンサーを募る」というスキームも成り立つかもしれませんが確実に開始決定されるということでもありませんん。
一方スポンサー側からいうと、開始決定前に資金ショートが起きたり予納金や弁護士費用を払えない、ということになるとスポンサーが立て替えなければなりません。それらは再生債権として民事再生法の中でカット対象になる可能性が高いため、まず、
「いくら出す?」という質問をつきつけられることになります。
そして説得力のある再生計画を出せるかどうか…
上記の通り、申立をするまで相当な準備が必要になります。
一方、言葉はきついですが破産はどうでしょうか。
事業を引き継ぐ、ということであれば、破産申し立て⇒換価のなかで事業を継続、という目もなくはありません。管財人にすれば事業ごと換価できればそれぞればら売りしなくてもよくなりますし明らかに配当額は増えると思います。また、事業を引き取る側とすれば裁判所をくぐったものを買うわけで将来、思わぬ見逃し事項が明らかになり追加費用発生、ということもなくなります。
また、
複数店舗を展開している会社なら、「3店舗は●●社へ」「5店舗は△△社へ」という分け方もできると思います。パターンによっては民事再生法よりも柔軟に、かつ似たような効果(事業の温存)ができるかもしれません。
再生に置いては何事も決めつけをせず、柔軟に対応することがキモ、となります。
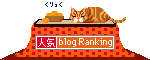
人気ブログランキングへ
