iPhoneにkindleアプリを入れて電子書籍を読んで見ました。画面が小さいのでページをめくる感覚がピンときませんが、すぐダウンロードで来てどこでも読めるのは便利です。保管場所も気にしなくていいし。
金融円滑化法がなくなったあとも、「円滑化対応」は残っています。金融円滑化法の有無にかかわらず、返済が苦しくなった場合、条件変更を通じて正常化を支援する仕組みは残りました。
さて、条件変更を金融機関に要請する理由はただ一つ。「資金が苦しいから」です。
金融機関に条件変更を要請するまでに、企業側はいろいろやりくりしようとします。
経営者をはじめ役員からの一時借入。
遊休資産の売却。
など。
当然社内のコストカットも進めます。
その一環として、公租公課に未払いを作るケースがあります。
公租公課は、
①法人税・所得税など所得にかかる税、
②消費税・源泉所得税など預かって払う方式の税、
③社会保険料は半分社員さんの負担を預り会社負担分を上乗せして支払、
④固定資産税などその他のタイプ、に大別できます。
①は所得がなければ(赤字なら)基本的にかかりません。
問題は②-④です。
消費税は赤字なら発生額は少なくなりますが消費税がなくなるまでとなると会社としてやっていけない額の赤字発生、ということになります。逆に言うと業背kが少々の赤字でも消費税納税は発生することになります。余談ですが来年消費税が引き上げられますが、5⇒8%へ、3%のアップという認識は誤りで、実際は、8÷5=160%の税負担増と認識するべきです。
源泉所得税も天引きして支払う、というものですので業績によって納税義務がなくなるものではありません。
この二つの税について未納を作りますと「預かったものを納税せず、会社の資金繰りに使った」として厳しく追及されます。
また、固定資産税や事業所税なども業績に係わらず発生しますので資金繰りが厳しくなるとついつい未納を作りがちです。
基本的にこれらの税金については未納が発生しても『年度内に解消を』というのがそれぞれの徴収庁の姿勢です。
ここからが条件変更との係わりあいになりますが、
1.条件変更により資金が回っていく、というストーリーが書けないケースがある 先に述べた、年度内に未納解消を織り込んで資金繰りを組むと銀行返済を止めても資金が回らないとうことになりかねない。
2.公租公課の未納がある場合、条件変更を通すには、①未納金額の明細、②それぞれの課税庁とどのような納付の打ち合わせをしているか(毎月○○万円ずつ、納付など)、③未納分の領収証提出が条件になりつつあります。(保証協会が要求する、とのこと)
3.条件変更を継続する場合、2.との兼ね合いになりますが、前回の条件変更時より未納金が減っているかどうかも見られます。
納税証明書を添付、というところまでは来ていませんが公租公課の未納がある状態でそれを隠して条件変更を行うのは困難、と言えます。
金融機関や保証協会が公租公課の未納にナーバスになるのは、放置すれば徴収庁からの差押を受けることになるからです。金銭消費貸借約定書の期限の利益喪失条項にも該当しますし、金融機関からすれば預金を差押さえられたような場合は目の前で会社の資金繰りと信用が崩壊するのを見せつけられることになるからです。
公租公課の未納については、
「未納を作らない」…未納が発生しそうなら金融機関に条件変更を要請する
のが正解と言えると思います。その方が金融機関としても安心して条件変更による再生支援に進める、というのが実態と思います。
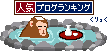
人気ブログランキングへ
金融円滑化法がなくなったあとも、「円滑化対応」は残っています。金融円滑化法の有無にかかわらず、返済が苦しくなった場合、条件変更を通じて正常化を支援する仕組みは残りました。
さて、条件変更を金融機関に要請する理由はただ一つ。「資金が苦しいから」です。
金融機関に条件変更を要請するまでに、企業側はいろいろやりくりしようとします。
経営者をはじめ役員からの一時借入。
遊休資産の売却。
など。
当然社内のコストカットも進めます。
その一環として、公租公課に未払いを作るケースがあります。
公租公課は、
①法人税・所得税など所得にかかる税、
②消費税・源泉所得税など預かって払う方式の税、
③社会保険料は半分社員さんの負担を預り会社負担分を上乗せして支払、
④固定資産税などその他のタイプ、に大別できます。
①は所得がなければ(赤字なら)基本的にかかりません。
問題は②-④です。
消費税は赤字なら発生額は少なくなりますが消費税がなくなるまでとなると会社としてやっていけない額の赤字発生、ということになります。逆に言うと業背kが少々の赤字でも消費税納税は発生することになります。余談ですが来年消費税が引き上げられますが、5⇒8%へ、3%のアップという認識は誤りで、実際は、8÷5=160%の税負担増と認識するべきです。
源泉所得税も天引きして支払う、というものですので業績によって納税義務がなくなるものではありません。
この二つの税について未納を作りますと「預かったものを納税せず、会社の資金繰りに使った」として厳しく追及されます。
また、固定資産税や事業所税なども業績に係わらず発生しますので資金繰りが厳しくなるとついつい未納を作りがちです。
基本的にこれらの税金については未納が発生しても『年度内に解消を』というのがそれぞれの徴収庁の姿勢です。
ここからが条件変更との係わりあいになりますが、
1.条件変更により資金が回っていく、というストーリーが書けないケースがある 先に述べた、年度内に未納解消を織り込んで資金繰りを組むと銀行返済を止めても資金が回らないとうことになりかねない。
2.公租公課の未納がある場合、条件変更を通すには、①未納金額の明細、②それぞれの課税庁とどのような納付の打ち合わせをしているか(毎月○○万円ずつ、納付など)、③未納分の領収証提出が条件になりつつあります。(保証協会が要求する、とのこと)
3.条件変更を継続する場合、2.との兼ね合いになりますが、前回の条件変更時より未納金が減っているかどうかも見られます。
納税証明書を添付、というところまでは来ていませんが公租公課の未納がある状態でそれを隠して条件変更を行うのは困難、と言えます。
金融機関や保証協会が公租公課の未納にナーバスになるのは、放置すれば徴収庁からの差押を受けることになるからです。金銭消費貸借約定書の期限の利益喪失条項にも該当しますし、金融機関からすれば預金を差押さえられたような場合は目の前で会社の資金繰りと信用が崩壊するのを見せつけられることになるからです。
公租公課の未納については、
「未納を作らない」…未納が発生しそうなら金融機関に条件変更を要請する
のが正解と言えると思います。その方が金融機関としても安心して条件変更による再生支援に進める、というのが実態と思います。
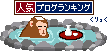
人気ブログランキングへ
