昨夕通りかかった博多駅で。めんたいこ、のゆるキャラだそうです。くまもんを超えられるか…??
金融円滑化法の期限切れを前に改めて条件変更でよく受ける質問をもとに基本事項をまとめてみました。
1.「条件変更を申し込んだが『来月の返済分からですね』と言われた」
銀行側は、「条件変更の審議」⇒「本店の承認」⇒「条件変更適用開始(元金返済猶予など)」という手順を踏みたいと思っているのだと思います。これでいくと延滞が出ない形ですので銀行としてはスッキリすると思います。
とはいえ、条件変更をお願いするのは資金繰りが苦しいから、に決まっていますので、「手続きに時間がかかるのはわかりますが資金繰り上、今月の返済から残不足になり返済が止まります」と通告するケースはよく見ます。
その場合、1-2回延滞が発生したあと、条件変更の調印(その時にそこまでの未収利息の清算を行う)というように進んでいきます。
2.「条件変更を申し込んでいるのにもかかわらず約定返済金額分の引き落としがあった」
銀行によりますが、条件変更の申し出を受けただけでは特段なにもせず、引き落とし指定がかかったままにしておく金融機関があります。返済日に残高があると引き落としされてしまいます。
また、返済日に残高を落としておくなどして返済がないようにしても、その後売掛金の回収が入ったなど一瞬でも回収金額を超える残があるとすとんと引き落としになることがあります。
条件変更申し入れ時には、「引き落とし指定も解除して欲しい、残が入っても落ちないようにして欲しい」とちゃんと表明することが必要です。
万が一引き落としがあった場合には、「当社として予定外の引き落としであり、落ちないようにしてくれ、と申し入れているのだから戻してほしい」と折衝すべきです。
経験則でいうと、政府系金融機関の引き落としが戻ったケースは複数みましたし、メガバンクがプロパー貸の引き落としをしてしまったものを返金してくれたケースもありました。
一方で、「あー、落ちちゃったものはしょうがないですねぇ」「ルール上返金はできないんですよ」など返金に応じない(応じる気が最初からない)金融機関もありますので十分注意が必要です。
3.「条件変更の許容期間が終了したら元の約定返済に戻った。そんなものなのか?」
そんなもの、です。
条件変更は銀行にとって異例な対処になります。いったん決めた返済スケジュールを変更するわけですから…
銀行の認識としては、「(異例の措置で)条件変更に応じた」⇒「その(異例な)期間が終了したのだから元に戻るのは当たり前でしょ?」となります。
しかし、条件変更で元金返済を止めてたあと、すぐ元の約定に戻せる会社はごく一部です。したがって条件変更期間が終わる前に、
「次も元金返済猶予を」または「返せたとしてもここまでしか」という申し入れをきちんと銀行側にしておくことです。銀行側も膨大な件数の条件変更に応じていますので、手抜き、ということではないですが、「何も言ってこないから元に戻っておしまいね」という対応があっても不思議ではありません。
3.「条件変更のデメリットは?」
新規融資を受けるのが難しくなります。この部分については、コストカットや売り上げ増強につながる融資であれば「積極的に対処せよ」という金融庁指針が出ているものの、現実的に新規融資を引き出すのは簡単ではありません。少なくとも、「条件変更を受けるだけではキャッシュが不足するのでその分を貸して欲しい」など安易な理由ではおカネは出ないと思います。
銀行がもし貸すとすれば、そのことで自行の貸付の回収可能性が上がるとき、ということになります。例としては、毎年季節的に資金不足になる時期がありそこをつながないと経営改善もへったくれもない、というような状況が考えられます。あるいはリストラ費用ですとか…
ここの部分は見極めが必要で、
すでに取引金融機関から「もうおカネはでません」と言われているのなら新規融資に期待するだけ無駄で条件変更を受けることで確実におカネを浮かせたほうが良い、という判断もできると思います。
4.「借りたばかりだが資金ショートを起こす見込みになった。条件変更はできるのか?」
結論としては、「条件変更を勝ち取るしか生きる道がない以上、全力で交渉する」。
金融機関側は、「出したばかりなのに」「出した時の審議では十分返せる、という話だったのにウソを言ったのか」さらには、
「資金がショートするのが解っていて融資を引き出したのか?」という理解になりますので面白いはずはありません。
状況が変わったことなどきちんと何度でも説明し頭を下げ、条件変更に応じてもらうことが必要です。
5.全般的な注意事項
①返済回数をそろえること A行は8月から止めたがB行は9月から、というようなでこぼこを作らない。「公平性」が重要です。
②同じ理由で残高シェアで返済額を計算していきます。不動産担保の有無を計算に入れる、「信用プロラタ」も一時適用されたことがありますが「計算が複雑」「不動産の公正な評価が難しい」ということで今は残高プロラタで計算するケースがほとんどです。
③各銀行同じ資料を同じ時期に出す 情報の格差も作らない
④万が一粉飾があるときには 条件変更の申し入れ時にその旨をきちんと伝える 粉飾を隠しながら条件変更をしていくのはムリです。粉飾はいつかどこかで告白しなければなりません。条件変更を受けないと会社がつぶれる、という状況なら選択の余地はなく、粉飾はしていましたが条件変更はしてください、会社を生かしてください、と金融機関にお願いするしなないのではないでしょうか。
銀行側も「だましていたな」ということで態度は硬化すると思います。こちら側の誠意、熱意が伝わるかどうかがポイントになります。
↓ぽちっと一押しお願いします。
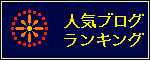
人気ブログランキングへ
金融円滑化法の期限切れを前に改めて条件変更でよく受ける質問をもとに基本事項をまとめてみました。
1.「条件変更を申し込んだが『来月の返済分からですね』と言われた」
銀行側は、「条件変更の審議」⇒「本店の承認」⇒「条件変更適用開始(元金返済猶予など)」という手順を踏みたいと思っているのだと思います。これでいくと延滞が出ない形ですので銀行としてはスッキリすると思います。
とはいえ、条件変更をお願いするのは資金繰りが苦しいから、に決まっていますので、「手続きに時間がかかるのはわかりますが資金繰り上、今月の返済から残不足になり返済が止まります」と通告するケースはよく見ます。
その場合、1-2回延滞が発生したあと、条件変更の調印(その時にそこまでの未収利息の清算を行う)というように進んでいきます。
2.「条件変更を申し込んでいるのにもかかわらず約定返済金額分の引き落としがあった」
銀行によりますが、条件変更の申し出を受けただけでは特段なにもせず、引き落とし指定がかかったままにしておく金融機関があります。返済日に残高があると引き落としされてしまいます。
また、返済日に残高を落としておくなどして返済がないようにしても、その後売掛金の回収が入ったなど一瞬でも回収金額を超える残があるとすとんと引き落としになることがあります。
条件変更申し入れ時には、「引き落とし指定も解除して欲しい、残が入っても落ちないようにして欲しい」とちゃんと表明することが必要です。
万が一引き落としがあった場合には、「当社として予定外の引き落としであり、落ちないようにしてくれ、と申し入れているのだから戻してほしい」と折衝すべきです。
経験則でいうと、政府系金融機関の引き落としが戻ったケースは複数みましたし、メガバンクがプロパー貸の引き落としをしてしまったものを返金してくれたケースもありました。
一方で、「あー、落ちちゃったものはしょうがないですねぇ」「ルール上返金はできないんですよ」など返金に応じない(応じる気が最初からない)金融機関もありますので十分注意が必要です。
3.「条件変更の許容期間が終了したら元の約定返済に戻った。そんなものなのか?」
そんなもの、です。
条件変更は銀行にとって異例な対処になります。いったん決めた返済スケジュールを変更するわけですから…
銀行の認識としては、「(異例の措置で)条件変更に応じた」⇒「その(異例な)期間が終了したのだから元に戻るのは当たり前でしょ?」となります。
しかし、条件変更で元金返済を止めてたあと、すぐ元の約定に戻せる会社はごく一部です。したがって条件変更期間が終わる前に、
「次も元金返済猶予を」または「返せたとしてもここまでしか」という申し入れをきちんと銀行側にしておくことです。銀行側も膨大な件数の条件変更に応じていますので、手抜き、ということではないですが、「何も言ってこないから元に戻っておしまいね」という対応があっても不思議ではありません。
3.「条件変更のデメリットは?」
新規融資を受けるのが難しくなります。この部分については、コストカットや売り上げ増強につながる融資であれば「積極的に対処せよ」という金融庁指針が出ているものの、現実的に新規融資を引き出すのは簡単ではありません。少なくとも、「条件変更を受けるだけではキャッシュが不足するのでその分を貸して欲しい」など安易な理由ではおカネは出ないと思います。
銀行がもし貸すとすれば、そのことで自行の貸付の回収可能性が上がるとき、ということになります。例としては、毎年季節的に資金不足になる時期がありそこをつながないと経営改善もへったくれもない、というような状況が考えられます。あるいはリストラ費用ですとか…
ここの部分は見極めが必要で、
すでに取引金融機関から「もうおカネはでません」と言われているのなら新規融資に期待するだけ無駄で条件変更を受けることで確実におカネを浮かせたほうが良い、という判断もできると思います。
4.「借りたばかりだが資金ショートを起こす見込みになった。条件変更はできるのか?」
結論としては、「条件変更を勝ち取るしか生きる道がない以上、全力で交渉する」。
金融機関側は、「出したばかりなのに」「出した時の審議では十分返せる、という話だったのにウソを言ったのか」さらには、
「資金がショートするのが解っていて融資を引き出したのか?」という理解になりますので面白いはずはありません。
状況が変わったことなどきちんと何度でも説明し頭を下げ、条件変更に応じてもらうことが必要です。
5.全般的な注意事項
①返済回数をそろえること A行は8月から止めたがB行は9月から、というようなでこぼこを作らない。「公平性」が重要です。
②同じ理由で残高シェアで返済額を計算していきます。不動産担保の有無を計算に入れる、「信用プロラタ」も一時適用されたことがありますが「計算が複雑」「不動産の公正な評価が難しい」ということで今は残高プロラタで計算するケースがほとんどです。
③各銀行同じ資料を同じ時期に出す 情報の格差も作らない
④万が一粉飾があるときには 条件変更の申し入れ時にその旨をきちんと伝える 粉飾を隠しながら条件変更をしていくのはムリです。粉飾はいつかどこかで告白しなければなりません。条件変更を受けないと会社がつぶれる、という状況なら選択の余地はなく、粉飾はしていましたが条件変更はしてください、会社を生かしてください、と金融機関にお願いするしなないのではないでしょうか。
銀行側も「だましていたな」ということで態度は硬化すると思います。こちら側の誠意、熱意が伝わるかどうかがポイントになります。
↓ぽちっと一押しお願いします。
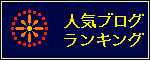
人気ブログランキングへ
