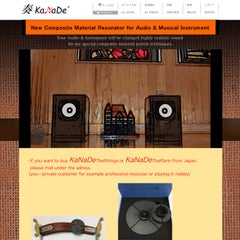先日の続きにもなるのですが、ネットサーフィンしていますと、未だにスピーカーの防振にゴムを使いなさい、というオタク?の推奨文句がみられます。
非常に残念なことで、筆者らはインシュレーターの作用を①振動減衰、しか理解されていないのです。
いつも言うように、インシュレーターには②共振増音、の作用もあることを、ご存じないわけです。
共振増音がなければ、きっとブレーキ鳴きで33年も苦労することはなかったでしょう。
間違った教えの1つが、「スピーカーの振動を床に伝えなくしましょう。防振と音質は両立しないため、ゴムでスピーカーの揺れを抑えましょう。」という考え。
この教えの間違いは2つありますね。
1つは、スピーカーはユニットとエンクロージャーが一緒に振動して音質を決めていますから、エンクロージャーの揺れを止めてしまったら、設計した音質にならなくなります。
(だから、一緒に振動するKaNaDeを作ったわけで。)
2つは、何度も言いますが、ゴムは粘弾性体のため非線形に伸び縮みしますから、スピーカーの重心が前寄りになっているために前がやたら沈み込みます。
でんじろう先生のゴム測りの解説がわかりやすいです。
なので、前側のゴムは薄くなり、後ろ側のゴムは厚く。
つまり、前側は高い周波数、後ろ側は低い周波数とズレてしまうわけです。
実はこの厚み変化でゴムはもう一つ、問題が起こります。
ポアソン比、というのをご存じないようで。
やはり、その筆者は有限要素法解析を知らない。
(計算に必ず必要な係数)
ポアソン比とは、物資を圧縮したり引っ張ったりしたときの体積変化率を表す係数で、計測して 0〜0.5まで割り振ってます。
(0は体積変化大、0.5は体積変化なし)
通常の物資は0.25〜0.3の間にありますが、ゴムは0.49と全く体積変化しない物資なのです。
つまり、戻りますと、スピーカーの前側はゴムの面積が広く広がり、後ろ側は面積が狭いわけです。
面積と共振音圧は比例しますから。
防振と音質は両立しない、ではなく、両立させる手法を解説しなければ意味がありません。
両立させるには、粘弾性体だけではダメで弾性体と組み合わせる必要があるわけです。
それが、以前からあるハイブリッドインシュレーターであり、それを進化させたのが複合材インシュレーターKaNaDeなので。
また、ゴムといっても、
天然ゴム(イソプレン)
ニトリルゴム
ニトリルブタジエンゴム
エピクロルヒドレンゴム
シリコンゴム
アクリルゴム
フッ素ゴム
ウレタンゴム
など、数多く開発されていて、それぞれ物性が異なります。
なので、ゴムを使いましょう、と、どれを選べば良いかまで解説してもらわないと。
少しは、教科書を紐解いて解説してもらいたいところです。
特にyoutuberともなりますと、それで稼いでいますから異論には反応しないです。
音もだちも言ってますが。
自分の知っている情報や計測だけで結論まで述べてしまう不勉強者なので。
50万円のアンプを100円のインシュレーターで振動処理する?から疑問を持つ思考が必要です。
それに、ゴムを敷いて音が良いと言っている耳は参考になりません。
うんちくの前に、生の音楽演奏を聴くべきです。
また、続きます。
- 【1m~カット販売】日本製 綿平袋ひも 並打 サイズ(約10mm) カラー #31黒Amazon(アマゾン)2mm単線スピーカーケーブルの静電気対策に使用します。➕➖は依らずにバラで使うと更にクリアになります。
- LATINAAmazon(アマゾン)デジタル録音機器にKaNaDeが使用された、高音質のラテン音楽です。
- time - 10Amazon(アマゾン)until you sayがボケずにちゃんと再生出来ますか? オーディオマニアが熱くなるほどのチャレンジ課題です。
- ナイト・グロウAmazon(アマゾン)田中真由美の新しいアルバム。 Quietudeに引き続く高音質で、おすすめです。