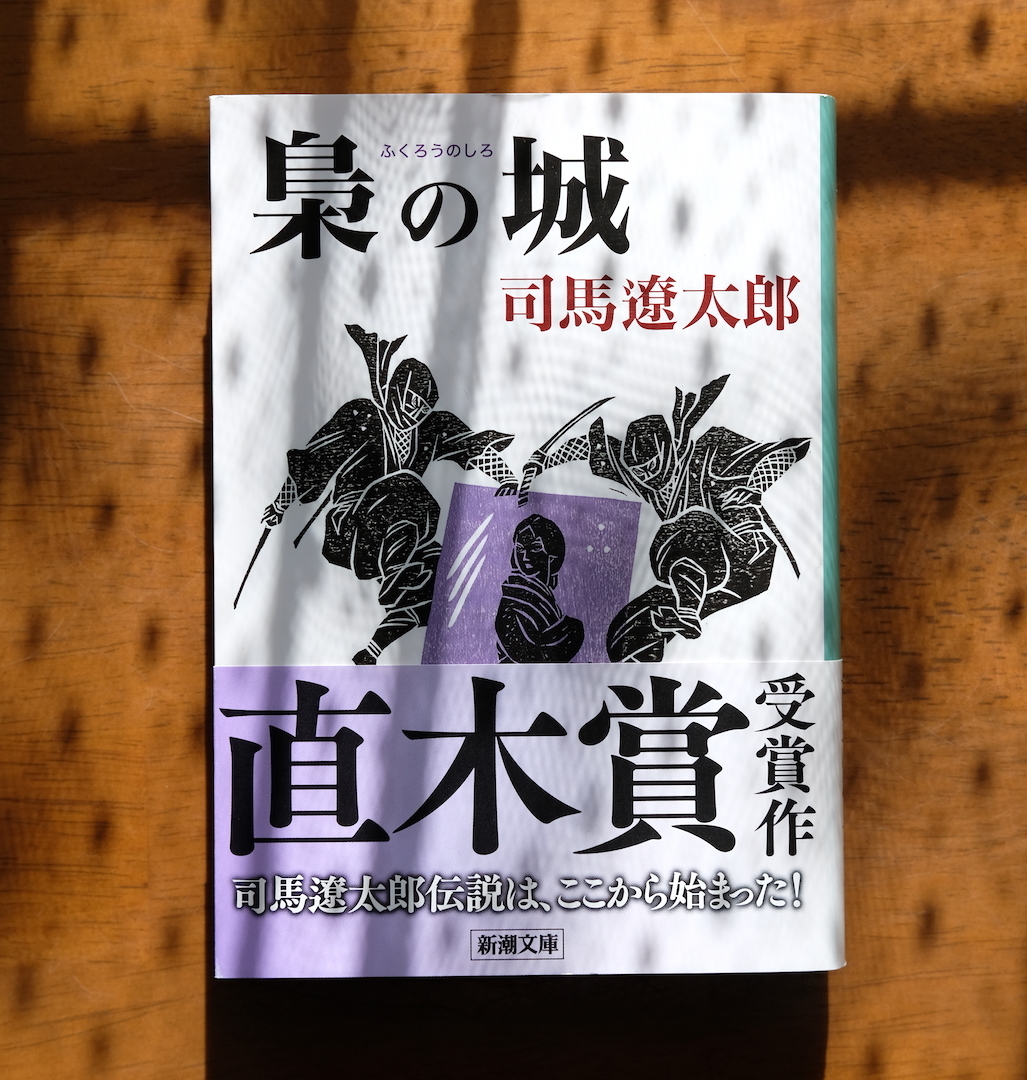司馬遼太郎という文豪がいます。
幕末や戦国時代に活躍した武士たちの物語などをはじめとする、多くの歴史作品を世に出した日本が誇る文学者です。
まずは、司馬遼太郎の出自と経歴をたどります。
筆名の由来は「中国前漢時代の歴史家で『史記』の著者として名高い司馬遷に遼󠄁(はるか)に及ばざる日本の者(故に太郎)」から来ているという。
大阪府大阪市生まれ。
産経新聞社記者として在職中に、『梟の城』で直木賞を受賞。
歴史小説に新風を送る。
代表作に『竜馬がゆく』『燃えよ剣』『国盗り物語』『坂の上の雲』などたくさんの小説がある。
さらに、『街道をゆく』をはじめとする多数の随筆・紀行文などでも活発な文明批評を行った。
1923年(大正12年)8月7日、大阪府大阪市南区難波西神田町(現・浪速区塩草)に、薬局を経営する父・福田是定(薬剤師)、母・直枝の次男として生まれた。
1930年(昭和5年)、大阪市難波塩草尋常小学校(現・大阪市立塩草立葉小学校)に入学。性格は明るかったが、学校嫌いで、悪童でもあったようである。大陸の馬賊に憧れていた。
後に戦車隊の小隊長となることでこの夢は結実した。
1936年(昭和11年)、私立上宮中学校に進学。
入学後の成績は300名中でビリに近く本人も驚いたらしいが、慌てて勉強をしたら二学期には上位20位に入ったという。
井伏鱒二の『岩田君のクロ』に感銘を受ける。
3年生から松坂屋の横の御蔵跡町の図書館に通うようになり、大阪外国語学校卒業まで本を乱読するようになる。
古今東西のあらゆる分野の書物を読破したという。
阿倍野のデパートでは吉川英治の宮本武蔵全集を立ち読みで読破した。
いつも立ち読みばかりするので頭にきた売り場の主任が「うちは図書館やあらへん!」と文句を言うと、「そのうちここらの本をぎょうさん買うたりますから…」と言ったそうである。
また、半ば趣味として山登りを好み、大阪周辺の名山は大抵踏破している。
高等学校への受験に際して、家計の都合で私立学校への進学は許されず、官立のみと父親から釘を刺されていた。
1939年(昭和14年)、中学生だった司馬にも日中戦争や第二次世界大戦が影を落としており、上宮中学の配属将校から学校教練を受けている。
1940年(昭和15年)に旧制大阪高校、翌年には旧制弘前高校を受験するも不合格。
1942年(昭和17年)4月に旧制大阪外国語学校(現在の大阪大学外国語学部モンゴル語専攻)に入学。
1943年(昭和18年)11月に、学徒出陣により大阪外国語学校を仮卒業(翌年9月に正式卒業となる)。
兵庫県加東郡河合村(現:小野市)青野が原の戦車第十九連隊に入隊した。
軍隊内ではかなり珍しい「俳句の会」を興し、集合の合図には一番遅れて来た。
翌44年4月に、満州四平の四平陸軍戦車学校に入校し、12月に卒業。
戦車学校で成績の良かった者は内地や外地へ転属したが、成績の悪かった者はそのまま中国に配属になり、これが生死を分けた。卒業後、満州国牡丹江に展開していた久留米戦車第一連隊第三中隊第五小隊に小隊長として配属される。
翌1945年に本土決戦のため、新潟県を経て栃木県佐野市に移り、ここで陸軍少尉として終戦を迎えた。
敗戦にショックを受けた司馬は「なんとくだらない戦争をしてきたのか」「なんとくだらないことをいろいろしてきた国に生まれたのだろう」との数日考えこんだ。
「昔の日本人は、もう少しましだったのではないか」という思いが、後の司馬の日本史に対する関心の原点となり、趣味として始めた小説執筆を、綿密な調査をして執筆するようになったのは「昔というのは、鎌倉のことやら、室町、戦国のころのことである。やがて、ごく新しい江戸期や明治時代のことも考えた。いくら考えても昭和の軍人たちのように、国家そのものを賭けものにして賭場にほうりこむようなことをやったひとびとがいたようには思えなかった」と考えた終戦時の司馬自身に対する「いわば、23歳の自分への手紙を書き送るようにして小説を書いた」からであると述懐している。
復員後は直ちに図書館通いを再開する。
戦地からの復員後、生野区猪飼野東五丁目8にあった在日朝鮮人経営の新世界新聞社に大竹照彦とともに入社。
1946年(昭和21年)、ふたたび大竹とともに新日本新聞京都本社に入社。同僚に青木幸次郎がいた。
このころから30歳を過ぎたら小説を書こうと考えるようになる。
大学、宗教記事を書いたが、社は2年後に倒産。
産経新聞社から「外語大卒だから英語くらいできるだろう」と誘われ、英語がまったくできないにもかかわらず「できます」と応じて京都支局に入る。
入社して1か月も経たない1948年(昭和23年)6月28日午後、福井地震が発生し、その日のうちに福井の取材に行く。
同年11月、歌人川田順の失踪事件を取材。
1949年、大阪本社に異動。
1950年(昭和25年)の初夏に京都の岩屋不動志明院に宿泊し奇っ怪な体験をする。
同年に金閣寺放火事件の記事を書いた(真っ先に取材に訪れた記者の一人とされる)。
このころ京都の寺社周り・京都大学を担当し、その結果京都の密教寺院で不思議な僧侶らと出会ったり、石山合戦のときの本願寺側の兵糧方の子孫の和菓子屋と話したり、京都大学で桑原武夫、貝塚茂樹らの京都学派の学者たちに取材したりするなど、後年の歴史小説やエッセイを執筆する種となる出会いがあった。
このことは後年の自筆の回想記(多く『司馬遼󠄁太郎が考えたこと』に所収)に記されている。
その後文化部長、出版局次長を務めた。
文化部時代の同僚に廓正子がいる。
同年に大阪大学医局の薬剤師と見合いにより最初の結婚。
1952年(昭和27年)に長男が誕生するが、1954年(昭和29年)に離婚。
長男は実家の福田家に預けられ祖父母に養育される。
この結婚及び、誕生した息子のことは、当時は一切公表されなかったが、司馬の死後の新聞報道により明らかになっている。
1955年(昭和30年)、『名言随筆・サラリーマン』(六月社)を発表。
この作品は本名で発表したが、このほかにも「饅頭伝来記」など数作本名で発表した作品があるといわれる。
さらに、当時親しくなっていた成田有恒(寺内大吉)に勧められて小説を書くようになる。
1956年(昭和31年)5月、「ペルシャの幻術師」が第8回講談倶楽部賞に応募(「司馬遼󠄁太郎」の名で投稿)、海音寺潮五郎の絶賛を受け同賞を受賞し、出世作となる。
また、寺内とともに雑誌『近代説話』を創刊した。
『近代説話』『面白倶楽部』『小説倶楽部』に作品を発表し続ける。
1958年(昭和33年)7月、「司馬遼󠄁太郎」としての初めての著書『白い歓喜天』が出版される。
当時は山田風太郎と並ぶ、伝奇小説の担い手として注目され、本格歴史小説の大家になろうとは予想だにされていなかった。さらに「梟のいる都城」(のち『梟の城』に改題)の連載を開始。
1959年(昭和34年)1月、同じ産経新聞記者の松見みどりと再婚。
12月に大阪市西区西長堀のアパートに転居。
同じアパートに南海ホークス時代の野村克也がいた。
『大坂侍』『梟の城』を発表。
1960年(昭和35年)、『梟の城』で第42回直木賞を受賞、翌年に産経新聞社を退職して、作家生活に入る。
初期は直木賞を受賞した『梟の城』や『大坂侍』『風の武士』『風神の門』などの長編や、短編「ペルシャの幻術師」「果心居士の幻術」「飛び加藤」など、時代・伝奇小説が多い。忍者を主人公にした作品が多く「忍豪作家」(五味康祐ら「剣豪作家」にちなむ呼び名)とも呼ばれた。
また、初期数編が西アジアを主要舞台としている点も異色でありながら、後年の創作へは引き継がれなかった。
推理小説も書き、『豚と薔薇』『古寺炎上』があるがあまり得意ではなくこの2作にとどまっている。
1962年(昭和37年)より『竜馬がゆく』『燃えよ剣』、1963年(昭和38年)より『国盗り物語』を連載し、歴史小説家として旺盛な活動を本格化させた。
この辺りの作品より、作者自ら、作中で随筆風に折込解説する手法が完成している。

1964年(昭和39年)には、終のすみかとなる布施市下小阪(現在の東大阪市)に転居した。
近所には付近の大地主であり上宮中学からの同級生の山澤茂雄がおり終生交流が続いたのちに「猥雑な土地でなければ住む気がしない」と記している。
1966年(昭和41年)、菊池寛賞を受ける。
その後も『国盗り物語』に続き、『新史太閤記』『関ヶ原』『城塞』の戦国四部作を上梓した。
1971年(昭和46年)から、紀行随筆『街道をゆく』を週刊朝日で連載開始した。
1972年(昭和47年)には明治の群像を描いた『坂の上の雲』の産経新聞での連載が終了。
また、幕末を扱った『世に棲む日日』で吉川英治文学賞。初期のころから示していた密教的なものへの関心は『空海の風景』(日本芸術院恩賜賞)に結実されている。
「国民的作家」の名が定着し始めるようになり、歴史を俯瞰して一つの物語と見る「司馬史観」と呼ばれる独自の歴史観を築いて人気を博した。
1970年代中期から80年代にかけ、明治初期の『翔ぶが如く』や、『胡蝶の夢』、江戸後期の『菜の花の沖』、戦国期の『箱根の坂』などを著し、清朝興隆の時代を題材にした『韃靼疾風録』を最後に小説執筆を止める。
「街道をゆく」や、月一回連載のエッセイ『風塵抄』、『この国のかたち』に絞り、日本とは、日本人とは何かを問うた文明批評を行った。
1981年(昭和56年)に日本芸術院会員、1991年(平成3年)には文化功労者となり、1993年(平成5年)に文化勲章を受章した。
このころから腰に痛みを覚えるようになる。
坐骨神経痛と思われていたが、実際は直接の死因となる腹部大動脈瘤であった。
それでも「街道を行く 台湾紀行」取材の折に、当時台北で台湾総統だった李登輝との会談「場所の悲哀」を行ったり、「街道を行く」取材で青森の三内丸山遺跡を訪れるなど精力的な活動を続ける。
また、晩年にはノモンハン事件の作品化を構想していたといわれているが、着手されずに終わった。
1996年(平成8年)1月、「街道をゆく 濃尾参州記」の取材を終え、連載中の2月10日深夜に吐血して倒れ、大阪市中央区の国立大阪病院(現:国立病院機構大阪医療センター)に入院、2日後の2月12日午後8時50分、腹部大動脈瘤破裂のため死去した。
享年72歳。
死去した国立大阪病院は、奇しくも『花神』で書いた大村益次郎が死去した場所であった。
絶筆「濃尾参州記」は未完となった。
親族・関係者による密葬を経て、3月10日に大阪市内のホテルで「司馬遼󠄁太郎さんを送る会」が行われ、約3,000人が参列した。法名は、「遼󠄁望院釋淨定」。
政府から従三位を追賜された。
翌年に司馬遼󠄁太郎記念財団が発足し、司馬遼󠄁太郎賞が創設された。
2001年(平成13年)に、東大阪市の自宅隣に司馬遼󠄁太郎記念館が開館。
司馬遼󠄁太郎記念室がある姫路文学館では毎年8月7日の生誕日に、ゆかりのゲストを迎えて「司馬遼󠄁太郎メモリアル・デー」を開催している。

司馬遼󠄁太郎は、新しい視点による彼自身の歴史観と斬新な描写により、日本社会に広く影響を与えた国民的作家であると言われており、死後においても司馬の影響力は大きい。
司馬の作品の多くがベストセラーとなり、また多くが映像化されている。
NHK大河ドラマ原作となった作品数は最も多く、「21世紀スペシャル大河ドラマ」(後にNHKスペシャルドラマと変更)と称する『坂の上の雲』を含めると7作品である。
司馬遼太郎の長編小説は以下の通り:
- 『梟の城』(1959年、講談社)
- 『上方武士道』(1960年、中央公論社)- 没後『花咲ける上方武士道』に改題再刊
- 『風の武士』(1961年、講談社)
- 『戦雲の夢』(1961年、講談社)
- 『風神の門』(1962年、新潮社)
- 『竜馬がゆく』(1963-1966年、文藝春秋新社)
- 『燃えよ剣』(1964年、文藝春秋新社)
- 『尻啖え孫市』(1964年、講談社)
- 『功名が辻』(1965年、文藝春秋新社)
- 『城をとる話』(1965年、光文社)
- 『国盗り物語』(1965-1966年、新潮社)
- 『俄 浪華遊侠伝』(1966年、講談社)
- 『関ヶ原』(1966年、新潮社)
- 『北斗の人』(1966年、講談社)
- 『十一番目の志士』(1967年、文藝春秋)
- 『最後の将軍』(1967年、文藝春秋)
- 英訳版『The Last Shogun』(Juliet Winters Carpenter・訳)
- 『殉死』(1967年、文藝春秋)
- 『夏草の賦』(1968年、文藝春秋)
- 『新史太閤記』(1968年、新潮社)
- 『義経』(1968年、文藝春秋)- 連載時の題名は『九郎判官義経』
- 『峠』(1968年、新潮社)
- 『宮本武蔵』(1968年、朝日新聞社『日本剣客伝』収録)
- 『坂の上の雲』(1969-1972年、文藝春秋)
- 『妖怪』(1969年、講談社)
- 『大盗禅師』(1969年、文藝春秋)
- 『歳月』(1969年、講談社)
- 『世に棲む日日』(1971年、文藝春秋)
- 『城塞』(1971-1972年、新潮社)
- 『花神』(1972年、新潮社)
- 『覇王の家』(1973年、新潮社)
- 『播磨灘物語』(1975年、講談社)
- 『翔ぶが如く』(1975-1976年、文藝春秋)
- 『空海の風景』(1975年、中央公論社)
- 英訳版『KUKAI THE UNIVERSAL』(武本明子・訳)
- 『胡蝶の夢』(1979年、新潮社)
- 『項羽と劉邦』(1980年、新潮社)- 連載時の題名は『漢の風 楚の雨』
- 『ひとびとの跫音』(1981年、中央公論社)
- 『菜の花の沖』(1982年、文藝春秋)
- 『箱根の坂』(1984年、講談社)
- 『韃靼疾風録』(1987年、中央公論社)
- 英訳版『The Tatar Whirlwind』(Joshua Fogel・訳)
司馬遼太郎の小説は大人気で、最新の発行部数に関するデータは以下のようになっている:
2023年1月11日付「産経新聞」によると、司馬遼太郎記念財団が生誕100年になるのに合わせ、各出版社に問い合わせた結果、全司馬作品の紙・電子を合わせた累計発行部数は、2億673万部。
1位「竜馬がゆく」2496万部
2位「坂の上の雲」1987万部
3位「街道をゆく」1224万部。
その他は「国盗り物語」は749万部、「関ヶ原」は630万部、「世に棲む日日」は527万部、「燃えよ剣」は517万部、「菜の花の沖」は515万部、「峠」は402万部、「花神」は384万部。
司馬遼太郎の多くの作品がすでに映画化されており、現在確認できるものは以下の通り:
- 恋をするより得をしろ(1961年、監督:春原政久、原作「十日の菊」)
- 忍者秘帖 梟の城(1963年、監督:工藤栄一)
- 新選組血風録 近藤勇(1963年、監督:小沢茂弘)
- 暗殺(1964年、監督:篠田正浩、原作「奇妙なり八郎」)

- 風の武士(1964年、監督:加藤泰)
- 城取り(1965年、監督:舛田利雄)
- 泥棒番付(1966年、監督:池広一夫、原作「盗賊と間者」)
- 燃えよ剣(1966年、監督:市村泰一)
- 人斬り(1969年、監督:五社英雄、参考文献「人斬り以蔵」)
- 尻啖え孫市(1969年、監督:三隅研次)
- 幕末(1970年、監督:伊藤大輔、原案「竜馬がゆく」)
- 忍びの衆(1970年、監督:森一生、原作「伊賀の四鬼」)
- 梟の城(1999年、監督:篠田正浩)

- 御法度(1999年、監督:大島渚、原作「新選組血風録」)
- 関ヶ原(2017年、監督:原田眞人)
- 燃えよ剣(2021年、監督:原田眞人)
- 峠 最後のサムライ(2022年、監督:小泉堯史)

これから映画化作品を出来る限り多くレビューして行きます。
お楽しみに!