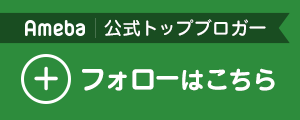加熱しても死なない芽胞とは?
 カレーの食中毒原因でよくある
カレーの食中毒原因でよくある
ウェルシュ菌による食中毒はどんな症状?
潜伏期間は6~18時間(平均10時間)で、腹痛や下痢などの症状が現れます。
夏(7~9月)に多く発生します。 ウエルシュ菌のうち、芽胞を形成したものは通常の加熱では死滅しません。また、自然界に分布する菌のため、食品への汚染を根絶することは不可能です。
予防するにはどうしたらイイ?
■しっかり加熱■
ほとんどの細菌やウイルスは、加熱によって死滅します。肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安心。特に肉料理は中心までよく加熱することが大事です。
※中心部を75℃で1分以上加熱←ちなみに厨房では毎回測り、記録を残しています。
■速やかに冷却■
ウェルシュ菌は一度、芽胞を作ってしまうと、一般家庭の加熱では、死滅させることは難しいです。そのため、芽胞を作らないように気を付けることが大切です。
増殖可能な温度帯(12℃~50℃)をできるだけ速やかに、通過させます。
保存容器がない場合は、鍋ごとではなく、1人分づつ、お皿に分けてラップをして冷蔵庫で冷やす方が良いです。
まとめ
再加熱すれば大丈夫!ではありませんので、調理後すぐに食べるか、
食べない場合は速やかに冷却してください。
ちなみに厨房では、3時間前調理というのが鉄則で、3時間以上前に調理したものは提供できないルールになっています。
久しぶりにネットでマスクを検索したら
N95が出ていたので念のため購入しました。
とりあえず、一番少ない枚数でお安かったのでこちらの20枚入りを。
↓
こちらは日本製のもので、N99規格のフィルターで
普通の形のマスクで、こちらは目立たないので、こちらも購入しました。
株式会社エースインターナショナルジャパン さんという日本のメーカーさんが作っている商品だそうです。
↓
ちなみにKN95という商品もたくさんでていて、KNは防塵用
ですが、メルトブレーンが入っている5層のものを購入しておきました。
本でご提案させていただだいている献立は、日本人の食事摂取基準(厚生労働省による)という健康の維持・増進、エネルギー、栄養素の欠乏予防、生活習慣病の予防、過剰摂取による健康障害の予防を目的とした、栄養士などの専門家向けの利用目的で作成されているものを参考にして、作っています。