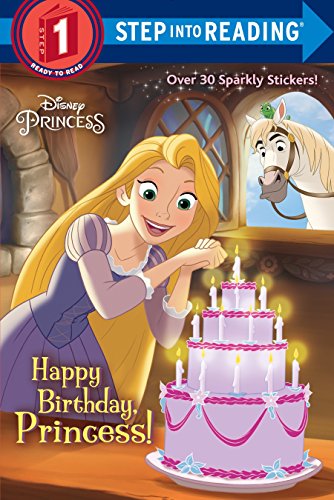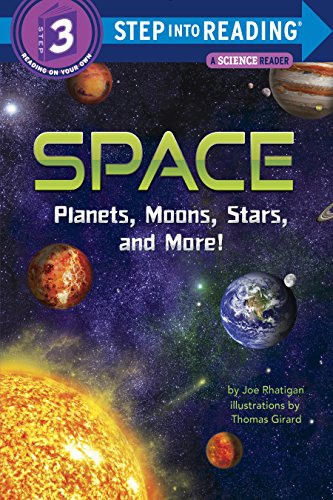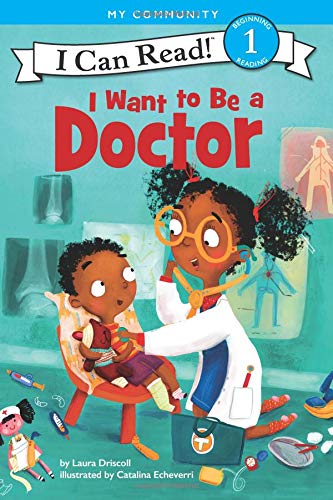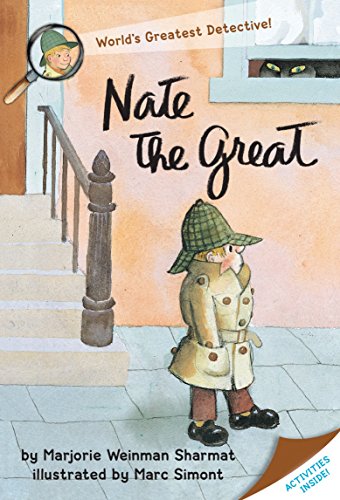SNSで質問をいただいたので
こちらでお答えします。
アルファベットの音も入り、
サイトワードもある程度 身についた
その後は読みはどうする?
書きの進め方は?
というご質問。
これは、お子様の年齢に限らず、
その子の現在の英語力や性格、
どれだけ運筆力があるか
読みに対してどのような姿勢か(自ら本を手に取る方か、動く方が好きなのか等々)
それが見えないと何ともお答えできませんが、一つ言えるのは
読み書きの流暢性は小学校に上がった後、伸びる子も多いので、未就学児であれば、気長に構えていてよいのではないかなと思います。
自分で読むというのは、
小学生になったら読む量も増えるとは思いますが
未就学児だったら
かなり労力を要するもの。
なので、フォニックスが入ったあとは
とにかく地道に今のレベルのものを読み続ける。
今読んでいるもの、例えば
Bob sat on a bat.
というような文章を流暢に読めるようになったら
サイレントeやサイトワードなどが少し入っているものに
レベルアップしてみる。
文字読みへの道④でも紹介したような
薄いリーダー本を読んでもいいし、
もうちょっと面白い内容を、
というのであれば、
下のような
Step Into Readingシリーズ。ただ、ボックス入りの薄いリーダー本と違い、サイトワードや読みづらい単語も一気に入ってくるので、子ども自身に読ませる時期はよく考えた方がいいかもしれません。
あるいは
I Can Readシリーズの簡単なものから一緒に読んでもいいと多います。レベル1の前に、"My First I Can Read"が付いているものから始めると良いのかなと。
この時に注意してもらいたいのが
いきなり最初から本人に読ませようとしない
ということ。
もちろん、自分でどんどん読みたい子もいるだろうし
横から言われるのが嫌な子もいると思います。
それだったら見守って
聞かれたら答えるくらいでいいと思いますが
そうでない場合は
最初は読めそうな単語から子どもに読んでもらう。
それ以外はお母さんが読み聞かせる感じで
ところどころ子どもに手伝ってもらう。
そうやって子どもが読める単語を少しずつ増やしていく。
というのもいいのかもしれません![]()
読みは、持久力がなかなかつきづらい。
フォニックスもサイトワードも入った。
そしたら、気長に子どもが読みの持久力がつくまで
細く長く続けるというのでいいのではないでしょうか?
こうしたリーダー本を経て、
段々と文章量が多いものも読めるようになって
下の本のように
Early Chapter Booksと呼ばれる
章ごとに分かれている本に進んでいきます。
もし、もう黙読をし始めていて、
「本当に読めているのかしら?」と分からない場合は、
無理に音読をさせるのではなく
「一緒にこの本、読もう」と言って
読み合いっこをするなどして確認してもいいかもしれません。
そして書きの進め方。
これも子どもによって書くのが好きな子、
そうではない子、それぞれなので
何が一番いいとは言いづらいですが
未就学児、小学校低学年であれば
好きなように書かせる
でいいのではないでしょうか?
スペルミスがあっても、Sが反対を向いていても
子どもが書きたいものを書く。
書きたいことが特にない場合は・・・
たとえば、サンタさんや歯の妖精さんに
手紙を書いてみるとか
お母さんがとっかかりを作ってもいいかもしれません。
「どんなことサンタさんに伝えたい?」
「こんなことはどうかな?」
ちょっとヒントを出してもいいかもしれませんね![]()
想いがなければ書くこともなかなか難しいので
書く前にたくさんお話するのをいいと思います。
文字の正しさや文法やスペルは
「書きたい」気持ちを十分に満足させてからでもいいかなと思います。