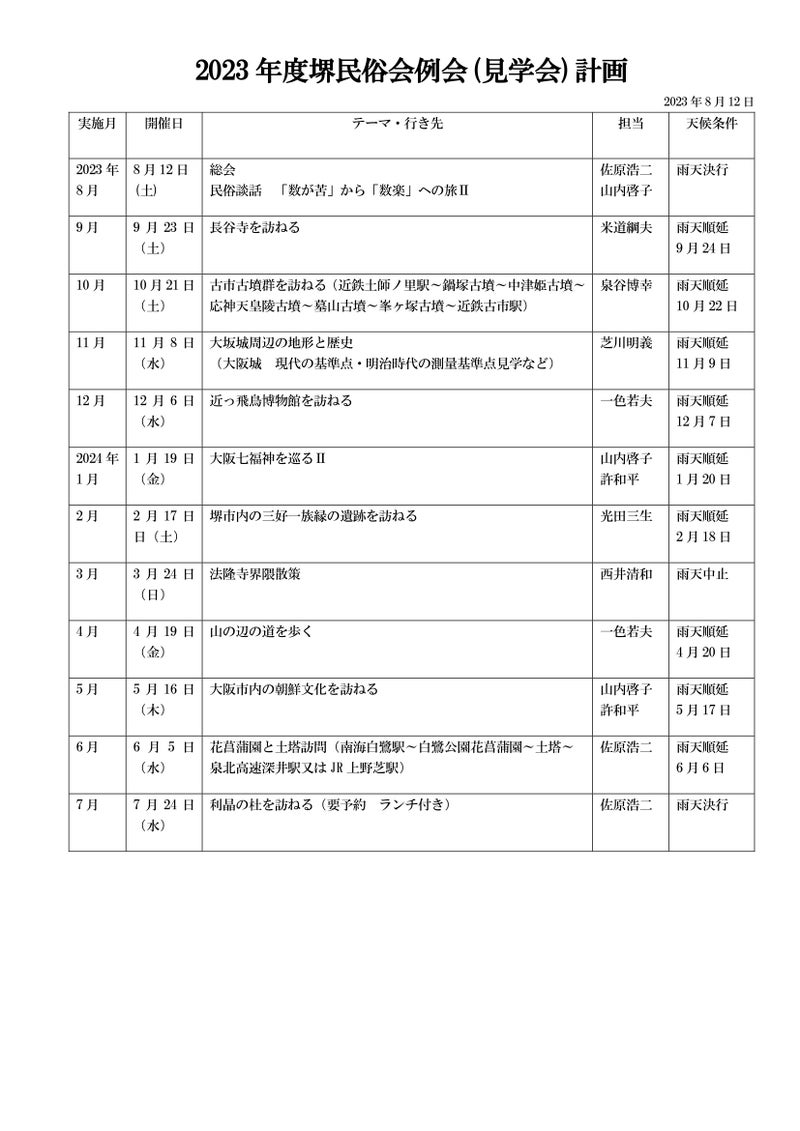米沢藩と上杉鷹山
米道綱夫
9月始めに米沢に行った。米沢は東北新幹線に連結された山形新幹線で行ける。福島で東北新幹線からツバサの車両を切り離して米沢に約1時間で到着する。米沢は上杉鷹山で有名な街である。鷹山の藩経営哲学は現代にも通じており、バブルが弾けた頃の1992年ごろから盛んに取り上げられた人物である。鷹山は高鍋藩の江戸屋敷で生まれた。幼年期から学問を好みすぐれた才能の持ち主であった。鷹山(治憲)が米沢藩の藩主になる前の米沢藩は財政が大変貧しく度重なる凶作で藩としての維持も難しい状況の中19歳で藩主になった。鷹山公以前の米沢は慶長5年関ヶ原の合戦で豊臣方についた上杉軍は会津120万石を没収され米沢30万石に移封されました。藩主上杉景勝の側近だった直江兼続は藩の収益の増大を図るために様々な施策を実行しましたが、その一つが桑、青苧、紅花でした。上杉謙信を祖先とし、代々上杉家としての誇りを体現したのが兼続です。それから約170年鷹山公が米沢藩を治めることになるのですが、兼続の精神は受け継がれていきます。
明和6年彼は家臣を集めると倹約、公平、清潔を政策の基本とし竹俣当綱、莅戸善政の二人を政策の実行役とした。倹約令は実施され藩の財政も少し持ち直してきた。鷹山が次に取った政策は殖産興業である。新田の開発、橋の架け替え、川さらいと土手の補強、備籾蔵の建設など精力的に進めたが、4年後以前からの老臣が、訴状を持って詰め寄った。しかし、訴状の内容は事実に反したもので老臣たちは処罰された。見事鷹山は危機を乗り切った。これを機に下級藩士で優秀なものが抜擢され積極的な産業の開発となった。その頃の米沢藩の重要な財源は青苧、蝋だった。それから2年後竹俣当綱は漆、桑、楮各100万本計画を発表特産品作りに励んだ。このほか小野川に製塩所を開き、墨・硯を作り、和紙の生産、藍園も開いた。青苧・繰り綿を藩財政の立て直しに使っていたが、安永5年越後松山の縮師源右衛門一家と職工2人を招き、婦女子に織物技術を教えた。そして何よりも鷹山の側室お豊の方が織物技術の普及に一役買った。お豊は鷹山より10歳年上で鷹山の正妻幸姫が30歳で亡くなった後鷹山の良き理解者であった。
藩政改革の要は人材育成であると、鷹山も竹俣当綱は感じていた。そこで鷹山は自ら細井平洲を江戸に訪ね、米沢に来てもらうこととした。白子神社の隣の松桜館で講義が始まったが藩内には藩の恥だと反対すものもいた。平洲の実業のための学問である講義は広く藩内に行き届いて、安永5年平洲が命名した興譲館が完成、塾長には神保欄室がなった。平洲の在米沢期間は短かったが2070名の聴講者を数えた。
天明3年の大飢饉は奥羽地方にとてつもなく大きな災害をもたらしたが、坂田新潟から米約一万俵を買取り飢饉に当てた。おかげで人口減少は全国平均5パーセントを下回り2,3パーセントだった。
寛政2年藩政に関する改革の意見を藩士求めたところ340通もの多くのぼった。黒井半四郎による黒井堰の完成は総延長44kmの水路で米沢北部から南部に水を引き、灌漑面積9平方キロメートルに及んだ。そして莅戸太華の政策によって衣部は桑・青苧・繰り綿食部は米・麦・栗・大根・鯉 住部は松・杉・桐 雑部は油・膳椀・硯などの増産が図られた。
米沢神社のそばの米沢市博物館は鷹山の業績を余すところなく伝えていた。私はその後上杉謙信の像や上杉景勝・直江兼続・上杉鷹山の銅像を見て回った後、米織会館に向かった。米沢織を開発したのは鷹山公であり、以前からあった青苧を原料とした織物から、置賜地方の養蚕を基礎とした絹織物製造に移行し、出羽の米沢織として全国に名声を馳せることとなりました。大正時代には米沢高等工業学校(のちの山形大学工学部)教授秦逸三が日本で初めて人絹の製造に成功、米沢市館山に帝国人絹株式会社(現帝人株式会社)を創設しました。米沢の織物業は伝統的な絹織物から発展し、現在は天然繊維と化学繊維による服地、呉服から総合的なテキスタイルの産地を形成し、全国でも類を見ない繊維の総合産地になっています。