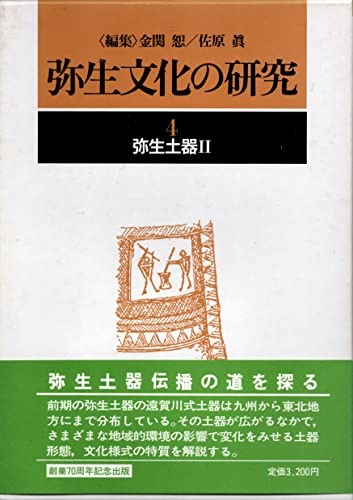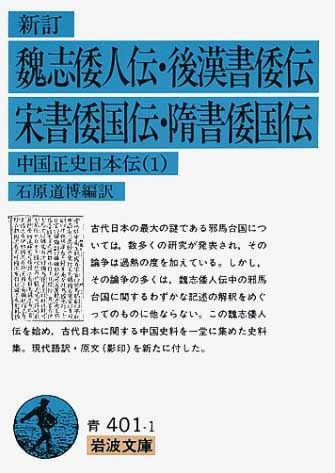毎度、当ブログへお越しいただき、ありがとうございます。
今回は愛知県安城市の古代の遺跡を訪ねます。
おそらく三河国の黎明期は安城市周辺が文化の中心だったんだろうと思われます。
それでは早速訪ねましょう!
安城市歴史博物館にあるアレ!を訪ねる
まず訪ねたのは安城市歴史博物館。
ここには、弥生時代について語る本では必ず見かける、アレがあります。
日本人に「鯨面」の習慣がある、と結論付けるきっかけとなった、アレです。
その名も「人面文壺形土器」!
写真を見ればわかります。考古学ファンならきっと一度は文献で見たことがあるはずです。
…見たことがありませんか?
私は、弥生時代には日本に入れ墨の風習があったことを示す貴重な土器の例として、最も出来の良いこの土器が文献で紹介されているのを度々目にしてきました。
ネットでその名前(人面文壺形土器)を見た時は「どんな土器なんだろう![]()
![]() 」と思いましたが、実物を見たら
」と思いましたが、実物を見たら
「ああ、この土器か![]()
![]() 」
」
となりました。
この土器が常設展示でいつでも見られるのが、安城市歴史博物館です。
この土器は安城市内、東町亀塚遺跡から出土したもの。
弥生時代も終末期に位置づけられる土器とのことでした。
「日本には古代、刺青をする風習があって、それによって特別な力を得たとされるシャーマンとされる人々がいた」という解説の流れで必ず紹介される土器です。
いやぁ、ここでその本物に出会えるとは。感慨深いものがあります。
今回の東三河地方の旅で一番、縁を感じた逸品ですね。
東町亀塚遺跡からは、文様が刻まれた土器片が他にも出土しているそうです。
それらの土器片は附指定となっていて、一緒に展示されていました。
土器片1とされているものには、4本の平行沈線文でF字形の文様が刻まれていました。
もう一つ。
高坏の脚部と思われる土器片2には、同じようなF字形の文様が2つ刻まれ、それ以外に、さらに竪穴住居のような文様がある、とのことです。
上の写真はF字文の方から撮影したもの。
下の写真は、竪穴住居とされる紋様を撮影したもの。
…そうなのかな?
F字文は住居に対して跪く人を表わしているとされています。
これは、反対する説もきっとあるだろうな。
私にはわかりませんが、こういった絵画を楽しむ余裕が、当時の人にはあったのだろうと思います。
ストレスとかなかったんだろうな。うらやましいです。
二子古墳を訪ねる
続いて訪ねたのは、同じ安城市内にある古墳、二子古墳です。
安城市内には矢作川流域に沿って、桜井古墳群といわれる古墳群が築かれています。
二子古墳はその主墳とされる巨大古墳で、しかもおそらく、古墳時代前期(4世紀)まで遡る可能性がある前方後方墳とされています。
そうなると、『魏志倭人伝』との関わりをうかがわせることになり、ひいてはあの「卑弥呼」との関わりも出てきます。
というのも、魏志倭人伝の中で、卑弥呼と対立した狗奴国は、この三河地方のことだという説があるからです。
もっともこれはいわゆる邪馬台国=畿内説に基づいた場合になります。
有名な説だから知っている人も多いことでしょうが、要は前方後円墳の文化圏である畿内地方に対立するように存在する前方後方墳文化圏は三河地方が中心となっている、だから邪馬台国と対立していたと魏志倭人伝にある狗奴国は、三河方面にあったのではないか、とされるものです。
この説にはもちろん、ツッコミどころはあるんですけどね。それは置いといて、桜井古墳群は古墳時代でもかなり古い時期の古墳が集中していているのですが、現在でも墳丘がキレイに見られるのは二子古墳とこの後紹介する姫小川古墳だけとなっているとのことですので、じっくり見てみましょう。
マニアとしては大変見どころ満載な古墳ですが、おそらく地元の人はあまり気にしていない様子。
犬の散歩コースになっているようで、墳丘を行ったり来たりしている私(マニアっぷりを発揮しているにもかかわらず)には目もくれず、スルーして行ってしまいました。
…むしろそんなマニアがしょっちゅう来ているのを見ているから、慣れているとか?
この古墳の麓、墳丘東側からは墳を築いたとみられる人々が営んでいた集落跡が見つかっています。
二タ子(ふたご)遺跡と呼ばれていて、安城市指定史跡となっていました。今は水田となっていました。
高架橋は東海道新幹線です。
姫小川古墳を訪ねる
続いては桜井古墳群に残るもう一つの古墳、姫小川古墳を訪ねました。
後円部には現在、浅間神社が鎮座しています。神社の前に少しばかり広場がありましたので、ここにマイカーを停めさせてもらいます。
くびれ部が細く、後円部が前方部に比して高いのは前期古墳の特徴ですが、前方部は江戸時代にお堂を建てるために削平されているそうです。
ただ、その他の調査によってこの古墳は、やはり前期古墳なのだろうとのこと。
「前期古墳」、古墳マニアにはキーワードのひとつでしょう。
私も古墳の周りをじっくりと歩き回ってしまいました。前期古墳は測量調査が重要だよねぇ。
というわけで現地解説板にあった平面図も掲載しました。
久麻久神社からここまで、やっと長い一日が終わりました。うーん、充実した一日だった。太陽もだいぶ西に傾いています。
夏至が近いからこんな時間まで色々見られましたが、冬だったらとっくに暗くなっている時間です。
夏は日が長いからいいねぇ。
この日は安城市内で一泊しました。
明日(次回)も早朝から活動します。