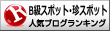今回もご覧いただき、ありがとうございます。
前回の吉見百穴は、閲覧数がいまいち伸びませんでした。
私が吉見百穴に寄せている思いを注ぎ込んだつもりだったのですが、あまり興味を持たれない話でしたのでしょうか。
残念です。

ちなみに、吉見百穴のそばに「岩窟ホテル」というものがあります。
この土地を所有する方が地山の加工のし易さからか、一人で30年ほどの年月をかけ、ホテルの客室のような部屋を岩壁を穿って作った彫刻、というのか建物?なのです。
私が幼いころは入場料を払えば入ることができ、中にはお休み処や土産物店もありました。吉見百穴が近いことや物珍しさも手伝って、地元ではちょっと有名な観光地でした。
私も家族と一緒に中まで入って見学したことがあり、よくぞまあ一人でここまで掘り進めたものだと感心したものでした。
その後しばらくして崩落の危険があるとのことで立入禁止となってしまい、廃墟化していきました。
それがきっかけなのか、この場所は心霊スポットとして名を馳せる場所になってしまい、不逞の輩が夜な夜な不法侵入するようで地元では問題になったこともありました。私から言わせれば、決してそのような曰くつきの場所ではないのですが…
おもしろい名所なので、再び見学できるようになってほしいものです。しかし閉鎖して既に30年ほど経ちました。
先日訪ねた時には、岩は崩れ、広場だったところは草や灌木が伸び放題。すっかり荒れ果てていました。
ここはもう、日の目を見ることもないのでしょう
さて、今回は吉見百穴に見られるヒカリゴケを紹介します。
正直、ヒカリゴケはそれほど珍しくはありません。比較的標高が高いような冷涼な気候の場所なら岩陰や洞窟に着生している場所が結構見られますから。
そういうわけであまり思い入れがないのですが、ここが国指定天然記念物になった当時は標高が低い場所での発生は珍しいとされました。
そのような理由で指定された経緯があるので、
「確かに平地でヒカリゴケが見られるのはあまりないよな」
ってことで数年ぶりに吉見百穴訪問と合わせて見てきました。
ヒカリゴケが見られるのは吉見百穴の西寄りの2~3基の横穴墓内で、立ち入りできないように柵が設けられた穴の中に見られます。通路脇なので簡単に見学できます。
 吉見百穴(ヒカリゴケは写真中央の最下部にある横穴墓に見られる)
吉見百穴(ヒカリゴケは写真中央の最下部にある横穴墓に見られる)
一番見やすい穴には、下の写真のような看板があります。
もう少し、接近してもう一枚。
看板には自生地とありますが、指定名称は「ヒカリゴケ発生地」となっています。
穴の中には、黄緑色に輝くヒカリゴケが、だいたい通年で見られます。
ヒカリゴケの構造上、光が入らないと光って見えないので明るくなったところのものだけ光って見えます。
昔に比べると、やっぱり減った気がするなぁ…。この穴では以前はもっと、上の写真でいえば右の方の、草が生えているあたりまで光っていたような気がします。
国内のヒカリゴケ自生地で国指定天然記念物となっているところは吉見百穴も含めて3ヶ所あり、他の1ヶ所は長野県佐久市岩村田の発生地、もう1ヶ所はなんと、都内の江戸城跡にあります。
長野県の指定地はヒカリゴケが初めて発見された場所として指定されました。
ここは昔一度見に行ったことがあり、川の流れがカーブする場所で、浸食でできた洞穴があって、その中が広く黄緑色に光っていて神秘的でした。こちらはいずれ、また紹介します。
江戸城の指定地は、北の丸公園に隣接する鉢巻土塁の石垣の中で、春のサクラで有名な千鳥ヶ淵に面している場所です。
こちらも昔、訪ねて行ってみたことがありました。しかし、足場が悪く危険なことや史跡保護の面から立入禁止となっていて見ることはできませんでした。
ヒカリゴケが天然記念物に指定されているのはその希少性からであり、長野県の指定地は最初の発見地ということで指定されました。
また先にも述べた通り冷涼な気候を好み、平野部での発生は珍しいとのこと。そのような理由から残りの2ヶ所については発生地の標高の低さや都市部での発生地ということが指定理由に挙げられています。
埼玉県内でも比較的高所であれば他にも自生地があり、県や市町村の天然記念物として保護されています。ただ、それらの場所は足場が悪かったり登山の装備が必要だったり、気軽に訪れられる場所ではありません。
そのようなわけで気軽に訪れることができる吉見百穴のヒカリゴケ自生地は、ヒカリゴケを気軽に見られる珍しい場所として国指定天然記念物となっているわけです。
ただ平野部の乾燥は以前よりも進んでいるとされ、吉見百穴は史跡自体の劣化が著しいです。ヒカリゴケの生育環境は明らかに悪化しています。いつまでここでヒカリゴケが見られることやら、懸念されます。
-----------
吉見百穴ヒカリゴケ発生地(大正12年3月・天然記念物 埼玉県比企郡吉見町北吉見)
吉見百穴にある横穴墓のうち、最下部にあるいくつかの横穴にヒカリゴケの自生が見られます。ヒカリゴケは胞子から発芽した原糸体の細胞がレンズ状になっていて光を反射する構造をしており、そのため光って見えます。亜寒帯針葉樹林内の洞穴や岩陰に自生することが多く、日本では中部地方以北の本州と北海道で見られます。
吉見百穴のヒカリゴケは亜寒帯ではない関東平野の中で、しかも特に標高が低い場所で発見されたことから天然記念物として指定されました。さらに標高の低い江戸城跡でも発見され、こちらも天然記念物として保護されています。
ブログが気に入ったらクリックをお願いします