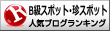いつもごらんいただき、ありがとうございます。
前回、高崎市の観音塚古墳を訪ねました。
群馬は古墳大国ですから、一つ古墳を見たら、次にまた別の古墳が見たくなります。
群馬県は巨大古墳が多数残されていますから、次に訪ねたい古墳に迷うことはありません。
「次はこの辺りに行こう!」と群馬県の南部、藤岡市に目を付けました。

そんなわけで、「次に行きたい」古墳は… 藤岡市にある白石稲荷山古墳です。
この辺りは巨大古墳が多く、「模様積み」の横穴式石室が秀逸な伊勢塚古墳、豪華な副葬品が発見された平井一号墳、横穴式石室が発見された皇子塚古墳、そしてその巨大さが際立っている七輿山古墳など、古墳時代後期の特徴的な古墳が有名な地域です。
いずれも後期に築かれた古墳なのですが、そのなかで前期に位置づけられる巨大古墳がありました。
その古墳が白石稲荷山古墳です。周辺の大きな古墳に対して、明らかに築造時期が古い古墳なのです。
古い前方後円墳の特徴が見られ、既にその時期にはこの地域を統治する巨大な権力を有した首長がいたことを明らかにしています。
それでは、訪ねてみましょう。
今では静かな住宅地となっている周辺には車を駐車するところはありません。近所にある、藤岡市内の考古学的成果を展示している「藤岡歴史館」という施設の駐車場をお借りしました。
藤岡歴史館は重要文化財に指定された収蔵品も展示されることがある立派な博物館です。
それらの展示も興味深いので後ほど閲覧させていただくこととして、とにかく駐車場をお借りします。
ここから南西方向へおよそ1kmほど歩くと、住宅街が途切れて広い芝地が現れます。そこは視界を遮るものがなく、ひときわ目立つ巨大な盛土が突然、姿を現しました。それこそが目指す白石稲荷山古墳でした。
ここは古墳の北側にあたります。
周囲の草は丁寧に刈られていて、墳形がよくわかりました。地元の人がよく手入れをされているようです。
古墳は地元を流れる鮎川という川の左岸にあたる丘陵上にあります。この丘陵を地元では白石丘陵と呼んでおり、丘陵上には多数の古墳が存在していました。
だから周辺の見晴らしがいい。南東側から見ると前方部の墳裾から後円部までよく見通せます。
一周して北側に戻ってきました。
ここから墳丘に登ってみたいと思います。
その前に上の写真の足元…
なんとなく盛り上がっているのがわかりますでしょうか?
実はなんと一見ほとんど平らに見える、このわずかな盛り上がりが白石稲荷山古墳の陪塚なんです。
昭和62(1987)年、ここは発掘調査で一つの古墳とみられていたところが2つの古墳だとわかり、それぞれ十二天塚古墳と十二天塚北古墳と命名され、平成21年には史跡として追加指定されています。
 北側の丘陵崖から見た十二天塚北、十二天塚および白石稲荷山の各古墳
北側の丘陵崖から見た十二天塚北、十二天塚および白石稲荷山の各古墳
正直言って、ここが古墳とは信じられないほど起伏がありません。地形のわずかな盛り上がりのように見えます。しかし発掘調査によって、それぞれから葺石や埴輪列、竪穴式の礫槨が見つかったそうなのです。
じゃあ、やっぱり古墳なんだな…
平地から見るかぎり、ほとんど盛り上がってません。埴輪列や葺石がなければ古墳とは認識できませんよ。
 白石稲荷山古墳の後円部から見た十二天塚(左側)、十二天塚北の両古墳
白石稲荷山古墳の後円部から見た十二天塚(左側)、十二天塚北の両古墳
稲荷山古墳の墳丘上から見ても、わずかな盛り上がりがあるだけのように見えます。
ここに2つの古墳があるようには見えません。
そもそも、ここは発掘前まで、一つの古墳と認識されていたくらいです。古墳とはみられていたんですね。現地に立つと古墳とみられていたことも驚きです。
しかしここにはそれぞれに埴輪列や葺石があり、一方からは礫槨も発見されたのです。
なかなか状態も良かったようですよ。驚きです。
そのまま稲荷山古墳の墳丘に登ってみました。
後円部の頂上へ来ました。
ここには大きな石碑がありました。「稲荷山古墳碑」とあります。
「何が刻まれているのかな?」と表面に目を凝らしました。
黒っぽい片岩の表面なので大変読みづらいのですが、目を凝らして刻まれた文字を読みました。そこには古墳の規模と昭和8年に行われた調査における成果が記されていました。
その当時の調査では、東西に二つの竪穴式礫槨が検出され、鉄刀、鏡、石製模造品や埴輪が見つかったようです。特に石製模造品の出土は特筆すべき成果で、これと埴輪の存在によって古墳の築造時期がほぼ4世紀末から5世紀初頭と位置付けらたようです。
墳頂からは群馬を代表する山、赤城山が望めました。
「ああ、群馬に来たな~。」と実感するひと時です。
前方部へ行ってみましょう。後円部より低い前方部は前期古墳の特徴です。先に記した出土品による推定築造時期にも合致します。
後円部が高いのがよくわかりますね。
後円部から前方部を見下ろすこともできます。前期古墳だな、と実感します。
ひととおり古墳を堪能したら、藤岡歴史館へ行ってみましょう。
白石稲荷山古墳から出土した埴輪が展示されています。
埴輪が出土しているから、推定築造時期が5世紀にまでずれ込むんでしょう。
もう少し白石稲荷山古墳についての展示があると嬉しかったのですけど、今回はこれだけでした。
もっとも、藤岡歴史館のメインは近所にある平井一号墳からの出土品です。この出土品は重要文化財に指定されていて、本物の展示は滅多にないのだとか(出土した刀剣の復元品は常設展示されています)。藤岡歴史館は本来、藤岡市の埋蔵文化財収蔵庫であり、平井一号墳出土品を保存するために博物館相当の収蔵庫や展示室を備えているんだそうです。これらも機会を狙って見に来たいです。
いかがでしたでしょうか。地域の古墳時代前期を代表する巨大前方後円墳、白石稲荷山古墳。
丘陵頂部に立地するため、丘陵裾から眺めれば大層立派な首長墓がそこに聳えているように見えます。古代から意識されたのでしょう、この視覚効果は現在もそのままです。
さて、ここは群馬、古墳王国。ここを見たら次はあそこの古墳だって見に行きたい、というくらい古墳がいっぱいあります。
というわけで次回は近所の別の大古墳を紹介します。
-----------
白石稲荷山古墳(平成5年11月・国指定史跡 群馬県藤岡市白石)
白石稲荷山古墳は群馬県藤岡市内を流れる2つの河川、鏑川と鮎川が合流する地点に挟まれるように位置する丘陵が鮎川に面する高台に位置します。3段築成の前方後円墳で、全長155m、前方部幅55m、後円部径は90mあり、高さは後円部で13.5m、前方部は6mあります。
築造年代は4世紀末から5世紀初頭と考えられています。昭和8(1933)年に発掘調査が行われ、2基の竪穴式礫槨が検出され、鏡や直刀、石製模造品が発見されました。また円筒埴輪、形象埴輪が出土しています。昭和62、63(1985、1986)年には範囲確認調査が行われ、北側に隣接する盛土が2基の陪塚であることがわかって十二天塚古墳、十二天塚北古墳と命名されました。
古墳時代前期の大型前方後円墳として貴重なため、国指定史跡に指定されています。
地域に広がる白石古墳群の主墳であり、同じ丘陵上の北方には皇子塚古墳、平井一号墳などが存在します。
ブログが気に入ったらクリックをお願いします