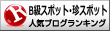前回、埼玉県熊谷市にある上円下方墳・宮塚古墳を紹介しました。
しかしそちらの古墳、十分な調査は行われていないので墳形が確定しているわけではない、ということも前回説明させていただきました。
実は、埼玉県内にはもう一か所、上円下方墳があります。今回はそこを訪ねます。
それは、川越市にある山王塚古墳。
今のところ、国指定史跡ではありません。文化財指定は受けていまして、川越市指定史跡となっています。
しかし、発掘調査が行われて上円下方形であることが確定しているうえ、築造方法や主体部の検出など重要な発見があったことから、いずれ国から文化財指定を受けることと思われます。
国指定史跡となるのが楽しみです。現状で一度見ておこうと思い、訪ねてみました。
山王塚古墳(南東から)
近所に駐車スペースはありません。住宅街の狭い道を入っていった先に古墳があるので、公共交通機関を使うことをお勧めします。西武鉄道新宿線の南大塚駅が一番近いですが、歩くと30分ほどかかります。
実は、これ以前に一度、発掘調査が行われていた時に現地説明会に来ました。幼かった息子の面倒を見るついでに訪ねたのですが、息子はあまり興味を示さなかったのが悲しかったです。大きな穴ばっかりでつまらなさそうでした。
その時は南西側の周濠跡の調査区を見ました。
その息子もすっかり大きくなり、「父ちゃんの見たいものって、タダの穴とかばっかり」といって、母親同様、決して私に付き合ってくれなくなりました(泣)。
東側から
鬱蒼とした森になっていて、昼でも薄暗く少し不気味です。
南側は住宅街に接していて視界を遮るものが多く、全体が見渡せません。
東側は開けていて見渡すことができます。ただ、私有地らしいのであまり長い時間滞在するのはお勧めしません。
写真だけ取らせてもらって、早々に退散しました。
古墳が大きすぎて、通常のカメラでは全景を納めることができませんでした。
墳丘上には山王社が祀られていて、石祠があります。その参道が南側から続いています。
そこから古墳に登ることができます。
南側から
上の写真では、鳥居の手前の平坦地が下方部上面になります。
この古墳は下方部の高さがそれほどなく、1m前後しかありません。とても低いです。
ただ、周囲からは周濠が見つかっていて、ほぼ正方形に区切られていることは確認されています。
下方部の高まり(山王社参道の左手側)
しかもこの古墳では、下方部の周縁部に土塁状の高まりが築かれていることまで確認されているのです。
こんな施設は他の古墳で見たことがありません。
下方部周縁の土塁状の高まり(写真中央から右方にのびる高まり)
発掘では上円部を円丘状に盛り上げ、この土塁状周縁部を造ってからその中に土を入れて鳴らし、下方部の上面を平坦に仕上げていることが明らかになっています。
下方部の外縁を決めるための土留めとして築かれたんでしょうね。こんな構築方法を取っていたなんて、合理的でおもしろいです。
下方部の角もハッキリとわかりました。
下方部の角(南東側)
いよいよ上円部を見てみましょう。
円墳状の盛り上がりが見えますでしょうか?
写真で撮ると雑木ばかりで古墳がよくわかりませんが…
上円部(西から)
山王社の参道と上円部
しかし現地では、大きな円丘を見ることができます。
上円部からは横穴式石室の残骸が発見されました。基床部と壁面の一部が出土しています。
出土位置はちょうど山王社の石祠とそこに続く参道の真下に当たります。
墳丘で、参道の部分が少し凹んでいるのは石室があったからなのですね。
山王社
そして墳頂には山王社が今もお祀りされています。
この真下が石室の玄室に当たるようです。
信仰を重視して、石祠の真下まで掘り下げることはしなかったとのこと。
でも、主体部が確認されたのは大きな成果の一つです。
北側の堀跡
北側まで周り込んでみました。
現地では濠跡が墳丘裾に続いている様子がわかったのですが、写真にすると灌木に遮られて、わかりにくいですね。
発掘調査で7世紀中頃に築かれたと分かった山王塚古墳、周濠も確認されてその規模が確定しました。
下方部の一辺はおよそ56m~59m、上円部直径が約37m、高さ約5mです。この規模は上円下方墳としては日本最大級です。
しかも、上円下方墳は畿内の天皇や豪族クラスの墓制として発生した説があるのですが、畿内より東日本の方がその数が多いのです。不思議じゃありませんか?
今後の研究においても、この山王塚古墳は重要なポジションを占めることになりそうです。早く国指定にならないかな…
-----------
山王塚古墳(昭和31年5月・川越市指定史跡 埼玉県川越市大塚一丁目・他)
山王塚古墳は埼玉県川越市にある南大塚古墳群の主墳とされる巨大な古墳です。上円下方墳といわれる特殊な墳形であることが明らかになりました。この墳形は畿内地方では有力豪族や天皇に連なる一族の墓制と見られていることから注目されています。
5回に渡る確認調査で、版築工法や掘込地業といった当時最先端の土木技術で構築されたこと、上円部を築いてから下方部を整形していること、主体部は上円部に横穴式石室があったこと(盗掘で破壊)、築造年代が7世紀中頃であることが明らかになりました。
実態がよくわかっていない上円下方墳の一例として重要であり、国指定史跡ではありませんが今後指定を目指しているとのことなので、この度訪問しました。
参考文献:
『川越市立博物館 第46回企画展 山王塚古墳 ー上円下方墳の謎に迫るー』川越市立博物館・編、川越市立博物館(2018)
ブログが気に入ったらクリックをお願いします