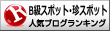『建郡1300周年』に沸く旧高麗郡の中心地、埼玉県日高市の高麗郷を訪ねました。
前回までに高麗村石器時代住居跡や聖天院勝楽寺の梵鐘を訪ねましたが、いよいよ高麗郡建郡時に指導的役割を果たした高麗王若光を祭神とする高麗神社をお参りしました。
しかし私にとっては、神社へのお参りも重要ですが、むしろその裏手にある高麗家住宅を訪ねることの方が心が躍るのです。
高麗家住宅は、高麗神社の宮司である高麗家の住宅だった古民家です。もちろん、私の食指を動かすのはその古民家が重要文化財に指定されているからということもありますが、高麗家は特に古式を残している民家だから、ということもあります。
まずは、高麗神社へご挨拶がてら、お参りしましょう。
高麗神社は聖天院の東方に鎮座していて、出世の神様として知られています。
そのきっかけとして若槻礼次郎や浜口雄幸などが参拝した後、いずれも総理大臣にまでなったことから有名になったそうで、今でも境内の参道脇に、若槻礼次郎が奉納した樹が成長した姿を見せています。
まあ、この方々が大臣になった当時の歴史を見れば、この人たちがこの神社を参拝した理由はうっすらとわかる気がします。
私も何度もお参りしていますが、ちっとも出世しません。
だから、「高麗神社にお参りすれば出世する」のではなく、「出世する人が高麗神社にお参りに来た」わけで、その理由は世界大戦に突入する前夜の昭和初期の時代背景が大きい、ということなんでしょう。
高麗神社
初詣の時期などには大勢の参拝客が押しかけますが、普段はこのように山懐に抱かれた、広々としてひっそりとした神社です。
お参りするだけで、とても心が落ち着きます。
高麗神社境内
それでは、神社の裏手にある高麗家住宅を訪ねましょう。
現在の高麗さんは新しいお宅を建てて、やや離れた場所にお住まいです。古民家の方は、晴れた日なら雨戸や扉を開け放ち、内部まで見学できる便が図られています(天候が悪い時は開けないそうです)。
無料で見学できるのでお勧めなのですが、参拝後にここまで来る参拝客はあまりおらず、穴場スポットとなっています。
高麗家住宅
内部は座敷に上がっての見学はできませんが、ドマまでなら立ち入って見学できます。
なお、部屋の名称は文献等に従ってカタカナで表記します。
外観ばかり見ていても古民家の良さはわかりません。とにかく、ドマへ入ってみましょう。
ドマ
ドマへ入ってきました。
煮炊きをするためのカマドが見えます。右手には古い農具も展示されていました。
ここで、ちょっと頭の上を見てみましょう。
ドマの屋根裏
私は古民家を見るおもしろさは、小屋組みのダイナミックな組み方を見ることにあると思っています。
いかがですか?ドマの屋根裏を見上げれば、伐採した木のうねりをそのまま利用したような巨大な梁が見て取れます。
その曲線が巨大な屋根の重量をうまく受け止めているところにダイナミックさと曲線の美を感じます。
ドマからオモテザシキ、カッテを見る(オモテザシキの壁に押板が見える)
ドマから上がったところにオモテザシキがあり、家族の集まる場所となっています。
この部屋の壁には押板といわれる、平面図で見ると壁が一段奥へ引っ込んだ場所が設けられています。この押板が重要でして…。
なんと、この押板こそ現在の住宅にもよく見られる「床の間」の原形だとされています。
この押板の存在こそ、私が高麗家住宅に心惹かれる大きな理由なのです。
この住宅の古さを伺わせるアイテムなのですから。
カッテ
カッテは今でいうダイニングでしょうか。ここには囲炉裏があります。
そして、写真には写っていませんが、この奥に部屋が1間あります。
このお宅は四間取りの構造をしています。これは比較的、新しい民家の特徴です(それより古い民家は三間取り)。
オモテザシキ
前庭側からオモテザシキを見ました。
押板があり、その上に神棚があります。右手の糸車の辺りに、畳で塞がれていますがもう一つ囲炉裏があります。
そしてオモテザシキの天井を見ると…。
オモテザシキの天井
簀の子のようなもので屋根裏を隠すように、簡単な天井が設けられていました。
これを下の写真のオクの天井と比較してみると、大きな違いが分かります。
オク
オクにも押板のような施設がありますが、これは「トコ」とされています。床の間ですね。この家には、古い押板と新しい床の間の両方が設けられていました。
そして天井ですが、板が貼られたきちんとした天井があります。
こちらは客間だったのだろうと想像されます。ただ、客間といえばその前庭側に式台のようなお客様用の玄関があったりするものなのですが、この民家にはありません。
そこがこの家がお客を頻繁に迎えるような家ではないことを表わしています。民家とはいえ、やはり社家は農家とは少々違うのでしょうね。
主屋裏手
そして主屋の裏手に回ると、全く窓や入口がないことがわかります。
これも特徴的で、おそらく山を背にして建っているので、獣などの侵入に備えた造りなのではないでしょうか。
埼玉県内の古民家でも、特に古いとされているお宅では、軒が低く窓が少ない構造をしてるものが見られます。
これは開拓期の武蔵野原野で、まだシカやイノシシなどの獣が多かった頃にそれらの獣の襲撃を防ぐための構造だったとされています。
こうしてみると、高麗家住宅が古式から新式へ移行する過程の民家と位置付けることができる、結構ユニークな住宅であることがお分かりいただけたと思います。
高麗家住宅を紹介したいくつかの文献では全国的にも珍しい「社家」の遺例と記述されていますが、あまり社家らしい特徴は見られません。民家としての住宅の変遷過程の上で評価するほうが妥当ではないでしょうか。
-----------
高麗家住宅(昭和46年6月・重要文化財 埼玉県日高市大字新堀)
高麗家住宅は、高麗郡建郡の父・高麗王若光を祖伸として祀った高麗神社の宮司を代々務める高麗氏の住宅でした。
平面図的には、ドマと前後に2列並ぶ2室からなる四間取りの型式で、屋根の架構形式は上屋柱と側柱を梁でつなぎ、梁上に立てた束で上屋梁を支える、関東でよく見られる形式です。
各部屋境に一間ごとに柱が建つ点や、押板の存在などに古式が見られる一方、オモテザシキやドマで上屋柱の省略が見られ、前庭側が開放的な点などに発達した点が見られます。
建築年代は不明で、慶長年間(1596-1615)の建築との伝承もありますが、これらを総合的に判断して17世紀後半の建築と見られています。
参考文献:
『関東の住まい』 INAX ALBUM 37・日本列島民家の旅⑧関東、田中文男・著、INAX出版(1996)
『さいたまの名宝』、埼玉県立博物館・編、平凡社(1991)
ブログが気に入ったらクリックをお願いします