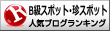当ブログをご覧いただいている皆様、いつもありがとうございます。
おかげさまで記事の数が70を超え、ブログに訪れていただいている方々の数も徐々に増えてきています。
私の拙い知識も、以前より充実する日々でして。
皆様に感謝しています。
今後ともよろしくお願いいたします。
さて、今回訪ねたのは福島県郡山市にある旧福島県尋常中学校本館です。
福島県尋常中学校の後継である福島県立安積高校の敷地内に今でも所在し、現在では安積歴史博物館として一般公開されています。
が、実はここ、全国で唯一、昔のままの位置にある学校建築なんだとか。
旧福島県尋常中学校本館
そんなこともよく知らず、明治時代の校舎が残る建物として聞いていたのでノコノコと出かけて行きました。
建物の全景(東から)
博物館はJR郡山駅から西へ約3.5㎞ほどのところにあります。安積高校の校門がそのまま入り口でした。
敷地内には人が全く見当たらなかったので何も気にせずに入館したのですが、実はこの日、高校の入学式だったのです。
後で気付いてこっ恥ずかしい思いをすることについては後ほど。
中央玄関
いわゆる明治時代の初期に見られる、洋風を模した日本建築“擬洋風建築”の建物です。
このブログを見返すと、ちょうど一年前にも擬洋風建築の“旧開智学校校舎”を紹介していたんですね。そちらもぜひ、ご覧ください。
擬洋風建築として初の国宝となった開智学校と、昔から位置を変えずに立つ福島県尋常中学校。
比較してみると面白いでしょう。
玄関は平面八角形で、八角形の柱を建てて二階にはベランダがあります。
柱や上部の飾り板、安山岩を使った腰壁などに洋風の意匠が見られます。
屋根の下に見える軒蛇腹などは擬洋風建築に見られる典型的な洋風意匠ですね。
それでいて一方で屋根は瓦葺。降棟の先には鬼瓦もあり、和の雰囲気を持っています。
1階廊下
中は装飾もほとんどなく、質素な印象です。そのあたりは開智学校校舎と随分違います。
こちらの方がその意味では学校校舎らしいですね。
上の写真の廊下なんか、今にも生徒たちが駆けて来そうです。
実際に授業を行った教室(2階)
教室の様子も、私が通った学校と大した違いはないように見えます。こういうところはあまり変化しないものなんでしょうか?
ちなみに、私が通った高校は昭和もど真ん中、昭和50(1975)年開校です。
階段
階段はちょっとシャレていますね。手すりもそうですが、上部の飾り板には雲をデザインしたような彫刻があります。
実はこの学校、歴史が古いだけあって多くの著名な方々を輩出しているそうです。
例えば、
高山樗牛
明治時代の思想家、評論家。福島尋常中学は中退したようです。
朝川貫一
歴史学者。『日本之禍機』で日本の敗戦を予想、その後の日本の歩みまで予言していて、今まさにその通りに歴史が進んでいるようです。日本人で初めて、アメリカのイェール大学教授にもなりました。安積歴史博物館には『朝川記念室』が設けられて、その業績が広く紹介されていました。そのくらいすごい業績を残した卒業生らしいです。
玄侑宗久
僧侶であり、小説家。図書館でよくお名前をお見掛けします。しかし著作を読んだことがなく詳しいことは知りません。最もそれは紹介した方すべてに当てはまりますが。今度著作を読ませていただきます。
田母神俊雄
元航空自衛隊幕僚長。この方もそうだったんですね。『論文問題』で一時、新聞の紙面を賑わせていました。
etc.…
超名門校なんじゃないですか、この高校…
これらの方々については歴史博物館の一室で、その業績と共に紹介されていました。
2階ベランダ(内部から)
ベランダから見た外の風景は涼しげで、春先の風を爽やかに感じられました。
2階講堂
パイプ椅子が並んでいます。その理由は後に知ることになりました。
シャンデリアや壁のランプがまた洋風で、文明開化の時代に建てられた建物であることを知らしめています。
講堂にある壁上のランプ
歴史博物館として気軽に見学できる、明治期の学校建築・旧福島県尋常中学校本館。
2月には、福島県沖を震源とした大きな地震があり、我が家のある埼玉でも大きな揺れに見舞われました。
その地震でこの校舎にも壁にヒビが入る被害があり、その補修が終わって4月初頭から再公開されたばかりでした。
10年前の東日本大震災の時には壁が割れ、屋根瓦が落ち、建物が歪む被害があったそうで、耐震補強工事も施されてたくましく復活しました。
これからも末永く、近代建築の遺産としてその姿をとどめ伝えてほしいものです。
な・の・で・す・が。
「現役で活躍中」とは、博物館として公開されていることもそうなのですが、実は学校の施設として今でも使われているようなんです。
見学を終えていざ立ち去ろうとしたとき、大勢の新入生とその保護者らしき服装の人々が、ぞろぞろと校門を入ってくるではありませんか。
「ええっ!」
何と、この日は安積高校の入学式当日だったのです。
講堂のパイプ椅子は、入学式の後で新入生ガイダンスをここで行なうために並べてあったのです。
校門前には新入生とその保護者が列をなすに決まっています。
「こんな日によく開館していたなぁ…」
校門は博物館の入り口にもなっているのに、この人混みをかき分けて車で退出しなくてはいけません。
間違えて新入生と衝突なんぞしようものなら、ハレの日を血に染めることになりかねません。
しかも一部の親御さんは、我が子がそんな名門校に入ったのがやはりうれしいのでしょう、歴史ある建物を背景にお子さんと記念写真撮影に興じているではありませんか。
そんな前を車で横切るのは本当に気まずい…
交通誘導をしている先生や入学式に向かう若者や親御さんに頭を下げ下げ、バツの悪い思いをしながら建物を後にしたのでした。
--------
旧福島県尋常中学校本館(昭和52年6月・重要文化財 福島県郡山市開成5)
現在の福島県郡山市桑野・開成地区周辺には「大槻原」と呼ばれる原野が広がっていました。この地の開拓が始まったのは明治初期の話です。これを「安積開拓事業」と呼びます。
開拓が進んで人口が増え始めた頃、もともと福島市に建てられていた尋常中学校の移転要望が県議会に提出され、実現しました。
現在の位置に開校したのは明治22(1889)年、建物もその頃のものと思われます。設計者などの詳しいことはわかっていませんが、基礎を安山岩で作り、正面玄関のデザインや軒蛇腹、小屋組や瓦葺きの屋根には典型的な擬洋風建築の特徴が残っています。建立当初と同位置に残る学校建築としては日本唯一とされています。
ブログが気に入ったらクリックをお願いします