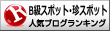最近訪ねた群馬県内の遺跡を紹介しています。
昨年(2020年)3月、高崎市にある綿貫観音山古墳から出土した出土品一括を国宝指定するよう答申がありました。
その報を私は、埼玉県の自宅で聞いていました。
昔、綿貫観音山古墳を訪ねたことがある私はその報を聞き、
「それほどの価値が認められたんだ、これは朗報だ。」
と喜びました。
それと同時に、出土品を目にしたことがなかった私は、
「文化庁保管と聞いているので簡単に見ることはできないだろうな---。」
と、新たな国宝をその目にすることは諦めていました。
しかし、そこへ更なる朗報が。
群馬県立歴史博物館において第101回企画展『国宝決定記念 綿貫観音山古墳のすべて』が開催されていることを耳にしたのです。
早速、綿貫観音山古墳を再訪し、群馬県立歴史博物館にも足を運びました。
もうとっくに終わってしまった企画展で申し訳ありませんが、これはその時の訪問録です。
まずは、朝早く綿貫観音山古墳へ。
県道から標識に従って住宅街へ入ります。
「こんなところに古墳があるのか?」と思ったら突然、目の前に緑の山が出現します。
芝生が葺かれた巨大な山。それが綿貫観音山古墳の現在の姿です。
綿貫観音山古墳(後円部側から見た全景)
わざわざ早朝に訪ねた理由、それは訪問客も、犬の散歩をする近所の人もまだ少ない時間に、じっくりと古墳を堪能するためでした。
中堤体も、内堀の跡(砂利が敷かれている)もしっかりと整備されていました。
そして墳丘へ。
二段築成、前方部と後円部の高さがほぼ同じ、もう典型的、教科書的な後期古墳です。
嬉しくなりますね。
横穴式石室は後円部にあります。
現在は時節柄、中に入れませんが、普段はボランティアの案内員さんがいて、石室内部まで案内してくれます。
横穴式石室の入口
格子戸の外から中を覗くことはできますので、今回はこれでガマンです。
早くコロナ禍、落ち着かないかな。
横穴式石室
角閃石安山岩の切石積みです。
人一人立って入ることができるのですから、相当巨大な室内だと思います。実際に入って体感したかったです。
でも多胡碑や山上古墳を見た後では、側壁や奥壁の石の切り方は粗いように思えます。
それが100年という時期差のせいなのかはわかりません。
それでもここまでできるのですから、技術集団の差ではなく、時期の差なのだろうと思います。
出土品が発見された時は、天井石が落ちていたそうです。
たしかに、落ちたらひとたまりもなさそうな、巨大な天井石です。
たいていの横穴式石室内は荒らされているものなのに、副葬品が失われることがなかったのはそのおかげだとか。
粗く切った石を積み上げた側壁は、巨大な天井石と墳丘の土の重さを支え切ることができなかったのです。
結構早くに崩れたのでしょうね。
しかし、そのおかげで大陸系の文化を伝える貴重な大量の副葬品が守られたのですから、むしろ不幸が転じての幸運に感謝したいくらいです。
後円部頂から前方部を見る
遠くに赤城の山が望めます。赤城山や榛名山は、高崎や前橋の市内ならどこからでも望めます。
前に赤城、左に榛名の両山を眺望すると、
「ああ今、俺は群馬にいるんだなぁ。」
との思いが心の底から湧き上がってきます。
だからきっと、赤城山や榛名山、そしてもう一つの妙義山は「上毛三山」として群馬県民の心に刻まれているんでしょうね。
その赤城山が前方部の先に臨めることを考えると、もしかしたら古墳築造の際の設計基準に選んでいたのかもしれません。
前方部頂から後円部を見る
巨大さが伝わりますか?写真ではイマイチですね。
しかし登ったり降りたり、墳裾を一周したり第2段目を周ったりしていれば息が切れてきます。
それくらい大きな古墳です。
次回、続いては、いよいよ出土品とのご対面です。
--------
観音山古墳(綿貫観音山古墳)(昭和48年4月・国指定史跡 群馬県高崎市綿貫町)
綿貫観音山古墳は利根川の支流・烏川に流入する井野川の右岸に位置し、周辺にはいくつかの前方後円墳があって綿貫古墳群を形成します。当古墳はその中で最大であり、最後に築かれました。6世紀後半の築造で、石室内から大量の副葬品が出土しています。
墳丘は全長約97m、主軸を北北西から南南東に取り、前方部は北方をむいています。後円部には巨大な横穴式石室が南西方向に開口しています。玄室長が羨道長に対して極端に長い羽子板型の平面形をしていて石室長は約12.6m、玄室だけの長さは約8.3m、幅は奥壁で約3.9mもあります。壁面には県内で採石された角閃石安山岩を粗く加工し互目に積んでいますが、羨道の入り口付近は河原石を乱石積みにして築いています。天井石は多胡碑などに使われた牛伏砂岩製の巨石で、玄室は3石、羨道は2石で覆っており、その大きさが伝わるかと思います。
副葬品は大変豪華なもので、技術や装飾の面から朝鮮半島などとのつながりが伺われるものが多数含まれています。また武具や馬具が多数を占めていることからその学術性の高さが評価され、先ごろ国宝に指定されることが決定しました。
参考文献:
『綿貫観音山古墳のすべて』国宝決定記念 第101回企画展、群馬県立博物館(2020)
ブログが気に入ったらクリックをお願いします