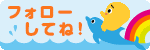読書シリーズの第二弾になります。今回は島崎藤村の「夜明け前」を選びました。思えば、前回の「武田勝頼」は甲斐武田家の滅亡を書いた小説でしたが、今回は見方によれば江戸幕府徳川家の滅亡の話とも考えられます。それで、この小説を選んだという理由もありますが...この本の出版は昭和48年となっていました。全体的に日焼けして変色してはいますが、その度合いは若干の程度なので読むのに問題はありません。どうやら誰も一度も読んでいないようです。この本は出版されてから今までどのような変遷を辿って来たのか想像もできませんが、誰かに一度は読まれたほうがこの本にとっても幸せではないかとも思うのです。
今回は、万福寺の話が出て来ます。この寺院は青山家との関係も深く、また今後の半蔵の生涯にも影響して来ることになります。
1-2-1 「万福寺」
十曲峠の上にある新茶屋には出迎えのものが集まっています。今度いよいよ京都本山の許しを得、僧智現の名も松雲と改めて、馬籠万福寺の跡を継ごうとする新住職があります。山里へは旧暦二月末の雨の来るころで、年も安政元年と改まりました。
「きょうはご苦労さま」
出迎えの人たちに声をかけて、本陣の半蔵もそこへ一緒になります。馬籠の百姓総代とも言うべき組頭庄兵衛は茶屋を出たり入ったりして、和尚の一行を待ち受けています。
間もなく、半蔵のあとを追って、伏見屋の鶴松が馬籠の宿の方からやって来ます。小雨は降ったり休んだりしています。しばらく半蔵は峠の上にいて、学友の香蔵や景蔵の住む美濃の盆地の方に思いを馳せます。半蔵らは中津川の宮川寛斎に就いた弟子であり、寛斎はまた平田派の国学者です。日ごろ教えられることは、暗い中世の否定であり、漢学び風の因習からも仏の道で教えるような物の見方からも離れよということでした。こんな本陣の子息が待つとも知らずに、松雲の一行は十曲峠の険しい坂路を登って来て、予定の時刻よりおくれて峠の茶屋に着きました。
松雲は、出迎えの人たちの予想に反してそれほど旅窶れのした様子もありません。笠の紐をといて、半蔵にも松兵衛たちの前にもお辞儀しました。万福寺は小高い山の上にあります。諸国を遍歴して来た眼でこの境内を見ると、これが松雲には馬籠の万福寺であったかと思われるほど小さく、松雲は周囲を見廻します。数えて来ると、何から手を着けていいかも分からないほど種々雑多なことが新住職としての彼を待っています。まず自分で庭の鐘楼に出て、十八声の大鐘を撞くことだと考えるのでした。
翌朝は雨もあがりました。松雲は夜の引き明けに床を離れて、山から来る冷たい清水に顔を洗いました。まだ本道の前の柊も暗い中、朝の空気の静かさを破って、澄んだ大鐘の音が起こります。力を籠めた松雲の撞き鳴らす音でした。
1-2-2 「吉田松陰、佐久間象山」
ある朝、半蔵は妻の側に眼をさまして、街道を通る人馬の物音を聞きつけ、かねて噂のあった尾張藩主の江戸出府がいよいよ実現されることを知ります。
前の六月に江戸湾を驚かしたアメリカの異国船は、また正月からあの沖合いにかかっているころで、今度は四隻の軍艦を八、九隻に増して来て、武力にも訴えかねまじき勢いで、幕府に開港を迫っているとの噂すら伝わっています。その日、半蔵は店座敷に籠って、この深い山の中に住むさみしさの前に頭を垂れました。
「こんな山の中にばかり引っ込んでいると、何だか俺は気でも違いそうだ。みんな、のんきなことを言ってるが、そんな時世じゃない」
と考えます。
新しい機運は動きつつありました。長州萩の人、吉田松陰は当時の厳禁たる異国への密航を企てて失敗し、信州松代の人、佐久間象山はその件に連座して獄に下ったとの噂すらあります。遠い江戸湾のかなたには、実に八、九艘もの黒船が来てあの沖合いにかかっていることを胸に描いて見ると、半蔵は尾張藩主の出府も容易でないと思うのでした。
アメリカ艦隊はその後、翌年の正月にもさらに隻数を増して来航していたのですね。幕府は吉田松陰や佐久間象山らを捕えて投獄します。後に言う安政の大獄の始まりです。
 | 夜明け前 01 第一部上 0円 Amazon |