今回紹介する本は、児島襄さんの「指揮官(下)」です。前回は「指揮官(上)」 の感想を記事にしました。下巻では13人の第二次世界大戦において名を残している指揮官を取り上げて、それぞれが直面した事態や作戦における指揮官ぶりからその人物像を描いた本です。
- 指揮官 (文春文庫)/文藝春秋

- ¥価格不明
- Amazon.co.jp
下巻は外国の指揮官、指導者を選んでおり、日本人にとっては上巻に比べると馴染みの薄い名前が並んでいます。とは言っても、最初に挙げられているのは「ダグラス・A・マッカーサー」ですし、インパール作戦において日本軍を崩壊に導いた(自壊しただけ?)「オート・C・ウィンゲート」、ミッドウェイ海戦で大方の下馬評をひっくり返して米海軍に大勝利をもたらした「レイモンド・C・スプルーアンス」など大物が並んでいます。
今回取り上げたいのは、この本の最後に出ている「アドルフ・ヒトラー」です。最後の最後に第二次世界大戦としては超在り来たりな人物を挙げて今更何だろうなと思ったのですが、読んでみるとこれまで知らなかったヒトラーの姿を描いていて、この本の最後に挙げてしかるべきという感想を持ちました。
それは、大戦の末期、ヒトラーは<女性化>していたのではないか、そしてその<女性化>の裏には大戦中の米国諜報機関OSS(戦略諜報局)が暗躍していたのだ、という内容でヒトラーを分析し、描いているのです。
心理学的に見ると、ヒトラーには女性的性格傾向のほうが男性的それよりも多く認められる、というところから始まります。ヒトラーが政権を握るために採用した戦術の中で目立つのは演説と演出ですが、それはお喋り好きとお芝居性・・・これはヒステリー性格における自己顕示性の現われですが、いわずと知れた女性の特徴である訳です(現代ではこのような書きかたは女性を卑下することにつながり、よろしくないことですが、この本が出版されたのが1974年ということで文章をそのまま引用します)。
OSSは、ヒトラーに強力な女性ホルモンを服用させる計画を考えます。女性っぽいヒトラーであれば、女性ホルモンによって<女性化>した場合、その結果として感情の激動、疑い深さ、外罪性向(他人に責任を転嫁する)、不決断、被害意識、受動的行動など、女性的な性向が促進され、心理は極端に不安定になり、ナチス・ドイツの戦争指導は支離滅裂になるに違いない、と踏んだのです。
事実、ヒトラーは戦争の後半になると左手・左足が震え出し、左手の震えを隠すために右手で押さえつけなければならなくなっています。また、1943年以後は公衆の前に姿を現すことを嫌い、特異な演説も滅多にしなくなりました。ヒトラーは、記録に残る演説などの映像を見ても分かるとおり、極めて主観的、感情的な人物ですが、自己顕示欲に富む人間が急激に隠遁生活に没入するにはそれだけの理由がなければなりません。ノルマンディー上陸作戦後は、さらに被害意識、不信感、外罪性向などの<女性的>性格性向が強化している感があります。
ヒトラーの最後は、恋人のエバを総統官邸の地下防空壕に呼び、結婚式を挙げた後、ピストルを口中に発射して自殺しますが、残された遺書には「...わたしはひたすらわが国への愛情と真心をもって活動し続けてきたのに、戦争中に不忠と裏切りのために勝利に導くことができなかった...」と、自分は悪くない、悪いのはユダヤ人と将軍たちだ、といった憎悪と不信と責任転嫁と混乱に満ちたものでした。
戦後、OSSはこの女性ホルモンによる<女性化>計画は失敗したと宣言しているのですが、OSSの工作だとするとその成果があまりにも強烈で範囲が広大過ぎる(第二次大戦では軍人、ユダヤ人、一般市民を入れると死者だけで3,000万人に達すると推定されています)ので、敢て失敗したと記録しているのではないか、というのですがどうでしょう。
- わが闘争(上)―民族主義的世界観(角川文庫)/角川書店
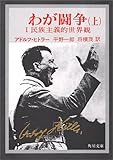
- ¥864
- Amazon.co.jp
- わが闘争(下)―国家社会主義運動(角川文庫)/角川書店
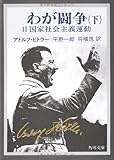
- ¥778
- Amazon.co.jp

