最近読んだ小説 - 塩野七生 「海の都の物語1、2」 -
昨年10月にキリスト教諸国とイスラム教トルコ帝国との戦いを描いた塩野七生さんの三部作である
を紹介しました。今回は同じ塩野さんの作品で、海洋都市国家ヴェネツィア共和国の一千年にわたる歴史を描いた「海の都の物語」です。文庫版は6巻から成っており、紹介の1回目は1、2巻についてです。
- 海の都の物語〈1〉―ヴェネツィア共和国の一千年 (新潮文庫)/塩野 七生

- ¥420
- Amazon.co.jp
1巻目は「第一話 ヴェネツィア誕生」「第二話 海へ!」「第三話 第四次十字軍」という題目で、アッティラ率いるフン族が攻めてきて、イタリア北東に位置するヴェネト地方の人々がイタリア半島の付け根の東側に位置するヴェネツィアに逃げ込んでくるところから始まります。時は西暦452年、その24年後に西ローマ帝国は滅亡します。ヴェネツィアは、現在は美しい都の姿をしていますが、当時は干潮時にところどころ露出している沼沢地帯で、葦が一面に生い茂るだけの干潟でしかありませんでした。フン族がそこまでは攻めてこないほど、人の住む場所としては最悪の条件の場所に逃げ込んで命をつないだ、というわけです。
ここからヴェネツィアの人々は船を操り、交易で生計を立てながら、海へ出て東地中海や黒海を舞台に商人として活躍し、次第に富を蓄えてヴェネツィアを海洋都市国家にまで発展させます。一千年もの長きにわたって地中海の女王として君臨できた理由は、合理的で現実的な考え方に基づき、効率を第一に国家の利益を追求していくという現実主義の精神でした。その極端な例が、第四次十字軍に表れています。十字軍にも拘わらず、ザーラやコンスタンティノープルの同じキリスト教徒を攻撃した第四次十字軍は、その悪の根元がヴェネツィアであると評価されています。しかしヴェネツィアからすると、十字軍の置かれた状況から最適解を提案し、締結した契約を実直に実行したに過ぎなのですが...
- 海の都の物語〈2〉―ヴェネツィア共和国の一千年 (新潮文庫)/塩野 七生
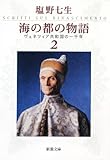
- ¥380
- Amazon.co.jp
- 2巻目は「第四話 ヴェニスの商人」「第五話 政治の技術」という題目で、ヴェネツィア人の商人の生き方と政治手法が語られています。ヴェネツィアの商人として日本で有名なのはマルコ・ポーロです。ヴェネツィアの商人は20年ぐらい海外に出ていったまま帰国しないというのは珍しいことではなかったそうです。ただマルコ・ポーロのように北京まで行き着き、宮廷の役人になったりしたのは西欧人として最初でした。ヴェネツィアは唯一交易による利益で成り立つ国家でしたので、マルコ・ポーロなど活躍した高名な商人には優遇した制度を取っていたと考えがちですが、どちらかというと、一般の商人を基準に置いて国家の進路や運営を決めていたそうです。国家の営みを表現する際、「統治」と「経営」という2つの言葉が思い浮かべた場合、ヴェネツィア人は国を「経営」するいう表現の方が当てはまります。ヴェネツィア共和国は現代の私企業の会社と同じように経営されました。経済の安定成長を重要視し、そのためには強力な行政指導を行使することもためらいませんでした。まさに「ヴェネツィア株式会社」という感じです。日本が「日の丸株式会社」と呼ばれていたことと似ているところがあるかも知れませんね。
- 最後に、なるほどと思ったことを1つ紹介します。当時の商人が扱っていたオリエントの貿易品として代表的な品物は香味料でした。これは中学校の歴史でも出てきますが、なぜ西欧人はそんなに香味料が欲しかったのか? 私は単なる珍品・贅沢品としてだと思っていたのですが、実は生肉を食べるための必需品だったのです。冷蔵庫のない当時は、肉を保存する方法は塩漬けか乾燥しかありません。臭味のない生肉を食べたくともそれはとても恵まれたことであり、肉の臭みを消し、味を良くするには香味料がなくてはならなかった訳です。なるほど、現代の生活の慣れてしまった私たちにはちょっと想像できないことですね。高校では世界史を専攻しなかったので、今さらながら世界史を勉強しておけばよかったなあと後悔しています。
-
今、3巻目を読んでいる最中ですので、読み終えたらまたこの続きをご紹介しようと思います。
