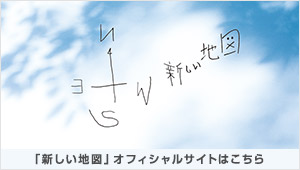橋倉藩の近習目付を勤める長沢圭史と団藤匠はともに齢六十七歳。本来一人の役職に二人いるのは、本家と分家から交代で藩主を出す――藩主が二人いる橋倉藩特有の事情によるものだった。だが、次期藩主の急逝を機に、百八十年に亘りつづいた藩主交代が終わりを迎えることに。これを機に、長らく二つの派閥に割れていた藩がひとつになり、橋倉藩にもようやく平和が訪れようとしていた。加齢による身体の衰え感じていた圭史は「今なら、近習目付は一人でもなんとかなる」と致仕願いを出す。その矢先、藩の重鎮が暗殺される。いったいなぜ――隠居した身でありながらも、圭史は独自に探索をはじめるが・・・・・・。
地味で渋い話ではあるが、それだけに味わい深い趣がある。
一語一語をおろそかにせぬよう、嚙みしめるように読み進める。
先を急いではならない。むしろときには後ろを振り返る。
「青山文平の本を読んだ」というレポートのとき、いつも何も語ることができない。
この小説を読み終えたとき、身体が震えた。
震撼させられた。
人が生きることの意味、誇りや矜持。
そのようなことが吾が身に突き刺さる。