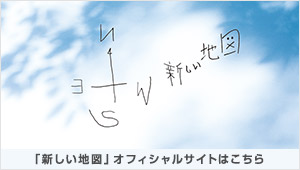この本の初読は、3年ほど前になるだろうか。
与謝蕪村と蕪村との交流ある人々の物語。
与謝蕪村といえば、俳人。あの
春の海ひねもすのたりのたりかな
の句で知られる。もっとも蕪村の名が世に広く知られるようになったのは明治になってからで、正岡子規が与謝蕪村を高く評価したからだという。これは後で知ったのであるが、今もなお、与謝蕪村の俳句そのものを知るわけではない。
小説に蕪村の句がさらりと出てくる。どの句も蕪村の口元からこぼれるようにさらりと詠まれる。暗喩を含ませつつ滑らかにして流れるような句である。
さて、ここで裏表紙
京に暮らし、二世夜半亭として世間に認められている与謝蕪村。弟子たちに囲まれて平穏に過ごす晩年の彼に小さな変化が……。祇園の妓女に惚れてしまったのだ。蕪村の一途な想いに友人の応挙や秋成、弟子たちは呆れるばかり。天明の京を舞台に繰り広げられる人間模様を淡やかに描いた傑作連作短編集。
そうだ、初読はいとも軽く読み飛ばしてオシマイだった。特に印象に残らなかった。その頃は、ともかく江戸期の俳人を題材とする小説を読んだ。俳句に関して必要最低限の知識を得たいと思っていたからである。
この小説の文章が、あたかも蕪村の句のようにさらりと軽い。とり上げる話が軽いわけではないが、さらさらと流れるような筆の運びである。しかしながら、描かれるのは宿命ともいうべき重い人生である。
それぞれの恋模様を軽妙洒脱な筆にのせる。これぞ名人芸なのではないか。心に深くしみいり、余韻を残した。
再読してよかった、一冊。
最終章『梅の陰』に与謝蕪村辞世の句が記される。
白梅にあくる夜ばかりとなりにけり