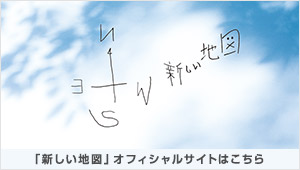梅雨だから雨が続くのは当たり前のこと、なかなか晴れ間がない。本棚に古木信子著「雨と晴れの間」が目に入る。これは梅雨の晴れ間かな。今がそのときだな。などと思って、本を手に取ってみた。
ブログに「書くな、読め」という記事をアップばかりでもあるし、せめて何なりと読んでみようかなという気にもなっていた。古木信子さんの作品を読むのも中断したままだったし…。本の帯を見ると、「雨と晴れの間」は熊日文学賞受賞後第一作のようだ。
「雨と晴れの間」は15の章で構成されている。章の終りのフレーズが秀逸で、次はどうなるのかと、中断することができずに、先へ先へと読み進めてしまう。例えば、
7章の終り
「毎日、当たり前のようにして暮らしているが、本当にそれでいいのかは分からない。ほろ酔いの邦子の中に桜が散る。」
え~、桜が散るって?邦子の中で何が起きたのかと次が気になってしまう。
8章の終り
「驚いて振り向いた邦子の姿勢が少し崩れ、男性の上着の襟に、前髪が触った。」
あ~、髪が触れてしまった~。
9章の終り
「今だったらこのまま付いて行けます。後だったら、行くことはありません。」
あちゃ~、行っちゃったよ~。
と、まぁ、このようにして読み進んでしまうのでした。ごく自然にディティールが積み重ねられているから、何の違和感もない。
梅雨の晴れ間のことかと思って読み始めたのに、雨も晴れも関係なくストーリーが展開していくから、何が「雨と晴れの間」なのかと気になって仕方がない。どこかにその訳が出てくるはずなんだけどと思いながら読み進めると、12章になって、やっと「雨と晴れの間」の話題が提供される。
ここまでくればもうあと少し、一気読みが約束されたようなものだ。まてまて、ここで急いてはならぬ、ここからがじっくりと味わうところだからな。そう言い聞かせるが、どうにも急いてしまう。
年齢も容姿も冴えない女性だけど、声としゃべりが妙に心に残ってしまうのだ。これって、とってもよく分かるというか、ん、誰かに似ていないか?ま、誰ということは控えておこうか。
「晴れでも雨でもない場所、その現実でない、ミストの空間のような境目」。そのようなことが、誰にでも訪れることがあるのだろうか。文学だなぁ~。