松田龍平を見るのは何度目だろうか。「舟を編む」はおもしろかった。今回も、何もしない感じがおもしろい。
いろいろ好きなシーンがあるが、特に好きなのが父親(柄本明)が指導している中学の吹奏楽部を指揮するところというか、そのあと。ドラムのリズムを変える。そうすると全員が乗ってくる。ロックぽくなる。父親の求めていた音楽になる。肺ガンで闘病中の父親は、それを携帯電話で聞いているのだが、大喜びだ。で、問題の、そのあと。家に帰ってきた松田龍平に、父親が「もっと近くへ来い」と手招きする。顔を近づける松田龍平の頭を柄本明がぱしっと叩く。「おまえ、やったじゃないか」。この、叩かれるために顔、ではなく、実は頭を近づけていく感じと、そのあと叩かれる感じがとてもいい。
頭を叩くのは怒りではなく、乱暴な祝福。
こういうことが松田龍平と柄本明の間で何度も何度もあったんだろうなあ、と感じさせる。「うれしいとき、おやじは頭を叩くんだよなあ」。それを知っていて、それを自然に誘う角度とスピードの近付き方。ちょっとうれしくて涙ぐみそうになる。
これと、少し似ているのが、最初の方の前田敦子とのからみ。松田龍平が家に帰ってくると、前田敦子が寝ている。眉間に皺を寄せて寝ている。その皺を松田龍平が指でそっと伸ばす。一瞬、前田敦子の顔が笑顔になるが、すぐに眉間に皺を寄せた顔になる。繰り返しているうちに、前田敦子が「うるさい」という感じで目を覚ます。怒る。それを見て松田龍平が笑う。前田敦子の肉体がどう動くかを知っていて、それを誘うように肉体で接している。
この怒りとも、親愛ともつかない感情を誘い出す「肉体感覚」が妙にいい感じなのである。そうだなあ。人間の感情なんて、ひとことではいえないし、あらわし方はひとつではないからなあ。
海辺で、柄本明のとなりに座り、おにぎりを食べながら、松田龍平が少し涙ぐむシーンもいい感じだ。
「台詞」が「意味」を語るシーンではなく、ただ「肉体」で演技するシーンがとてもいい。「肉体」そのものが感情になっている。
で。
この「肉体」の演技は、もちろん松田龍平だけではなく、柄本明もそうなのだが、エキストラの人たちとの演技ととてもよく融合している。
舞台は瀬戸内海(広島)の小さな島。(といっても、学校や病院がある大きさの島。)そこでは住民がたがいに知り合い。「肉体」をいつも見て暮らしている。遠くからでも歩き方を見ただけで誰が誰だがわかるような感じで暮らしている。いつも見ているので、ちょっとした肉体の動きで誰が誰であるかわかる感じ。そして、その「肉体がわかる」感じの「つきあい」がある。
うれしいとき、頭を叩く。人が眠っているとき皺を伸ばして遊ぶ(? からかう?)ことが許される「接触」がある。それが何とも温かい。この温かい感じは、ラストのクライマックスで爆発するのだが、そのシーンよりも、私は、柄本明が知り合いを呼んで家で宴会をするシーンが好きだなあ。松田龍平が連れてきた娘、前田敦子が妊娠していると知る。結婚し、孫ができる、と知って、喜んで知り合いに電話をかける。「宴会をやるぞ」。その呼びかけに知り合いが集まってきて、延々と宴会がつづく。その「飲み食い」のシーンが、とてもいい。演技(映画)ではなく、ほんとうに「宴会」になっている。
その「宴会」のシーンの、松田龍平が、また、とてもいいのだ。
柄本明と町民は長いつきあい。けれど松田龍平は長い間島を離れていて、町民(父親の仲間)とはそんなに親しいわけではない。だから、ちょっと「間」がある。松田龍平は「主役」だけれど、そのシーンをひっぱっていくのは(動かしているのは)、松田龍平ではなく、宴会を楽しむ町民。その「楽しみ」のなかに、戸惑いながら引き込まれていく。「自己主張」しないで、のみこまれていく。この「自己主張」のない感じが、すごい。
いっしょにいる人を、その人の感情を壊さない。
最初に「何もしない感じ」と書いたが、それはそばにいる人の「感情を壊さない」と言い換えた方がいいのだと、ここまで書いてきてわかった。そばにいるひとの感情が自然に動くのを支える、と言い直してもいいなあ。
外見は、金髪のモヒカンというアンバランスが、そうした動きをきわだたせている。
(ユナイテッドシネマキャナルシティ・スクリーン4、2016年04月13日)
*
「映画館に行こう」にご参加下さい。
映画館で見た映画(いま映画館で見ることのできる映画)に限定したレビューのサイトです。
https://www.facebook.com/groups/1512173462358822/
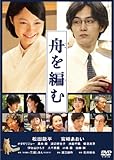 | 舟を編む 通常版 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| 松竹 |