監督 園子温 出演 國村隼、堤真一、二階堂ふみ、友近、長谷川博己

この映画は、もうめちゃくちゃ。ただ映画を撮りたいという欲望が、そのまま映画を撮りたいという欲望を描くことで成り立っている。
映画は、嘘。つくりもの。それがなぜおもしろいか。映画のなかの堤真一の台詞を借りて言えば「ファンタジーがリアリティーに勝ってしまう(勝ってしまっている)」からである。
ヤクザ同士の抗争。殺し合い。そのとき勝つのは、ほんとうはリアルな戦い方をする方だろうけれど、ファンタジー(夢/欲望)の強い方がリアルな問題点を乗り越えて勝ってしまうときがある。度胸とか、怨念とか、怒りとか。
で、どんな映画を見るときでも、私たちは(私は?)、そこにファンタジーを見ている。スピルバーグの「フライベート・ライアン」の冒頭の長い長い戦闘シーンさえ、現実を通り越して夢を見る。海のなかを銃弾が進む。それが兵士にあたる。血が噴き出る。血が海の色にとけて、まじる。こんなシーンを、あ、すごい、すごい、すごい、と思いながら見てしまう。そうか、こんなシーンをみた人間がいるのか、見てみたい--あ、書くと、とんでもなく変な感じだねえ。実際にその戦闘の場にいたら、そんなものに感心していられない。銃弾にあたらないように祈るだけだ。感動と現実は違うのだ。
うーん、まいるねえ。笑ってしまうねえ。
ヤクザの親分が、出所してくる妻が娘が主演する映画がみたい(女優になった娘に会いたい)と言う。その願いのために娘を主役に映画を撮る。監督は、街で見つけた映画オタク(ちょっと違うのだけれど、めんどうだから、そう書いておく)。で、映画を撮るとき、暴力団の抗争が起きる。あ、すごい、これをそのまま映画にすればいい。「仁義なき戦い」の「実録版」。そんなこと、実際にはできないのだけれど、映画だからやってしまう。
そのとき。
抗争が現実? 映画を撮っていることが現実? 抗争を映画にしてしまうという映画を、さらに映画にしてしまう--それは現実? 虚構? これは、いちいち考えるとめんどうくさい。つまり、どうでもいい。
ばかげたファンタジーに、みんなが夢中になる。映画にとられる方も、自分が死ぬか生きるかなのに、なせか映画という夢のなかで死んでいく(けっして死なない)という夢を見ている。映画を撮る方は、虚構ではとれない真剣勝負--実際に、首が飛び、銃弾で撃たれて死ぬからねえ、にわくわくする。こんなクオリティーの高い(偶然を必然に抱き込みながら)映像は二度とありえない。「映画の神様」が撮らせてくれている。
いやあ、あほくさい思い込み。でもねえ、でもねえ。私は映画を撮ったことなんかないけれど、わくわくどきどき。むちゃくくちゃなのに、ぜんぜんむちゃくちゃに感じない。うれしくなって、「あ、國村隼。主役なのに、抗争の前半で首刎ねられて死んじゃった」と大声で笑いだしてしまう。首が切られてごろん、じゃなくて、ロケットみたいに飛び上がってしまうからねえ。こんなの、嘘だねえ。嘘だけれど、ファンタジー。リアリティーを超える。
最後、監督ひとりが生き残り、「やった、やった、やった。生涯に一本の大傑作」と大喜びして道路を走る。撮影しながら死んでしまった仲間なんか関係ない。やちろん抗争で死んでしまったヤクザなんか知るわけがない。「映画だ、映画だ、だれも撮ったことのない映画」というはじける喜び。
いいなあ。
そうだよなあ、どうせなら、映画を超える現実を映画にしたい。そうすれば映画は、もう絶対的な存在になる。
この欲望は異常? 異常という正直が駆け抜ける。
(2013年10月09日、t-joy 博多シアター5)
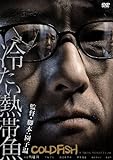 | 冷たい熱帯魚 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| Happinet(SB)(D) |