この映画は二重人格をトリックにつかったホラー、あるいは探偵映画なのかもしれないけれど、後半よりも女がシャワーをあびながらナイフで殺されるまでの部分がとても魅力的である。
女は男とふんぎりのつかない逢い引きをつづけている。逢い引き--というのは古くさいことばだが、女にはそういう古くさいことばがあっている。その逢い引きのあと、女は仕事場へもどる。不動産の案内所。そこへ金持ちの客がやってくる。大金をぽんと机の上において見せる。金を見せつけながら、女に色目をつかう。女は、客がいやらしい目つきをして見ることに対しては平気だ。セックスをすませてきたから、「御用済み」という感じなのだろう。意識は机の上の金に集中している。誰も、そのことには気がつかない。上司も、同僚の女秘書も、客が女に色目をつかっている、ということの方に気が向いているからである。男と女がいて、そこに何らかの交渉がはじまれば、誰だって、これらか二人はどうなるのか(セックスするのか)というところへ関心が向いてしまう。人間はすけべだからね。逢い引きをすませてきた女は、そういうことにも気がついているかもしれない。
で、重要なのは。
ここには二つの意識があるということ。性に関する思い、金に対する関心。女が金に興味を持つのは、その大金があれば、逢い引き相手の男とうまくやれるんじゃないかという思いもある。
映画はアンソニー・パーキンスの演じる「二重人格」に収斂していくのだけれど、被害者になる女も「二重人格」といえば、そういえるのだ。銀行に大金をあずけに行く、という仕事をしなければならないのに、頭痛といつわり早退を申し出、銀行へ行ったら、そのまま家へ帰ると上司に告げる。実際は、大金をもって、そのまま逃走するのである。女もまた「二重人格」と言おうと思えば、そう言ってもいいのである。平気で嘘をついているのだからね。
女は逃走しながら、上司や同僚、そして客のことを思い出している。ただ思い出すのではなく、その人たちが言うであろう「批判」を聞く。空想(想像)するを通り越して、しっかりと「確信」する。それは女の「肉体」のなかから溢れてくる、別の女なのである。女は「二重人格」どころか、「三重、四重人格」なのである。
その女がシャワーをあびながら殺される。そのとき女は悲鳴を上げることしかできないが、悲鳴とともに女は「多重人格」であることをやめる。「二重人格」という女より劣った男によって殺され、「肉体」に帰っていく。
女より劣った男というときの、劣ったというのは変な言い方だが、女が多重人格なのに対して男は「二重」と、肉体のなかに抱え込んでいる他者の数が少ない。男は男以外にもうひとりしか肉体に抱え込むことができない。
しかし、これはまた別な見方もできる。
男は自分と自分のなかの母という「二重人格」に苦しんでいるが、それは男のなかにいる「他者」がたったひとりだから苦しいのかもしれない。女のように、上司も、客も、同僚もというたくさん「人格」を自分の「肉体」のなかで競合していたら、母親に支配されることもないかもしれない。自分のなかに「他人」を存在させることができないことが、アンソニー・パーキンスの不幸だったのかもしれない。
ということは、しかし、映画とは関係ないことだね。
後半は映画のストーリーのためには必要な部分だけれど、映画としてはあまりおもしろくないね。殺されるまでがおもしろいので、ついつい最後まで見てしまうという映画だ。いまから思えば。(何度も見ているのでそう思うのかもしれないが。)
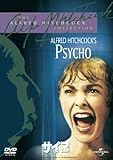 | サイコ [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| ジェネオン・ユニバーサル |