監督 ケン・ローチ 出演 ポール・ブラニガン、ジョン・ヘンショウ、ゲイリー・メイトランド、ウィリアム・ルアン、ジャスミン・リギンズ
映画には感想の書きやすいものと書きにくいものがある。ケン・ローチ監督「天使の分け前」はとても書きにくい。何が書きにくいかというと……。
ケン・ローチという監督は、他人に対する「親和力」がとても強い監督である、と書いたらあとは書くことがないからである。「親和力が強い」というのは、私の勝手なことばなので、ほんとうはもっと別な言い方があるかもしれないが。
違った言い方をすると。
ケン・ローチは、映画に出てくる人を嫌いにならない。そのまま、全部を受け入れる。生きているまま、動かしてしまう。ルノワールやタビアーニ兄弟にも同じ力を感じるけれど。
そして、ケン・ローチは生きている人間をそのまま応援するけれど、かといって応援しすぎて人生をねじまげるというようなこともしない。「そのまま」そこに存在させる。そしてそうやって生きていることが輝くのを待っている。そんな感じ。
映画に則して言いなおすと。
登場するのは、いわゆる「不良」である。すぐ暴力を振るってしまう主人公。盗み癖がとまらない女。無知な酔っ払い。でも、そういう彼らが社会でちゃんと働いていけるよう応援する人もいる。
主人公には人とは違った能力がある。嗅覚が強い。ウィスキーのテイスティングで香り、味の違いを指摘できる。--こういう人間を主人公にしてしまうと、その能力を生かして、主人公の出世物語をつくりあげてしまいそうである。主人公には恋人がいて、赤ん坊もうまれる。テイスティング能力をかわれて、主人公の成功物語が始まり、それに家族がむすびつく……いわゆるハッピーエンディング。
でも、ケン・ローチはそういうことをしない。主人公にできることは、そういう「成功」ではない。彼のまわりにいるのは、そういう「成功」をささえる人ばかりではない。もっとだらしない(?)。でも、生きている。そういう仲間と一緒になって、そういう「成功物語」もあるかもしれないけれど、それじゃあ、嘘になってしまう。
嘘にならない前に、現実に戻り、そこで生きる。
不良仲間なので、まず、盗みをする。すばらしいウィスキーがみつかった。オークションがある。その会場に潜り込んで、樽ではなく、樽からビンにちょっと盗み出す。そしてそれをほしがっている人間に売りさばく。--これって、まあ、犯罪なのだけれど、もともとウィスキーには蒸発分が見込まれている。蒸発しながら味がよくなる。これが「天使の分け前」と呼ばれるもの。その「天使の分け前」を増やすだけ。自分たちのものにするだけ。
これを否定してしまったら、人間は生きるのがむずかしい。積極的に「やれ」というのではないけれど、そうしたからといってそれをとがめない。そういうことは「個人」の問題なのだ。自分で切り開いた道なのだから、それをやればいい。そういう「天使の分け前」の領域というのは社会がもっていないといけないのである。あいまいな、どこかへ消えてしまう何か。けれども、そのあいまいなものによって「味」がよくなる。そういうもの。そういうあり方に、ケン・ローチは寄り添っている。この寄り添い方が、人間を嫌いにならない、人間を好きになるということ。受け入れるということ。
で、最後の方。
盗み出した一本を主人公は、自分を受け入れてくれたウィスキー好きのおじさんにささげる。このおじさん、それが盗み出されたものであることをすぐにわかる。わかって、そのことに対して怒るのではなく、「あいつめ」と受け入れる。ここにケン・ローチがそのまま出で来る。いいなあ。
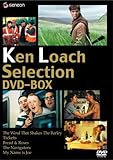 | ケン・ローチ 傑作選 DVD‐BOX |
| クリエーター情報なし | |
| ジェネオン エンタテインメント |