おもしろいシーンがいくつもある。いちばん印象的なのが少年と父とのやりとりである。父は少年に向かって「おまえなんかいらない。生まれてこなければよかったんだ。殺してやりたい。殺してしまえばすっきりする。なんでも好きなことができる」というようなことを言う。父は何度も何度もくりかえしているので、少年はそのことばをすっかり覚えてしまっている。それなのに父は毎回、それを初めて言ったと思う。言うたびに、「やっと言いたいことが言えた。すっきりした」と言うのだ。
この映画には詩が重要な役割を果たしているが、詩のあり方と、この父のことばを対比させると不思議なものが見えてくる。
父親は「気持ち」を語っているが、それは「気持ち」ではない、ということだ。父親のなかにある「感情(思い)」には違いないのだろうけれど、それは実は「気持ち・感情・思想」になりきれていない、あいまいなことばなのである。父親の思想は酔っぱらって不機嫌であるということだけなのである。父親の肉体となって支えている「思想」は、酔っぱらってくだをまくと、そのとき「世界」を忘れられるという「事実」である。酔っぱらって、息子にからみ、何事かを言う、セックス相手の妻を探す--その肉体が「思想」である。「おまえを殺せばすっきりする」というのは、「思想」になりえていない、未生のことばなのである。だから父親は何度も何度も、それを忘れてしまう。そのことばといっしょに「気持ち」は生まれてはいないのだ。
この映画は、そういう生まれていないことばと対比させる形で、少年のなかからことばが生まれるまでを克明に描いている。ことばはある年齢になればだれでもがしゃべる。しかし、しゃべるからといって、それがことばであるとは限らないのだ。多くは自分のことばではない。だれかのことば。それを、うのみにして反復している。父の「おまえがいなければ云々」もちちのことばというより、「流通言語」なのだ。
たいていは「流通言語」だけで暮らすことができる。しかし、ときには自分のことばが必要になる。自分の「気持ち」をはっきりさせるための「ことば」が必要になる。「気持ち」をつくる必要があるのだ。「気持ち」は最初からあるのではなく、つくりあげていくもの、鍛えていくものなのだ。鍛え上げられた気持ちが「思想」なのだ。
少年は父を発作的に殺してしまう。そのとき「気持ち」が生まれる。いままで知らなかった「気持ち」が「肉体」のなかに生まれてくる。だれも教えてくれなかった「気持ち」。それをどうしていいのか、少年はわからない。手探りである。誰かが誰かを殺そうとしている。そう気づいて少年は、その殺人者を襲う。そのとき別の人が少年を助け「逃げろ」と指示する。これはいったい何? 何が起きている? 少年はわからない。自分の「気持ち」がわからないように、他人の「気持ち」もわからない。「気持ち」はわからないのに、「肉体」がある。そして、その「肉体」のなかで何かが動いている。
その動いているものを正確につかむために、少年は苦しむ。
これは、すごい映画だなあ。--この少年の苦悩を、東日本大震災後の東北の風景(現実)と重ねるとき、少年が自分のひとつだけ残った気持ちをことばにするラストがとても美しく輝く。「気持ち」はつくっていくもの、そして「気持ち」はつくれるものである。「気持ち」をつくれる力が人間にはある。
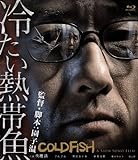 | 冷たい熱帯魚 [Blu-ray] |
| クリエーター情報なし | |
| Happinet(SB)(D) |