この映画はとても変わっている。タイトルから、驚いてしまう。なぜ「フーバー」が省略されているのだろう。私は映画館でチケットを買う時「フーバー」と言ってしまって、係員から「J・エドガーですね」と念を押された。えっ、「フーバー」という名前はタイトルにないのか、とその時気がついた。そうか、イーストウッドはフーバーを題材にしながら、フーバーを描いていないのか。タイトルはファーストネームさえイニシアルにしている。
では、何を描いたのか。
愛、だね。
表面的にはアメリカへの愛。国家というか、理想の体制への愛。そこには不思議な不寛容がある。なぜ、他人を寛容できない? それは、言いかえると自分を寛容できない、ということだね。緊張した時の吃音のみっともなさ。女性ではなく、男性の方にひかれること。それは、アメリカの理想、あるいは母親の理想とは違う。だから、肯定できない。肯定すべきは「理想」だけである。その「理想」実現のためなら、違法行為もかまわない。あるいは、そうすることが「違法」なら、「違法」にならないように法律を作りかえればいい。――この、激烈な情熱の不思議さ。
もしフーバーがこの情熱を、彼自身の内部にうごめく本能を実現するために傾けていたらどうなっただろうか。簡単に言うと、男にひかれるという本能は間違っていない、男にひかれてもいいのだ、と言い切ってしまえたらどうなっていただろう。ゲイに対する世間の不寛容に対して怒り、その不寛容を打ち破るために情熱を傾けていたら、どうなっただろう。
情報管理、情報操作のエキスパートではなく、性の解放のリーダー、マイノリティーの解放のリーダーになっていたかもしれない。
自己の内なるマイノリティーに対して不寛容を貫き、その反作用のようにしてアメリカ社会のマイノリティーを拒絶する。あるいは社会的悪を撲滅する。その激しさの奥に、彼自身のマイノリティー、悪とみなしている本能が燃え上がっている。
この葛藤を、イーストウッドは相変わらずの慎み深い抑制で描き切る。描きようによってはどこまでもエキセントリックになるところを、エキセントリックを避けている。ディカプリオに対しても、演技を拒絶して、ただそこに存在させている。演技は必要がない。カメラが演技をする――カメラの演技を受け入れるのが役者の肉体である、とでも言うように。
たしかに映画はそういうものだろう。カメラが演技をし、役者は肉体を提供する。カメラの演技が世界を切り取るのであって、役者の肉体が世界のフレームを作るわけではない。
このときのイーストウッドの「カメラの演技」というのが、相変わらずすごい。語りすぎない。完璧に言い切らない。映像の頂点寸前で閉じる。一番いいシーンは観客の想像力の中にある。出だしの、1919年当時の司法長官の家が爆弾テロ事件の爆弾シーンが象徴的である。「ヒア・アフター」の津波のシーンもそうだったが、もっと強烈なシーンがあるはずなのにその手前で終わる。7語れば10わかる――それが人間だと信じている。10語れば、ひとは12を想像してしまう――つまり反応に余剰(過剰)が生まれ、それが世界を汚してゆく。あ、まるでフーバーの世界への向き合い方だね、この余剰・過剰反応は。イーストウッドはこういう余剰・過剰が大嫌いなひとのように見える。
この余剰・過剰を排除した映像は、ディカプリオとアーミー・ハマーの愛のシーンにすばらしい輝きを与えている。ディカプリオがハマーを見染める。ハマーがディカプリオに見染められたと直感する――これを目の色の変化、目の輝きの変化だけで見せる。ふーん、愛が行き交う瞬間は、直感は、こんなに短く、こんなに強いのか、とびっくりする。男も女も、この直感の力に差はないね。そのあとの、2人が手を握り、握りかえすアップもいいもんだねえ。秘密の愛が行き交う感じが濃密で、あ、私もディカプリオの手を握り返してみたい、なんて思ってしまったなあ。(あ、フーバーじゃなくて、ほかの役をやっているときがいいけれど。「キャッチ・ミー、イフ・ユー・キャン」ならうれしいけれどね、なんちゃって。)で、この抑制が利いた映像が下地にあるから、2人が喧嘩し殴り合うシーン、キスするシーンが、感情の発露として非常に効果的。最初から燃え上がっていたら、この喧嘩はありふれた痴話喧嘩になりさがるからねえ。
ナオミ・ワッツ、ジュディ・デンチとディカプリオの愛も、とてもおもしろい。2人の女性の間で、ディカプリオは均衡を保っている。1人ではだめなのだ。献身的な女性と激しく叱ってくれる女性の2人がいて、ディカプリオは安定する。フーバーが生涯独身だったのは、二面性を持つ女性がいなかったということかもしれない。副長官との愛がつづいたのは、彼がフーバーの行動を実践的に支えると同時に、「それは違法なのではないか」と批判もするという二面性をもっていたのではないのか、という気がする。
――と、ここまで書いてくると、この映画のもうひとつのテーマも、「肉体的」に見えてくる。ディカプリオの肉体として見えてくる。つまり、アメリカの現代史の光と闇が、フーバーの行動のなかで不思議なバランスをとって動いている、ということがわかる。何にでも二面性がある。その二面性を、ひとつの「肉体」として具現化したのがフーバーなのである。
ディカプリオは、このイーストウッドの要求をきちんと把握し、しっかり演技していた。名演である。ナオミ・ワッツもジュディ・デンチもよかった。リンドバーグを演じたのは誰かよくわからないが、彼もよかった。
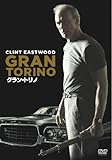 | グラン・トリノ [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| ワーナー・ホーム・ビデオ |