(2004年1月14日に、panchan worldで一回感想を書いている。下の方に、それを再掲する。このサイトは、ある事情で閉鎖状態。)
福岡の「ソラリアシネマ」が閉館する前の特別企画で、「ミスティック・リバー」を上映していたので、もう一度見てみた。
なぜ、この映画がアカデミー賞作品賞、監督賞を受賞できなかった不思議でしょうがない。「ロード・オブ・ザ・リング」1、2が受賞を逃し。3も逃すと無冠に終わる――という配慮から票が流れたんだろうなあ。で、イーストウッドにはお詫びのようにして「ミリオンダラー・ベイビー」の時に賞が来たんだけど。「ミリオンダラー・ベイビー」も傑作だけれど、やっぱり「ミスティック・リバー」の方がすごい。救いがないというか、カタルシスがないところが、賞には向かないのかもしれないけれど。
どこが、すごいか。
イーストウッドの映画はどれどもそうだが、映像に抑制がある。演技にも抑制がある。もう少し見たい、もう少し見ることができればじっくり共感できるのに、と思う寸前で映像が切り替わる。
そうすると、私の想像力がかってに働く。映し出されなかった表情を、自分の内部に感じるのである。
多くの映画が、クリマックスというか、見せ場をじっくり見せるのとまったく違う。多くの映画は観客が涙を流し、――それだけではなく、あ、隣の人も泣いている、みんな泣いていると気がつくまで、つまり、映画を忘れ、観客の変化にまで気がつく余裕が生まれるまでクライマックスを映し続けるのとはまったく違う。
この映像文法、映像リズムをイーストウッドがどうやって身につけたのかわからないけれど、とても感心する。
前回見た時は、ティム・ロビンスの演技にびっくりしたが、今回はショーン・ペンの演技に驚いた。
たぶん7年前に見た時は、ショーン・ペンの演じている役の「過去」が、最後の方になった突然噴出してきて、事件がどんでん返しのように解決するというか、構造がはっきりする部分が「種明かし」のようで、それが気になって、感想を書くとき、つまづいたのだと思う。今回はストーリーが分かっているので、「種明かし」は気にならず、その分、ショーン・ペンの演技そのものを見ることができた。
「過去」の表し方、特に、娘のボーイフレンドを拒絶しようとするときの演技がすごい。人が「なぜ、あの少年が嫌いなのか」と聞くが、その理由が演技からまったくわからない。不可解である。この「不可解」がすごいなあ。わかっては、困るのだ。ショーン・ペンは、そのわかっては困る、という演技を、演技している。嫌っている――のではなく、娘と一緒になってしまうと人生が複雑になりすぎる。「過去」がいつも「目の前」に存在してしまう。それが、困る。誰かに言いたい。でも、言えない。そして、隠す――その演技の、妙に中途半端な、つまり感情が分かりにくい演技を演技している。うーん。
これが、観客には分かってしまっているティム・ロビンスの演技と交錯する。それが演技だけじゃなく、ストーリーそのものになっていく。「過去」が「いま」を突き破って、「未来」が思いもかけない方向へ動く。
でも、その「未来(というか、現在)」を、イーストウッドは、また深追いしない。それは深追いしても、結局、カタルシスにはならないからねえ・・・。
逆にいうと、イーストウッドはカタルシスに終わらせない映画の終わらせ方を知っているということかなあ。
****以下は2004年の感想**********************
映像がどのシーンをとっても非常に抑制が効いている。品がある。
そして、その抑制の効いた映像の積み重ねによって、悲しみが静かに静かに積もっていく。
俳優人の演技も抑制が効いている。けっして大げさにならない。
クリント・イーストウッドの音楽も、音楽を主張せず、しかも音楽でありつづける。形にならない不安、こころのように、断片的に響き、その断片がずーっとつながりつづける。
主役の3人の運命のように、重なり、離れ、また重なることで、深い深い川のように流れる。ゆったり、ぶきみに、哀しく。
(音楽に★1個追加。)
*
結末の描き方に、イーストウッドの人間観察の深さを強く感じた。
3人の少年の1人はつらい過去によって苦しみ続けた。
そして、残された2人は、これからつらい時間を生き続ける。
遠い昔、2人(ショーン・ペンとケビン・ベーコン)は友達の1人(ティム・ロビンス)を救えなかった。3人のうちの2人(ショーン・ペンとケビン・ベーコン)は偶然被害者にならず、1人(ティム・ロビンス)は被害者になった。そして今、その被害者(ティム・ロビンス)はもう一度被害者になり、1人(ショーン・ペン)は加害者になり、もう1人(ケビン・ベーコン)はその関係を察知しているが「証拠」を見出していない。また、その1人(ケビン・ベーコン)はもし事件の解決がもっと早ければティム・ロビンスが被害者にならずにすんだ、ショーン・ペンが加害者にならずにすんだことも知っている。
偶然が、何かのはずみが、人生を狂わせる。そして、それを人はどのように生きていけばいいのか、誰も知らない。どうすれば人生が狂わないのか、そのことを知っている人間は誰もいない。
本当の哀しみとは、たぶん、そうしたことなのだろう。
*
映像――。
抑制が効いていると最初に書いた。抑制と同時に、非常に工夫された映像であるとも思った。
何度が木を、木の葉を、木の葉越しの空の映像が出て来る。たとえば、少年のティム・ロビンスが監禁場所から逃げるシーン。何を見ただろうか。彼が本当に見たのは、木の葉と空だったのか。誰も自分をささえてくれなという不安、恐怖だったかもしれない。
それとは逆の映像がひとつある。(いくつかあるかもしれないが、私が思い出せるのはひとつだ。)
ショーン・ペンが娘が殺されたと知って取り乱す。警官に取り押さえられながら叫ぶ。天を仰いで叫ぶ。――このシーンだけが天からの視点である。
ショーン・ペンは叫びながら何を見たのか。何を見なかったのか。その叫びを、苦悩を見ていたのは誰なのか。
そして、そのときショーン・ペンに自分の哀しみが他人に理解されているという自覚があったかどうか。
彼には、たぶん、ない。
しかし、彼が天を仰いで絶叫するとき、その哀しみは多くの警官によって支えられている。共有されている――この点が、実は、ティム・ロビンスの場合とまったく違う。
そして、そのまったく違うと言うことをショーン・ペンはこのとき知らないのだ。
彼がそれを知らない、けれど多くの人がショーン・ペンが苦しんでいるということを瞬時のうちに理解、共有しているということを天からの視点で完璧に描いてみせる。
(このシーンが、この映画で一番美しい。)
一方、ケビン・ベーコンが見ているのは何か。
天を仰がない。天を見つめない。そして、天もケビン・ベーコンを見下ろしてとらえることはない。
彼が見ているのは、今、彼の目の見えるところにいる妻ではなく、見えない場所にいる妻――そして、その口元だ。ことばだ。
彼は、今、ここにいない人間が実は自分を支えている――そう想像して、その想像を頼りに自分を律している。生きている。ティム・ロビンス、ショーン・ペンの視点が垂直に動くのに対して、ケビン・ベーコンの視点は水平に動いている、といえるかもしれない。
*
また別の視点から……。
ティム・ロビンスの孤立、絶対的な孤独は、妻が彼の言動を信じないところにも描かれている。つらい過去、こころの苦悩を語っても、理解されない。逆に誤解される。妻の不信をまねいてしまう。誰も彼を支えない。
監禁場所から逃れながら少年のティム・ロビンスは天を見つめた。木の葉、空を見つめた。絶対的な何かにすがろうとしたのかもしれない。
皮肉なことに(ショーン・ペンのことについて後で書くが、そのとき、「皮肉」の意味を補足できると思う)――彼の孤独、苦悩は、恐怖のためにティム・ロビンスを拒絶する妻によっていっそう深まる。
妻は恐怖ゆえにティム・ロビンスを疑う。そして、その疑いがティム・ロビンスを完全な孤独に陥れる。
誰ひとりティム・ロビンスを支えてくれないと感じてしまう。本当に恐怖を感じているのはティム・ロビンスなのに、誰もその恐怖について理解してくれないという絶望が彼を孤立させる。
一方、ショーン・ペンには犯罪者の仲間がいる。絶対的にショーン・ペンを支えようと思う妻がいる。
ショーン・ペンは娘が殺されたと知ったとき、天を仰いで絶叫した。その瞬間、彼とは直接関係のない警官が彼の絶叫を支えた。そしてそのあとは仲間が、妻が彼を支える。彼のしていることが正しいかどうかではなく、彼が必要だから(彼なくしては生きていけないから)、彼を支え、彼を守るために動く。
ティム・ロビンスの妻が不正義に対する恐怖のために動いたのとは逆に、正義に目をそむけた人がショーン・ペンを支えている。ショーン・ペンを支えている人間は、ショーン・ペンのしていることが正義であるかどうかではなく、自分たちと常に手を取り合っているかどうかなのである。
ショーン・ペン自身の行動規範も「連帯」である。
裏切る奴は許せない。行動するとき支えあわない人間は許せない――というのがショーン・ペンの役どころである。
他方、ケビン・ベーコンを支えているのは何だろうか。「正義」。人が行動するとき何を基準にすればいいか、そういことを少しずつ積み上げてきた結果としての「法律」。そういうものだろうか。
そうしたものを手がかりに、人の行動を調べていく。(犯罪捜査をしていく。)そうすると、そこに「正義」(何が間違っているか、誰が間違っているか)だけではとらえきれない人間の苦悩が浮かび上がってくる。哀しみが浮かび上がってくる。
犯罪捜査の結末には人間の苦悩、哀しみなど二次的なものである。しかし、その二次的なものが人間全てを結び付けているものだということが浮かび上がってくる。
*
また別の視点から……。
この映画では、ケビン・ベーコンが、なぜか私にはクリント・イーストウッドに見えた。
目の表情が似ているかもしれない。演技が似ているかもしれない。――ということとは以上に、たぶん上に書いたことと関係があるかもしれない。
ケビン・べーコンの役どころは、犯罪を捜査するというストーリーを演じながら、実は犯罪そのもの(犯人探し)ではなく、その犯罪が起きたときの人間の引き起こす苦悩、哀しみの総体を浮かび上がらせることである。
犯人探しなど、どうでもいい。犯人が誰であろうとどうでもいい。
重要なのは、その犯罪が起きたとき、その周囲で起きる人間の感情である。
そういうものを浮かび上がらせるために、脇役に徹し続ける。ティム・ロビンスやショーン・ペンのように、顔で(表情で)演技をしない。目立たない。ティム・ロビンス、ショーン・ペン、その妻達の表情(感情)を浮き彫りにするために、あくまで引いた演技を続ける。
最初に音楽のことを書いた。
たぶんイーストウッドは音楽に対する本能的把握が鋭いのだと思う。
いくつかの音が重なり合い、ひとつながりの音楽になり、それぞれの楽器が独特の表情を持つことで、それが豊かになる。
そのとき自己主張するだけではなく、他の音を支えることに徹する音も必要なのだろう。そういうバランス感覚がイーストウッドにはあるのだろう。
思い返せば、あの『ダーティー・ハリー』のときでさえ、イーストウッドは相手役を引き立てるような演技をしていたような気がする。
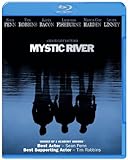 | ミスティック・リバー [Blu-ray] |
| クリエーター情報なし | |
| ワーナー・ホーム・ビデオ |