アフリカ(どこの国だったかな?)とデンマークで繰り返される暴力。暴力の質も、カメラがとらえる風景もまったく違うのに、違って見えない。アフリカであることを忘れる。デンマークであることを忘れる。ふたつの国の間にある「風土(風景)」の違いを忘れ、暴力の違いを忘れる。
なぜだろう。
カメラが、暴力描写に焦点を当てていないからだ。いや、これは正しい言い方ではないなあ。少年が空気入れで学校のボスを殴るシーンはあるし、自動車工場の男が医師を殴るシーンがあるし、何よりも腹部を切り裂かれた妊婦の描写がある。それでも、「暴力描写」という気がしない。映像に誘われて、「暴力の快感」に酔う、ということがない。暴力のアドレナインとは遠い所で、すべてがとらえられている。
そんなことでは、何の解決にもならない――という声が聞こえてくるのだ。どの暴力描写からも。
たとえばアフリカの暴力のクライマックス。妊婦の腹裂きの首謀者ビッグマンに対して怒りが爆発してしまう医師。そして、命を助けるのが仕事といって周囲の反対を押し切って治療したはずのビッグマン、そのビッグマンがリンチされるのを許してしまう。そのときカメラはリンチの暴力をとらえると同時に、医師の絶望する表情を映し出す。暴力を暴力で封じても、報復を生むだけ――という「信念」があるはずなのに、どこかで暴力を許してしまっている。自分の「怒り」を許している。抑えきれない「怒り」というものはあり、それはどうしても噴出してしまう。
そういう絶望の自覚。それが、静かに映像の底に横たわっている。
――と、ここまで書いてきて、この映画のテーマが「自覚」だと気づいた。
象徴的なシーンがある。いじめられっ子の父であり、医師である男。彼はこどもの喧嘩の仲裁に入り、相手の父親に殴られる。しかし殴り返さない。それを見た子供から「相手の男を恐れているからだ」と批判される。医師は、男を恐れていないということを子供たちに証明されるために、わざと殴られる、殴られて見せる。そのあとで、「あの男は暴力では何も解決できない愚かな男だ」と説明する。
それに対して、いじめられっこの友達の少年は、「でも、あの男はそれを自覚していない」という。
これはとてもするどい指摘だ。
誰もが自分の愚かさを自覚していない。自覚できない。そのために暴力が横行している。そして暴力とは、誰かを殴るとか、肉体的な傷をおわせるという形以外でも行われている。そのことに対する自覚はもっと難しい。
その例として、がんの妻の安楽死を選んだ夫の、子供に与えた「暴力」、浮気を謝罪する医師を許さない妻の「暴力」が描かれる。少年が、安楽死を受け入れた父を許さないのも暴力である。「自覚」の問題を指摘した少年にも、自分のことは「自覚」できない。自覚されない「暴力」は、他者を「許さない」という形で噴出する。そして、この「非寛容」こそが、この映画が追い続けている「暴力」の問題である。
様々な暴力があふれている。
スウェーデンから移民してきた医師の「発音」の間違いを許さない自動車工場の男の「非寛容」も、手で医師を殴る以上の暴力である。
世界のいたるところに、いつでも「非寛容」という暴力が寄り添っている。そのことは、アフリカもデンマークも変わりがないのだ。世界中、どこも同じなのだ。――この深い哲学が、絶望が、映画の視線を統一している。そのために、映画がアフリカを描こうが、デンマークを描こうが、「同じ次元」として映像に結晶するのである。
このテーマにこたえた出演者の演技がまたすばらしい。怒りを内に抱え込みながら、どうしていいか分からない――その感じが、主要な人物に共有されていて、その「感じ」が映画全体を支えている。
それと。
映画の冒頭に出てくるアフリカの子供たち。医師の乗ったトラックを追いかけて「ハウ・アー・ユー」と叫び続ける。その笑顔の美しさ、明るさ。あ、そこには「絶望」がない。状況は絶望的だが「絶望」がない。他者を完全に許している。「ハウ・アー・ユウ」と相手を気遣っている。彼らに「ハウ・アー・ユー」が相手を気遣うことばという「自覚」はないかもしれない。もしかすると「ギブ・ミー・チョコレート」と同じ気持ちかもしれない。でも、いいなあ。そんなこと、どうだって。「ハウ・アー・ユー」と言っている。そう信じるとき、私にはなんとなく「希望」が湧いてくる。その「希望」とアフリカの明るい光、乾いた空気がとても似合っている。
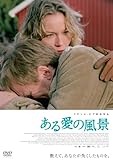 | ある愛の風景 スペシャル・エディション [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| 角川書店 |