とても笑えるシーンがある。主人公が「悪魔払い」をみた後、「悪魔」ではなく精神疾患なのでは、と疑問を抱く。それについて、アンソニー・ホプキンスが「緑のヘドを吐いたり、首がぐるっと回ったりしないからか」というのである。
この映画は、実際に生存する「エクソシスト」の誕生までを描いているのようなのだが、彼らもまた、あの「エクソシスト」を見たという設定だね。この台詞だけで、「もうこの映画はフリードキンの映画に負けています」と宣言しているようなもの。いやあ、ウィリアム・フリードキンの切れのいい映像と比べると、これはもう物足りなすぎる。緑のヘドにしろ、首がぐるりと回るシーンや、ブリッジしながら階段をおりてくるシーンは、グロテスクでこけおどしのような印象があるが、実は、とても美しい。いつだったか忘れてしまったが、私は「リバイバル」か「名作上映会」か忘れたが、2度目に見たときの印象が1度目の「びっくり」「ぎょっ」とはまったく違っているのにおどろいてしまったことがある。どのシーンも非常に美しい。シャープである。映像にとどこおりがない--というのがフリードキンの映画をあれだけヒットさせた理由である。
この映画がいくらか「ていねい」だとすれば、見習いの「エクソシスト」が悪魔というものを信じていなくて、悪魔に取りつかれている少女を精神疾患と見ているということである。精神病理学の視点で少女を観察し、また科学的な治療が必要だと主張する点だろう。--でもねえ、これだってフリードキンの作品に比べると、物足りない。
フリードキンの作品では、精神病理学を説く神父がでてきたかどうか忘れたが、ちゃんと病院がでてきた。病院でCTスキャンをとり、脳を調べている。そのレントゲンの写真もスクリーンにずらりと並んだ。「科学」をきちんと描いている。「ことば」ではなく、映像としてスクリーンに展開している。そういう「基本」があるから、「悪魔」が生きてくる。「ことば」精神科医に見せるべきだ、科学的な治療すべきだというだけでは、映画にはならない。安っぽい小説にしかならない。(小説でも、きちんとした小説なら「精神科医に見せるべきだ」だけではなく、精神科医が登場し、少女とどう向き合ったかを具体的に書くだろう。)科学の不在が、同時に神学(信仰)の不在へもつながっていく。バチカンで「エクソシスト養成講座」が開かれ、その講義にパソコン(プロジェクター)を使った映像が活用されるところなど、ばかばかしくてどうしようもない。パソコンなど、もはや「科学」ではないのだ。ここに描かれる「信仰」は「現実」とまったく向き合っていない。だから、「信仰」になっていない。「ストーリー(お話)」で終わっている。
クライマックス(?)で、エクソシスト見習いの主人公が「悪魔を信じる。それは髪を信じるからだ」と言うことで、悪魔に打ち勝つところなど、私は笑ってしまったなあ。映画なんだから「ことば」でそんなことを言ったって説得力がない。こんなロジックに悪魔が負けるなんて、悪魔の資格がない。詭弁を突き破って暴れる悪魔の魅力がまったく描かれていな。だから神も描かれていない。
冒頭の遺体処理(おくりびと、のような仕事)が少していねいで、シンクに流れる水の映像や、電信柱(と電線)などの街の風景がわりと「なま」な感じでおもしろかっただけに、これではどうしようもないなあ。
アンソニー・ホプキンスも前半はいいのだが、悪魔にとりつかれてからが、演技になっていない。手が震えるシーンなど、おかしくない? 抑えようとしても震えるから震えになるのに、あんなにぶるぶる震えたら、震えの強調になる。観客に、はい、いまアンソニー・ホプキンスは悪魔にとりつかれています、と宣伝してしまっている。それじゃ、こわくないでしょう。どっちかわからない、というのが一番こわいのだから。メーキャップ技術はフリードキンの時代より格段に進んでいるはずなのに、印象ではリンダ・ブレアのメーキャップの方がアンソニー・ホプキンスのメーキャップよりシャープだ。アンソニー・ホプキンスの牧師館(その室内)も、安直なセットなのか、あまりに「時間」を感じさせない薄っぺらな印象で、舞台をローマにする必要がまったくない。
この映画に手柄があるとすれば、フリードキンの「エクソシスト」は大傑作だったと証明したことかもしれない。
(2011年04月27日、中州大洋3)
*
今月のお薦めの3本
1 シリアスマン
2 SOMEWHERE
3 神々と男たち
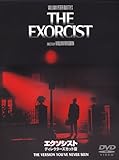 | エクソシスト ディレクターズカット版 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| ワーナー・ホーム・ビデオ |